次男に蹴られたひじに新しいシップを貼り付けて、
私は、深呼吸をひとつした。
―――今、私と子供との関係は、転換期なんだ。
今まで、私が言ったことは、
どんなに身勝手でもひとりよがりでも
子供たちにとっては、
「【お母さん様】が言ったこと」
として通用していたのだ。
お母さんはお母さんだから、大好きだから、
お母さんの言うことは「合ってる」と思っていた。
しかし、彼らは、そろそろ、
お母さんがお母さんであるにもかかわらず、
お母さんの言うことが「合っていないことがある」
ということに気付き始めたのだろう。
次男が最近、宿題や時間割を揃えるのを
全然しないことに困り果てている私がいる反面、
当の次男は、こう思っている。
今、いい絵が描けそうだ。
忘れないうちに描きたい。
どんどんいい線が描けていくぞ。
楽しいな。すごいぞ。面白い!
・・・・・・なのに、さっきからお母さんは物凄く怖い顔で僕の側にひっついて
「宿題宿題宿題宿題宿題宿題宿題宿題」
と怒鳴っている。
うるさいんだよ。ちょっと待ってよ。
後でちゃんとやるから。
ああ、うるさくて集中できない。
なんだよ、後でやるって言ってるのにしつこいんだってば。
あっ、画用紙を取り上げられた。
何するんだ! 今描かなくちゃ忘れちゃうのに!
どうしても描かなくちゃダメなのに!
お母さん、なんてことをするんだ!
いつも僕の絵を誉めてくれるのに、
最近どうして絵を描くと邪魔ばかりするんだ。
馬鹿。おかあさんの馬鹿。
あっ、なんでぶつの?
僕の絵を邪魔したお母さんが悪いのに、
なんで僕がぶたれなきゃならないの?
馬鹿。お母さんの馬鹿野郎!
あっ、お母さんが先にぶってきたのに、
僕がぶち返したら、お母さんが鬼みたいに怒った。
なんでよ! お母さんが悪いのに、
何でまたぶつの!
ぼくもまたぶつぞ!
あっ、10倍返ししてきた!
痛い、イタイイタイ!
馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿!
もう、こんな家出て行く!
もう夜だけど、出て行く!
お母さんが馬鹿だから出て行く!
次男の絵や工作は、何ににもとらわれていない。
時間にも、世間体にも、常識にも、約束にも、
みんながとらわれてしまっているものすべてから、
彼の作品は、自由なのだ。
だから、私は彼の描くもの作るものを愛し、
画用紙やチラシの裏や、折り紙や牛乳パックやヨーグルトのパック、
トイレットペーパーやラップの芯やプラスチックトレーなんかを
いつもいつも山のように用意していた。
兄弟たちもみんな、物心つく頃から図画工作には異常に燃えている。
しかし、次男以外は、製作と生活とを同時に進行できるのだ。
次男は兄弟の中でも桁外れに夢中になってしまうタチで、
何かを作り出したら、宿題も学校も、友だちもゲームも、
頭から飛んでいってしまうのだ。
思いついたものを形にするまで、
何かにとり憑かれたように無心になってしまう。
次男は、図画工作以外に、「面白いこと」にも
異常なほど夢中になってしまう。
それは大抵「テレビ」だったりするが、
それ以外の「犬」などでもあったりするのだ。
次男は犬年だというだけで、
自分を犬の化身だと思っているふしがあり、
入学当初、登校班でみんなと学校に行くときも、
電柱ごとに立ちションをしていたらしい。
ある時は「おしり」が面白い、と思ったらしく、
校庭で「優等生」で通っている長男と会ったとき、
その友だちに向かって自分のしりを出し、追い掛け回したらしい。
長男は「本当にあれ、君の弟なの?」
とみんなに驚かれ、心底困っていた。
そんな愛すべき(?)キャラクターだった次男が、
最近学校でも家でも暴れまくって人を怪我させているのは、
相変わらずの「次男ワールド」を貫かせてくれない周りの事情にもあった。
今までは、ほほえまれていた自分が、だんだん苦笑されるようになり、
更に嘲笑され、けなされ、
(なんでみんな僕を馬鹿にする? 僕はダメな子なのか?)
と思い始めているからなのだ、と思う。
ある晩、夕飯が終わっても次男はまだテレビに夢中で、
全然宿題をしないので、長男がテレビのスイッチを切ると、
次男が逆上して長男を蹴った。
私が飛んでいって次男のお尻を叩くと、更に逆上し、
私に掴みかかってきた。
私も次男に馬乗りになって「宿題するか!」
と威圧するが、体格のいい次男が暴れると
その足や手が当たって、私自身もあちこちあざだらけになってしまった。
次男の振り回したゲンコツが私のアゴに当たり、
私は一瞬頭が真っ白になったが、ここで負けてはいかんと思い直し、
(虐待?)と自問自答しながらも次男の頬を何往復もビンタした。
「親に手を上げていいと思ってるのか!」
「悪いことをして怒られて、逆ギレして! 反省しろ!」
私も次男も、痛いばかりで、ちっとも相手の気持ちが伝わらなかった。
お互いに痛すぎて悲しくなり、どちらからともなく脱力し、
部屋の端と端に分かれて座った。
アゴとひじが青くなって腫れてきた。
痛いし、悲しいし、私は、ただ黙ってアゴをさすっていた。
次男を見ると、ほっぺたが赤くなっている。
泣いてはいないが、驚くことに―――
何とも悲しそうに畳の一点を見つめているではないか。
母に叩かれ責められて、この世のどこにも居所がないような、
怖いくらいの悲壮感が漂っていた。
私は、鞭で打たれたようなショックを受け、
私そっくりの次男の顔を見た。
それは、30年前、父に連日殴られ、
この世に居所をなくした日の私の姿そのものだった。
私は家族に悟られないように声の震えを抑え、
「お前、淋しいんじゃないのか?」
と、次男に静かに言ってみた。
次男の顔は、みるみる歪んでいき、
肩で息をして、激しく泣き出す寸前だった。
「こっち来てすわんな」
私の横に座った次男の肩を抱き、
「淋しくて、悲しかったんだね」
と言うと、静かにうなづいた。
―――大丈夫。この子はいい子だ。
急いで、慌てて、周りの目を気にして、
ぶってはダメだ。ゆっくり話していこう。
・・・・・・と、次男の横に、何か強い気配を感じ、
見ると、長男が青い顔をして目を泳がせている。
「お前も淋しいんだろ」
私が言うと、長男は、ハッとして私を見た。
大きなくりくりの目に、涙がにじんでいた。
「お前もこっち来な」
次男の反対側に長男を座らせ、私を挟んで長男次男と3人、
肩を組んで横に座った。
「2歳になった途端に次々にアカンボがうちに生まれて、
お前、遠慮して全然甘えられなかったね」
私がそう言うと、長男は
「お母さんの隣りに寝たいなあ、ってずっと思ってたよ」
と言って笑った。
気が付くと私の膝の上には、甘え上手な末っ子の四男が座り、
背中には三男がおぶさっていた。
4人の小さな子供たちが吸い付く磁石のように私の胸元に集まって、
じっとしている。
―――私が変わらなくちゃ。
子供たちは毎秒、大きくなっていく。
大きくなって、もうこの胸には戻って来なくなるだろう。
私は、母親であることにあぐらを組んでいるのはもうやめて、
それこそ時間にも、世間体にも、常識にも、約束にも、
何ににもとらわれない母親の愛情を
離れて行くこの子たちに餞別として渡してやろうじゃないの。
これから大人になる途中でいくつもの試練がやってきても、
乗り越えられるだけの心の力を、生きていく自信を、
彼らに持ってもらいたいから。
「さ、みんな、そろそろお風呂入りな!」
私がそう言うと、みんな数ヶ月ぶりに
「は〜い」といういいお返事をして、仲良く風呂に入った。
愛されていることを実感できると、
人はなぜこんなにも「いい人」になれるのだろう。
愛されているのに、それを実感できないと、
人はなぜこんなにも「悲しい暴れん坊」になってしまうのか。
これは今、子供と私との問題だけではなく、
私自身の永遠のテーマでもあるのだ。
(了)
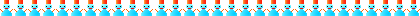
「転換育児」
(子だくさん)2002.12.3. 作あかじそ