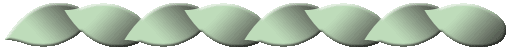
あゆさん No.22700 キリ番特典 お題【キャンプ】
小さなお話 「依存症治療キャンプ」
私は、世にはびこる依存症の連中に言いたい。
「みんな、自分のことは自分でしろ」と。
私と夫は、一人っ子同士の結婚だ。
両家とも、結婚を喜んでくれたのに、
相手が一人っ子と聞くなり、猛反対だった。
「お前は、私たち夫婦の人生そのものだ」
「手塩に掛けて育てたひとつぶだね」
「死ぬまで私たちと一緒に暮らすのが当然」
お互いの親がそう思っているものだから、
当然互いの利益は折り合わない。
「嫁に来い」
「婿に来てくれ」
みんな、自分のことしか考えていなかった。
私たちは、双方の両親の世話を約束して、やっと結婚を許された。
そんな風にしてやっと勝ち取った結婚生活なのに、
子供が生まれたら、私たちの結婚はガラリと変わってしまった。
夫は、仕事が忙しくて帰ってこない。
家のことも子供の世話も、何もしない。
両家の親たちは、いちいち私たちの家庭に口を出し、
何をやってもやらなくても、誰も誉めてはくれないし、
みんなで口々に文句ばかりを言っている。
私の母は、毎日部屋に上がりこんで子供を私の手から奪い取り、
子供を舐めるように扱っているし、
私の父は、私が毎日頑張っていることも知らないで、
時々来ては、えらそうに怒鳴りつけていく。
夫の母は、夫の子供時代がどんなに可愛かったか、と繰り返し、
私と結婚したことでそれが台無しだとニコニコ笑いながらいつも言う。
夫の父は、
「我が家の嫁だということを忘れるな」
と、会うたびに念を押していく。
一体、なんなのよ、あんたたちは!
子の幸せを祈るのが親なんじゃないの?
私は、親たちの人形じゃない。
私は、親たちの専属ヘルパーじゃない。
私は、夫に実質見捨てられ、幼い子供を抱えて、
親たちの人生をひとりで背負って生きていかなければならないのか。
部屋いっぱいに詰め込まれた、親たちから孫へのおもちゃの山の隙間で、
私は毎日暗澹たる気持ちで暮していた。
そんなとき、郵便受けに入っていたあるダイレクトメールを見て、
私は膝を打った。
「これだ! 親たちを更正させよう!」
依存症気質を改善するキャンプがあり、
このダイレクトメールは、その参加者を募ったものだった。
このキャンプに、あの、べたべたに甘えきった親たちをぶち込んで、
徹底的に根性を叩きなおしてきてもらおう。
私はすぐに両家の親4人分の参加を申し込み、
こつこつ貯めていた貯金のほとんどを払い込んだ。
将来のために貯めていたが、
よぼよぼの親たち全員に寄りかかられることを考えたら、
ここに投資することが一番自分たちの将来のためだ、
と信じての冒険だった。
「日頃の感謝の気持ちを込めて、旅行のプレゼントです」
そう言って両家の親をおびき出し、
とある人里離れた合宿所に連れてきた。
親たちは、嬉しそうにその宿にぞろぞろと入っていき、
それから一週間、そこから出てこなかった。
私は、家に帰って、久々に伸び伸びとした気持ちで暮した。
今度会うとき、彼らは、どうなっているのだろう?
第一声、
「これからは私たちのことは気にせず、自分たちの人生を歩みなさい」
とでも言うのだろうか。
楽しみだ。
ところが―――。
2週間たっても3週間たっても、一向に彼らは戻って来なかった。
たしか合宿の期間は1週間だったはずだ。
さすがに私もあせってきた。
なにか良からぬ団体に入会させてしまったのではないか。
監禁されて、ヒドイ目に遭っているのではないか?
一方、私の生活にも思わぬ支障が出てきた。
今まで気付かなかったが、
母が昼間部屋に来て作ってくれていた夕飯のおかずを、
今度は全部自分が作らなければならない。
しかも、ギャンギャン泣き喚く乳幼児をあやしながらだ。
何もかも中断中断で、
掃除、洗濯、炊事、と、どれもまともにマットウできなかった。
夫や姑の愚痴をこぼす相手もいない。
誰とも何日も口を利かず、笑顔も出なくなった。
いらいらして子供に辛く当たっても、誰も叱ってはくれない。
いちいち口うるさい父がいないと、
私は、何もできない無力な人間だった。
夫の両親から月々送られてくる大量の米や食材も断たれ、
実際、家計は立ち行かなくなってきた。
―――そして、半年が過ぎてしまった。
合宿所に行っても、決して親たちとは面会させてもらえなかった。
重症だから、もうしばらくかかる、と言われて、
いつも追い返されてしまった。
衣替えをしたら、去年の服は、子供にはどれも小さくなっていた。
私は、子供服を買いに店に行ったが、財布の中を覗いては、
ため息をつきながら帰ってきてしまった。
高すぎて買えなかったのだ。
今まで、子供の服は、すべてイヤと言うほど両家から送られて来た。
下着から、靴下まで、何もかも揃えてくれていた。
両家とも、多少の蓄えはあるとしても、年金暮らしだ。
くれる服はどれも名のあるブランド物で、
こういうものを買って孫に着せるのが趣味なんだろう、
と、バカにしていた。
むしろ、趣味を押し付けられて迷惑していたのだ。
お金がなかった。
私は、託児所に子供を預けて、パートに出た。
近所に託児所がなかったので、ペーパードライバーを返上して、
車で送り迎えし、運転も上達してきた。
今までは、近所に住む父がいちいち車を出して、
どこへでも連れて行ってくれていたのだ。
その都度、文句ばかり言うので、私は逆ギレして、
送ってもらいながら父に怒鳴りつけたりしていたのだ。
姑から時々送られてくる現金入りの封筒も、
もう来ることはなかった。
「今回は2万」
「おっとラッキー、今日は5万」
と、私は感謝の気持ちを一切持たず、
姑が病気をおして働いて、稼いだお金を気楽に使っていた。
今、食べるものを買うのにも困るようになって、
その2万5万が、どれだけ私たちを助けていてくれたのかを
初めて知った。
キャンプは終わらなかった。
午後6時過ぎ、パートが終わり、駐車場にとぼとぼと歩いて行くと、
ふと、見慣れた人が倉庫を出入りしているのを発見した。
夫だった。
いつもスーツで出勤し、会社では内勤のはずだが、
倉庫に荷物を何度も搬入している夫は、
くすんだクリーム色の作業服を着ていた。
背中には、聞き覚えのある運送会社の名前が書いてあった。
確か、夫の会社に出入りしているところだ。
さては、夫はリストラされて、黙って転職していたのか?
私は怒って夫の方に近づいていった。
―――と、
夫といっしょに働くもうひとりのおじさんに気がついた。
彼は、夫に向かって、
「いくら若くたって、仕事の掛け持ちはつらかろう!」
と言った。
夫は少し笑い、作業を続けた。
「ニョウボ子供が可愛いから頑張れるな」
と、おじさんが言うと、
「はい」
と夫は言い、特大の荷物を抱えて、倉庫の中に入っていった。
私は、夫に無視されていると思っていた。
実質、捨てられているのだと思っていた。
家に帰ってくるなり、疲れ果てて布団にもぐって眠ってしまう夫を、
泣き喚く子供を抱えて蹴り付けたこともあった。
甘えていたのは、誰でもない。
私自身だった。
依存していたのは、私だ。
周りの人すべてに依存して、
自分のために何かしてもらうのが当然だと思っていた。
少しでも不都合が生じると、まわりの人間のせいにして、
泣き喚き、自分の思うとおりにしようと暴れていた。
依存症治療キャンプに入らなければならないのは、私の方だ。
私は、泣きながら車を走らせ、託児所で子供を受け取って、
無意識に実家に来てしまった。
泣く私にきょとんとする子供。
その子供が、窓を見上げて急に大きな声を上げた。
「バアバだ!」
2階の雨戸が少し開いていて、中から灯りがもれていた。
思わず家に駆け寄り、玄関チャイムを激しく鳴らすと、
ゆっくりと母親が出てきた。
「帰ってきたわよ。ありがとう」
母は、そう言って、私を中に招き入れる仕草をした。
私は、とっさに入ろうとしたが、
「ううん、これから夕飯作るから、今日は帰る」
と言って、車に引き返した。
母は、
「そう?」
と言って、別段引きとめもせず、走り去る私の車を軽く見送って、
そして、あっさり家の中に入っていった。
みんな帰ってきた。
誰に寄りかかるわけでもなく、自分の足で立ち、
自分の体重を自分で支える人になって帰ってきた。
よろけた時は、近くの人が、サッと支える。
でも、またすぐしっかり立って、自分の足で歩く。
親たちだけでなく、私が一番変わったのかもしれない。
ところで、あのダイレクトメールをくれたキャンプの主催者に
感謝の手紙を書こうと連絡先を調べたが、
そこはなぜか架空の住所だった。
さては、親たちにハメられたのは私の方だったか。
この前、キャンプに支払った代金と同額の金額が、
通帳に振り込まれていた。
支払者名は、【自立キヤンプ】となっていた。
父はいつも小さい「ゃ」を大きく「や」と書いてしまう。
また父は間違えてしまったのだろう。
(了)
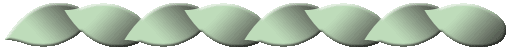
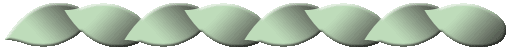
2003.2.18.(小さなお話)作あかじそ