フラメンコ歌手のまぬえらさんと出会ったのは、
2000年の政府主催のイベント「インターネット博覧会」会場だった。
私は、hanaとやっている
「読んでさっぱりあかじそドリンク」という読み物サイトで
このイベントに参加していて、
大オフ会的イベントの会場にブースを構えていた。
夫とふたりで地味にあかじそドリンク小冊子を並べて
静かに座っていると、なぜか急に空気が華やいだ。
大勢の取り巻きを引き連れ、
体に巻きつけた長い布をボワ〜ッとなびかせながら
颯爽と現れた女性がいた。
それが「まぬさん」こと、まぬえらさんだった。
「これからステージでフラメンコを歌うので
是非聴きに来てくださいね」
と言われて、音楽好きの私たち夫婦は楽しみにしていた。
が、いっとき、
うちのブースに何だか大勢のお客さんがどっとやってきて、
いろいろと応対しているうちに
もうステージの歌が終わってしまったという。
聴くのを楽しみにしていただけに、ふたりでがっかりしていたら、
後日、まぬさんからメールが届き、
インパク(インターネット博覧会の略称)の
仲間とのメール交流会に誘ってきてくれた。
それ以来、数年間、私たちのこの小さなサイトに通って
ありがたい感想を寄せてくれているのだ。
今度、まぬさんが教えているフラメンコ関係の
教室の発表会が催されるということで、
私は何を置いても駆けつけて、
あの時聴けなかったまぬさんの歌を聴きたいと思っていた。
小さな子供四人を預けて、平日の夜、
この片田舎から都心に出掛けるのは大変だったが、
父は子守をしながら子供たちに夕飯を食べさせてくれ、
夫は仕事を早く切り上げて子供たちを寝かしつけてくれていた。
うちの家族は、いつもみんな自分勝手に暮らしているくせに、
いざ芸術がらみのこととなると物凄く理解があるのだった。
芸術至上主義家庭であった。
これ幸いと私はひとりで家を出て、
近所の花屋で花束を買ってバスに乗り込んだ。
バスに乗って、私鉄に乗って、地下鉄を乗り継いで、
六本木だの恵比寿だのとなってきたとき、
私は電車の中でだんだん肩身が狭くなってきた。
都心に近づくにつれ、だんだん外人が増え、
乗客は目に見えてみんな垢抜けてきている。
家を出たときにはシュッとした格好だったはずの私の服装は、
ふと見ると、物凄くイナカッペ臭かった。
いつも大勢ぞろぞろとオスガキを連れて
小突き小突きしながら歩いていたここ十数年、
私はすっかりファッションとは縁遠い
おばはんになってしまっていたようだ。
自分の服を買うお金があったら、
子供に新しい靴下や下着を買ってあげたいと思って、
実際そうしてきたが、
私は無自覚のまま、
物凄く小汚い田舎のおばちゃんに
成り下がっていたようだった。
遠路はるばる花束を持ち歩いていたせいか、
買ったときにはシャンとしていた花束も、
何だか私の気持ちと一緒にしんなりとしてきている。
思えば、小さい頃から絵を描いたり歌を歌ったり、
オルガンを弾いたり、
ブラスバンドでトランペットやホルンを吹いたり、
演劇部で芝居をしたり、
大学のゼミで小説を書いたりして、
物心ついてからずっと表現活動を続けてきたが、
日々の家事育児ですっかり磨耗してしまった私がいる。
叫びたいこと、歌いたいこと、描きたいこと、
そういうことが山盛りに溜まり過ぎて、
濃縮されて沈殿し、
心の底の方にこびりついて
固まってしまっているのかもしれない。
歌の魂だけが私の胸の中に熱く煮立っていて、
もう今すぐにでも歌いだしたいテンションだった。
ああ、早く誰か歌って欲しい。
歌う技術を持たない私の、
この魂を外に出してやって欲しい。
たのむ、まぬさん、たのむよ。
会場に早く到着しすぎてしまったので、
近くにあった某コーヒーショップに入った。
そこは一時期話題になった、細かい注文をするところだった。
基本のコーヒーはこれで、
ミルクはこういう状態のものをこれくらい入れて、
砂糖はこんな感じで、
そのブレンドの割合はこんな感じで・・・・・、
みたいな注文をいちいちしなければならない店だった。
以前テレビで、
そのシステムがチンプンカンプンのおじさんが
コーヒーの注文をするための特訓をする番組があり、
私はゲラゲラ笑いながら見ていたが、
実際自分がメニューの前に立ったとき、
オジケついてどうしていいかわからなかった。
まるっきりイナカッペだった。
後から来た人たちに先に注文してもらい、
私は考えに考えた後、
「本日のコーヒー、ショートで」
と、いかにも余裕たっぷりという顔で注文してみた。
本日がどんなコーヒーかなんてどうでも良かった。
何でもいいから一杯のコーヒーを
恥をかかずに飲みたいだけだった。
フタがついたコーヒーの紙カップが出てきた。
ミルクも砂糖もくれなかった。
たぶん、言えばくれるのだろうが、今さら言えない。
何か余計なことを言って、
難しい質問でもされたら
すぐにイナカッペを見破られてしまう。
ミルクも砂糖もたっぷり入れないと飲めないのに、
私は「オッケー。サンキュー」みたいな顔をして受け取った。
席についてフタを取り、さっそうと一口飲んでみた。
ニガッ!
やっぱりブラックだった。
向かいの席に座っている同年代の洒落たご婦人が
私の方を見て、少し「ええっ?」という顔をした。
彼女はコーヒーのフタを取らずに飲んでいた。
フタをよく見ると、小さな穴が開いていて、
その穴からコーヒーを飲むようにできていた。
私は「そんなん知ってるし」という顔をし、
必要以上にフーフーやって、
自分は猫舌だということをアピールしてみた。
猫舌だから冷ますためにフタを開けたのだと。
しかし実際私は、馬鹿みたいに熱いものを
平気でゴーゴー飲み食いできるワイルド・タンの持ち主なのだ。
イナカッペ全開なのだ。
とりあえず一段落し、
熱々の苦いコーヒーをがぶ飲みしていると
(嗚呼、もうこの時点でイナカッペ)、
後ろの席からネイティブイングリッシュが聞こえてきた。
窓ガラスに映った外国人の女性が見えた。
彼女は、若い女性と向かい合って、何やらしゃべっていた。
”What do you do?”
「はいっ?」
”What do you do?”
「ええっと・・・・・・なんだろ」
”What! do! you! do?!”
「え、ナンだろナンだろ」
・・・・・・英語の個人レッスンらしい。
その後、外国人女性は何十回も
”What do you do?”と繰り返した。
「全然わかんなーい」
日本人の娘はへらへら笑っている。
わかるだろ、それくらい!
ヒアリング能力ゼロの私でさえも聞き取れるぞ。
”ファッッッッッッッッッ、デュ〜〜〜〜〜ユ〜〜〜〜〜〜デュ〜〜〜”
外国人もかなりしつこかった。
よっぽどその日本人娘が何やってんだか知りたいらしい。
いや、むしろ
「何やってんだテメー。今まで何勉強してきたんだよっ」
という意味合いの
”What do you do?”
だったのかもしれない。
ともかく、私はそのコーヒーを飲み終わるまでの十数分間、
ずっと”What do you do?”を聞いていた。
ホントに私は一体何をやっているのだ?
そろそろ開場の時間となったので
ホールの入り口に行くと、
出演者の家族や友人らしき人たちが大勢並んでいた。
私はひとり、何だか浮いていたが、
まぬさんに会えるのが楽しみでわくわくしていた。
当日券を二千円札で買った。
ちょっとした自意識であった。
「何だよ、今頃二千円札って」
とまぬさんの目に付いてくれたら
「それは私が出したのさ、ひひひ」
と言えると思ったのだ。
小さなホールだったが、満員だった。
私は一番後ろの真ん中の席で
物凄く前のめりで舞台を見つめていた。
やがて会場が暗くなり、
まぬさんの亡くなった師匠の歌と映像が流れてきた。
そして、まぬさんが舞台に現れ、
アカペラで歌い始めた。
思ったとおりの歌声だった。
私の胸の中にビーンと響き、
通る高い声は会場を圧倒し、
小さな声も太く通っていた。
歌に芯が入っていて、スペイン語のわからない私にも
大体どんなことを歌っているのか
なぜかわかってしまうのだった。
魂が入った歌というものは、こういうものなんだろう。
ここまで来て、本当に良かった。
生徒さんたちは緊張しまくっているのがわかったが、
半年であんなに歌えるようになるなんて大したものだ。
聴いていて、私は体や喉元が
うずうずしてきて仕方なかった。
私も歌いたい!
歌いたいことがいっぱいある!
途中何度かあった「リズムデモンストレーション」では、
数人が手拍子の掛け合いをしていた。
あれは聞いていて気持ちのいいものだ。
そういえば、あれに似たことを私は学生時代よくやっていた。
ブラスバンドの部室で
「ひとりウエストサイドストーリー芸」
などと言って、
手拍子と足拍子で
ンタタ、ンタタ、ンタ、ンタ、ンタ、と、
「アメリカ」という曲のリズムをすばやく打ちながら
歌い、踊り、部員たちの喝采を浴びていたものだ。
当時私は、単なる「一発芸」としてやっていたのだが、
私の芸の根底にフラメンコのノリが流れていたとは・・・・・・。
ワオッ。
さて、次にフラメンコを聴いて驚いたのは、
ギターの色っぽさだった。
若いお兄さんがふたり、ギターを弾いていたのだが、
至近距離の歌い手の顔を
穴の開くほど凝視しながら
手元は激しくギターを掻き鳴らしているのだ。
あれ、たまらんなっ!
若い男の子が私の顔を切なそうにじっと見つめながら、
甘く切なく、荒々しくギターを弾きまくった日にゃあ、
わたしゃ溶けるわ。
惚れる。チューしちゃう。
何なの、あの感じは!
たまらんのうっ!
私は、すっかりギターに魅了されてしまった。
ひとり静かにかなり取り乱した。
最後にまぬさんが歌い、
そして、生徒さんたちが全員で歌ったり踊ったり、
もう、物凄く楽しそうだった。
緊張していた人たちが全員、
突き抜けたような笑顔になり、
感情が開放されていた。
会場の踊れる人たちは立ち上がって
一緒になって踊っていた。
踊れない自分がもどかしかった。
それにしても、フラメンコの「間」というのは
なんて独特で気持ちのいいものなんだろう。
合いの手ひとつとっても沁みる。
もちろん、歌や踊りやギターも沁みるのだが、
何より「間」自体がパンパン自分に食い込んでくるのだ。
願わくば、暗い穴ぐらのような場所で
強い酒を浴びるように飲みながら、
恋人と抱き合って聴きたいものだ。
ヤバイくらい濃い世界だった。
昔、母と、銀座の「銀巴里」という店に
シャンソンをよく聴きに行ったが、
そんな風にフラメンコを聴きに通いたいと思った。
片田舎の一主婦が
ガバと前掛けを剥ぎ取り、
世界の中心になって炎を発することができるような世界、
それがフラメンコ―――
・・・・・・と思ったんだけど・・・・・・
違ってたらごめんね、まぬさん。
【追記】
深夜、地下鉄から私鉄に乗り換え、
だんだんと家に近づいてくると、
車内にはローカルな香りが漂いはじめ、
私のドン臭い服装は周囲に溶け込んでいった。
最寄駅に着くと、終バスはとうに出た後だった。
タクシーに乗り込むと、
客が女で、行き先が近い場所だったせいか、
運転手は返事もせず、ことばも荒く、
当てつけに客席に冷房を入れてきた。
いつもだったらへこんでしまう私だが、
今夜は大丈夫だった。
私に灯ったフラメンコの炎の種火は、
そんな陳腐なクサクサなど
一瞬でジュッと焼き消してしまうのだ。
しばらくはこの調子で生きられそうだ。
ありがと、まぬさん!
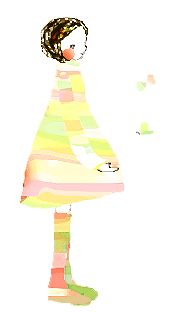 (了) (了)
|