| 「電車を待って」 |
第二子妊娠中、長男はまだ1歳だった。 当時長男は、異常なまでに人見知りで、神経質な子だった。 公園に連れて行っても、他に誰かいると、顔を両手で覆って 固まってしまった。 その頃住んでいた団地には、同じ年頃の子供が大勢いたが、 毎朝10時半から11時半に、団地内の公園で集合して遊ばないと、 親子共々仲間とは認められない、というシステムが 出来上がっていたようだった。 長男は早起きで、その時間帯は、いつも昼寝をしていたため、 私たち親子は、すっかり団地のコミュニティーから外れてしまった。 外に出れば、 「あのアウトサイダーが来た」 という目でチラリと見られて、挨拶も返してもらえなくなっていた。 私は、第二子妊娠当初からつわりがひどく、 ついには妊娠悪阻となって、連日点滴しながらやっと暮らしていた。 しかし長男は、一日中床に伏せっている私の側で、 だっこしろだの外に行こうだのとぐずりまくる。 真っ青な顔をして髪振り乱して公園へ行けば、 「あいつらが来た」と他の親子連れは皆、わざとらしく撤退してしまい、 居残ったとしても、カチカチに固まった長男と、 地べたにしゃがみこんでいるへろへろな母親を見ては、 こそこそと何かを囁いていた。 その頃、私の頭の中を渦巻いていたことばは、 「公園デビュー」だった。 育児雑誌は、どうやったら公園での人間関係がうまくいくかを、 何度となく取り上げていた。 「ヨットパーカーとジーパン、これが公園へ行くときの制服です」とか、 「目立っても沈んでも不可。普通の範囲内で自分と子供のキャラを売れ」 などという「読者からのコツ」がたくさん載っていて、うんざりしながらも、 内心、私は必死だった。 明らかに浮いてしまった私たち親子は、 もうすでに「デビュー」に失敗してしまっていた。 完全に仲間ハズレだった。 ある朝、私は、決死の覚悟で長男を昼寝からたたき起こし、 午前10時半に公園に向かった。 早く公園に着いて、一番で遊んでいれば、 長男も固まらないで友だちと遊べるかもしれない。 長男は、誰もいない砂場にしゃがみこみ、 昨日誰かが作ったらしい砂の城をそっと触った。 すると、ざざっ、とそれはあっという間に崩れ、ただの砂山となった。 「あっ! あーあっ!」 私たちの背後から、子供の高い声が聞こえ、 振り向くと、数組の親子が、私たち親子を睨みつけていた。 「昨日の夕方、みんなで頑張って作ったのにね!」 ある母親が聞こえよがしに大声で子供たちに言った。 「みんなで力を合わせて、一生懸命に作ったのにねっ!」 また違う母親が言った。 私は、自分の目玉が、どんどん充血していくのを感じた。 氷を飲み込んだように冷たい塊が胸に詰まった。 長男を見ると、真っ青な顔で表情もなく、ただ目を見開いていた。 そして、1歳の小さな小さな長男は、 複数の親子の罵声を浴びながら、まったく動かなくなった。 その時、私の胸は、パチン、と鳴った。 私は、長男を抱き上げると、大勢の親子に向き直った。 その時私は、みっともないくらいめちゃくちゃな顔をしていただろう。 子供を抱いたまま、砂場にずかずか入っていき、 砂の山を思い切り蹴飛ばし、唖然とする何組もの親子の間に 無理矢理割って入って、その壁の向こうに突き抜けていった。 もう、二度とヤツラとつるもうとは思うまい。 公園デビューなんて、もうしない。 長男をベビーカーに乗せて、私は毎日歩いた。 好きな時間に、好きなところを。 昨日は、隣町のスーパーに卵を1パック買いに。 今日は、鳩にえさをやりに、遠い広場まで。 そして毎日決まって同じ道を通るのだ。 高架と並行している陸橋を。 何分かに1度、電車がそこを勢いよく通過し、 運がよければ、カッコイイ特急も見られる。 ベビーカーを線路の方に向け、 大きなお腹を抱えて長男の横にしゃがみこみ、 「今度は何色の電車かな〜?」 と子供の頬にキスしながら、電車を待った。 「バイバ―イ」 と、数台の電車に手を振ってから、 「そろそろ行く?」 と長男に聞くと、 「いこーう!」 と、頬を紅潮させて、グーを天高く振り上げる。 目が光っている。 私は、ベビーカーを押しながら、懐かしい小学校唱歌をいくつもいくつも 歌った。 「名も知らぬ 遠き島より 流れ寄る椰子の実ひとつ・・・・・・」 長男もすっかり覚えてしまい、 「ふーるちゃーとーのーきーちーを、はーなれてー」 と、歌う。 「なれーはそーもー、なーみーにー、いくーちゅーきー」 声を合わせて歌えば、妊婦の胸苦しさも吹き飛んだ。 仕事で忙しい夫には、あの頃の私たちの悲鳴はついに届かなかった。 しかし、私と長男は、ひとつのものを捨て、 もうひとつのものを選ぶことで、目に光を取り戻した。 もう、震えながら嫌なところへは行かない。 高い陸橋の上で、たったふたり、 電車の起こす突風に前髪をかき乱されながら、手を振るんだ。 笑いながら。キスしながら。 今年、長男は、10歳になった。 私が引き止めようとしても無理だ。 毎日、学校から帰るとランドセルを玄関に放り出して 友だちのところへ飛んでいってしまう。 外国のエライ人が、 「世の中で必要なことは、みんな砂場で学ぶ」 というようなことを言ったが、うちのは、電車を待ってそれを学んだ。 私もだ。 |
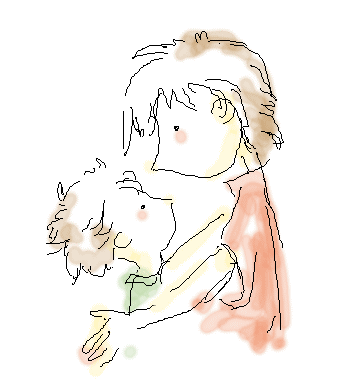 |
(子だくさん) 2002.09.12 作 あかじそ |