|
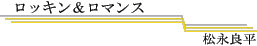
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
僕にとってロックするということはロマンス(妄想)するということと同じです。なおかつロッキン&ロマンス(Rockinユ
& Romance)は、頭文字がロックンロールと一緒です。
4年ほど前にフリーペイパーでやっていた「ロッキン&ロマンス」。この度、ハイファイさんのホームページに間借りして復活させていただくことになりました。ふつつか者ですが、よろしくお願いいたします。(松永良平)
第1回
不機嫌なジョン・サイモン
ジョン・サイモンのライブをまたしても見損ねてしまった。
20数年振りに復活したハース・マルチネスと、ジョン・ホールとの、3人の「名うて」によるステージはきっと素晴らしいものだったに違いない。
この3月にハースはプロモーションのために来日し、都内のレコード・ストアでインストア・ライブを行った。そのときに、彼の復活アルバムを録音している最中の場面がビデオで流された。そこで、僕は動くジョン・サイモンを久しぶりに見た。彼はハースの復活アルバムのプロデューサーを務めていたのだ。
その映像は、ホスト役の長門さんが「今映ったのがジョン・サイモン」と注釈してくれなければ、一瞬気付かないほど印象に薄いものだった。それとも僕だけだっただろうか?
どうしてそういう風に感じたのか、そのわけは僕とジョン・サイモンとのファースト・コンタクトがあまりにも印象的なものだったからと言うに尽きる。
少し時期は前後しているかもしれないが、91年頃だったと思う。その頃付き合っていた彼女とジャニス・ジョプリンのドキュメンタリー映画『JANIS』を吉祥寺のバウス・シアターに観に行った。彼女は音楽の趣味は僕と割合近かったのだが、一度火が付くと誰も止められないくらい対象に突っ込んで行く傾向があった。よく考えてみれば、そういう傾向は程度の差はあれ誰にでも当てはまることなんだけど、とにかく、そのときの彼女の相手になったのがジャニスだった。彼女は多分、10回以上バウスに足を運んだはずだ。そして、僕も彼女にくっついて、10回は観なかったが何度かは映画を観た。
貴重なライブ映像と、インタビューやプライベート・フィルムで構成された本編の中で、亡くなる直前に彼女がハイスクールの同窓会に出席して、ひとりではしゃいでいるシーンはやっぱり忘れることが出来ない。そこは「キャンパスでもっとも醜い男(!)」などと、さんざん蔑まれ、彼女が生涯憎んでやまなかった場所だったのだ。 しかし、この映画での僕の個人的ハイライトは1968年、ジャニスを含むビッグ・ブラザー&ホールディング・カンパニーが、スタジオでガーシュインの「サマータイム」を録音しているシーン。ビッグ・ブラザー〜は、ジャニスという極端にセンシティブな女性を受け止め、世に出したという意味では功績は大きい。とは言え、画面に映っていたのは、観念的な戯れ言ばかりを繰り返し、音楽的センスに明らかに欠けるくせに芸術家気取りだけは一人前の単なるローカル・グループだった。そして、その場面、そこには、そんな世間知らずの尊大な若者たちに対して、スタジオのガラスの向こうから苦虫を噛みつぶしたような顔で立ちつくし、不機嫌を表明している一人の青年がいた。
それがジョン・サイモンだった。
レコーディング・データを紐解いてみると、「サマータイム」を録音しているのは1968年の4月と、ある。
当時、コロンビアのスタッフ・プロデューサーとして働いていた(それとも退社するかしないかの時期だったろうか?)ジョン・サイモン。ザ・バンドと共に傑作『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』を創り上げて行くのと、ほぼ時を同じくして、こんな幼稚で下手くそな若造どもの相手をしなけりゃならないなんて、という神経質で憂鬱な感情が、そこでははっきりと読みとれる。
もちろん、ジャニスに夢中の僕の彼女は彼をやり玉に挙げた。僕もつられて「ああいうやつがレコード業界を悪くするんだ」などと、神をも恐れぬことをいけしゃあしゃあと言っていた。
その男がワーナー・ブラザースに残した2枚のソロ・アルバムに僕が夢中になるには、もうちょっと時間が必要だったのだ。
97年の暮れに、サウンドトラック『ユー・アー・ホワット・ユー・イート』がめでたく日本のSONYからCD化された。マンフレッド・マンやムーンライダーズの演奏で知られる「マイ・ネーム・イズ・ジャック」のオリジナル・ジョン・サイモン・ヴァージョンを収録している、ということで知られていたものだ。PPMのピーター・ヤロウやタイニー・ティムら(個人的にはジョン・ヘラルドもかなりミソ)の紡ぎ出すサイケ・ヒッピー・ソングを、切った貼ったの大騒ぎ、DJ感覚で提示して見せたジョン・サイモンの実質的なソロ・プロジェクトと言い切ることが出来る。
僕は以前からこのレコードがすごく好きだった。すごく腕利きの職人による「やっつけ仕事」のようなもので、全体は粗くても、随所に凝ったディテールが突出して見える奇形の音楽になってしまっているのも面白かった。例えばヴァン・ダイク・パークスの緻密な『ソング・サイクル』よりも、それ以前のベートーベンの「第九」と「カム・トゥ・ザ・サンシャイン」のカップリング7インチで強く感じることの出来るような思いつきまかせの感覚にしびれていたのだ。全体の質感も、荒々しいくらいに乱雑で、かなり鬱屈している。60年代という時間の持つ前向きでピースフルで、どこかタガの緩んだ感覚とはちょっと異質の空気が流れていて、エディット・センスが今風というだけでなく、ヒリヒリした個人的で神経質なジョン・サイモン自身のイラつきが、すごく90年代的に思えるのだ。
|
しかし、サイモン自身は今ではこの作品に肯定的なコメントを残しているけれども、当時としては、とても売れる見込みがないようなこんな仕事に対して、プロデューサーとして自分なりのモチベーションを持つのが難しかったはずだ。そして、それはこの春、ついにCD化された67年の『メディアはマッサージ』(マーシャル・マクルーハンのスピーチをメチャクチャに切り刻み、編集の極致を尽くした問題作にしてジョン・サイモン関係の一番のレア盤)にしても同様だと思える。
|

|
今、この日本でこそマクルーハンとジョン・サイモンは同列(と言うか、マクルーハンが軽く負けてる)だが、30年前の時点で言えば「王子と乞食」。当時のメディア論における圧倒的な権威であったマクルーハンに挑むドン・キホーテのようなものだったと考えて間違いない。
しかし、ここで彼が取った態度は、かつてドン・キホーテがそうだったように、ロマンに溢れ、自由と挑戦の精神に満ちたものだった、と僕は思わない。全然、思わない。
むしろ、これは屈辱の配役だったのではなかろうか。「新進気鋭のプロデューサーとメディア論の大家の白熱の好勝負」なんかではあり得なかったはずだ。1967年、彼はまだザ・バンドのプロデューサーでも何でもない。サークルのレコードを作りながら、ジャズのチャールズ・ロイドやスティール・バンド、その他もろもろの雑事も手掛けなければならない、ただの会社員で便利屋だったに過ぎない。
僕が考えることの出来る唯一の結論は、ジョン・サイモンがここで「キレた」ということだ。「頭がキレる」の「キレる」もダブル・ミーニングさせておきたいけれど、それも含めて、やっぱり「ふざけんじゃあねーよ!」ってことだと思ってしまうのだ。そして、その結果『メディアはマッサージ』は、頭で考えすぎたところのない、胸ぐら掴んで襟元からシャツを引き裂くようにヒステリックで、なおかつ最高の手腕による、最高に気持の良いスクラップ&ビルドになっているのだ。
いつかこういうことをジョン・サイモン本人に訊いてみたいと思うのだけど、きっと笑ってごまかされるような気がする。それとも怒ってしまうのかな? だとしたら、何か逆に証明してもらったことになるかもしれない。
彼がザ・バンドを手掛けたあたりから上ってゆく「名プロデューサー、ジョン・サイモン」という階段。もちろん、それ以降の作品も素晴らしい。けれども、そこに至る前の60年代の2作品が日本で敢えてリリースされてしまう、ということには、音楽のセンスや作品のレア度云々よりも、人間ジョン・サイモンの抱えるメンタリティに日本の音楽ファンに共鳴する部分が何か少なからずあるんじゃないだろうか。少なくとも、僕はそう感じている。クールやビートやグッド・タイムでは割り切れない、音楽以前の人間臭い何かを。
70年代初頭の2枚のソロ・アルバム(サントラ『ラスト・サマー』も加えれば3枚)では、そこまで若気で過激なジョン・サイモン像はもう拝むことが出来ない。どのレコードも当時、売れはしなかったが、シンガーソングライター系の最重要名盤として日本では長く語り継がれてきたし、実際、それだけの名声に値するコクのようなものがある。90年代に入ってからは、ついにソロ活動を再開。現在までに3枚の充実したアルバムを作っている。自分のために自分の作品を思うままにつくることの出来る現在の彼のゆとりから、僕がかつてスクリーンで見た張り詰めた青年を思い浮かべるのは難しい。
|
しかし、ジョン・サイモンの最新アルバム『ホーム』(98年)で、30年前の「マイ・ネーム・イズ・ジャック」をよくリクエストされることに応えて、「あれは映画の中の登場人物の歌だから」と言い訳しながら、彼はこう歌った。
「His name was Jack.」
彼が過去と訣別したその一瞬、僕の前に、あの僕の知っていた痩せて神経質なジョン・サイモンが姿を現して、「バイ・バイ」と残像を残して消えて行った。
|

|
●
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
▲このページのTOP
▲Quarterly
Magazine Hi-Fi index Page
|

