|
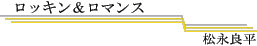
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
6
| 7
|
第6回「I
Had A Dream Last
Night.」
取材のため、青森行きの深夜バスに乗り込むと、早速、車内の電気は落とされた。隣の女の子が靴を脱ぎ、スリッパに履き替えている。
「あの娘、熟練さんだな」
同行しているSが小声で呟く。よく見ると、僕の足下にもちゃあんとスリッパが。こりゃいいね。むくんだ足から蒸気が出るような快感が這い上がってくる。北国の少女よ、旅の手ほどき、ありがとう。ついでに靴下も脱いでしまおう。
ほどなく、眠り地獄から伸びた手に引き吊り込まれ、僕の意識は薄曇った。まだ10時にもなってないというのに。
夢を見た。
22歳と20歳の兄弟二人雁首揃えて、いい年にもなって叱られていた。親父は続ける。
「まったく、お前ら、ヒッピーだかホッピーだかになるつもりか」
ヒッピーにもホッピーにもなる気はなかったけれど、二人揃って落第したのは本当だった。特に「初犯」の弟に対して、「再犯」の僕の方は分が悪い。二年連続だもんな。去年は、銀婚式直前の両親に留年爆弾だもんな。
しかし、僕は知っている。
親父もかつて、ジャズメンになりたかった、という時代があったことを。実家の奥に眠っている棚の開き戸の中に、東京にいた時分、20代前半に買い集めたサッチモやジャック・ティーガーデン、名も知れぬニューオリンズのデキシー・ジャズ・バンドの10インチや、当時バカ高かった筈のLPレコードが隠してあるのを。
その夢の塊を発見するまで、僕はてっきり親父のアイドルは石原裕次郎だと信じきっていた。社員旅行のバスで、「錆びたナイフ」を歌う姿に、子供心にけっこうヘキエキしていた。音楽に興味を持ち始めた頃、家の中を探しても出てくるのはジェリー藤尾や菅原洋一のシングル盤なんかで、ヒップな匂いのカケラもしてなかった。 でも、僕は発見した。そして、本人に訊くのはただでさえシャクだったし、ボンクラ息子の僕とはほぼ絶縁状態だったので、想像した。確か、親父の法政時代の友人に一度会ったときに、「クラブのバーテンか何かやってた」なんて話を聞いたことがある。僕はそのクラブのドアを思い切って開けた。夢の中だから、チャージはタダだった。
木を基調に作られたお店の中は二階建て。いい具合にコキタナイところが、逆に小洒落てる。一度行ったことのある中野北口の感じの良いバーがモデルになっていた。
カウンターを挟んで女店員とサラリーマンが会話。こないだ「五つの銅貨」観てきたンだよ、なんて、昭和30年代の映画で聞くようなアクセントと言葉遣い。サッチモがいいでしょう?と、奥から若いバーテンが会話に加わろうとする。蝶ネクタイか何か締めた痩せたその顔は、僕のひとつ年上の兄貴にソックリだった。実家で見た、親父の一番古い写真(多分、高校時代あたりの)で、それは確認してたから間違いない。32歳の僕は22歳(推定)の親父に軽く会釈。
お兄さん、ジャズ好きなンだね、とサラリーマン。この人、キチガイよ、と女店員。お給料全部レコードに使っちゃうの。ラーメン一杯50円の時代に、LPレコードは一枚千七百円位だった。じゃあ、お詳しいンでショ、と水を向けられると、親父はニヤっと笑って、照れて後ずさりしながら、どっかへ行ってしまった。
僕は親父を探した。僕も同じくらいの年で、高円寺の喫茶店でレコードをかけたり、お茶をいれたりしながら、ほとんどこれと同じようなことをしていた。自分ではそれなりに詳しい、って思ってても、詳しいだけ、ってのはイヤだった。音楽に自分が惹かれてるサムシング、それを上手く伝えられなくて、口ごもってしまってた。かえって、そんなのが「したり顔」だなんて思われて。そうじゃない、僕も楽器を弾いたり、歌ったり、文章を書いたりすることで、自分がどれだけ音楽が好きかを、ただそのまま伝えたいだけなんだ。そして、いつかはそれを自分の人生にしたい、と。アナタもそう思ってたんでしょ?
そんなに広い店じゃないはずなのに、かなり奥まで来てしまった。すると、そこにはどういうわけかステージがあった。
赤いビロードのカーテンに囲まれて、楽団がセットを始める。やがて、つかつかと奥からマイクに歩み寄るバンマスの姿。オールバックで決め、タキシードを着込んだ、恰幅の良い紳士の手にはトロンボーンが。
みなさま。それでは今宵の一曲目、「アラバマに陽は落ちて」。 ジャック・ティーガーデン! いや、40歳の頃の親父! ああ、あの頃の親父のスタイルは、それを真似てたんだ、って初めて気が付いた。と言うか、この場面、「バッファロー’66」で歌うヴィンセント・ギャロの親父のパクリだな。でも、僕はあの映画の中で、あそこが一番好きなんだ。そして、何故、あの場面がそんなに好きなのか、自分でもよく判った。
演奏が終わると、偽ジャック・ティーガーデンである親父は、荷物をたたみ始めた。買い集めたレコードも棚にしまいこみ始めた。いつの間にか、二十代の痩せたルックスに戻り、バー・カウンターで別れの挨拶をしていた。
今度、実家を継ぐことになりました。
親父は本当は長男では無く、実の兄が父親(つまり僕のじいさん)に反抗して家を出たため、急遽、家業を継ぐことになった、と知ったのは僕が「ホッピー」と言われた少し後だった。大学を卒業してから実家に戻るまで数年のタイムラグがあったのは、そのためだったのかもしれない。
つまり、次男で放蕩で稼いだ金はすべてレコードに使っていた、という若い頃の親父の姿は、すべて僕にも当てはまるのだった。親父の悪い趣味だと信じて疑わなかったジェリー藤尾や菅原洋一のシングル盤は、母親の持ち物だったし、裕次郎の歌を覚えたのも実家に戻ってから、会社のみんなに溶け込むためだった、という。
しかし、東京から持ち帰ったレコードは、自分の子供たちが一人前になり、親父が引退するときまで固く封印をされ、以降、少年だった僕たち兄弟に親父は音楽の手ほどきなんか一切してくれなかったのだった。
よりによって、その封印を開けたのが、僕だった・・・。
月明かりが揺れるカーテンから時々差し込む。
変な夢だった・・・。これじゃあ、オレって、親父が転げ落ちるはずだった人生を、今まさに落っこちて行ってるってこと? いずれにせよ、中途半端は否めないけどね。
ダメ人生の見本なのか、夢の先を生かされてるのか。冷房の効き過ぎた車内で、冷や汗を感じつつ、僕はまた眠りに落ちた。
バスは、そんな揺れる思惑なんかまるで関係なく、じゃんじゃんハイウェイを飛ばしていた。そのスピードは、まるで人生のようだった。
●
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
6
| 7
|
▲このページのTOP
▲Quarterly
Magazine Hi-Fi index Page
●
Home
| Shop on
Web | How
to Order | Shop
information | Quarterly
Magazine | Topics
| Links
| Mail
| 販売法に基づく表記
|

|