|
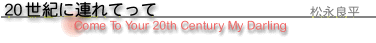
| 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8
|
ハイファイ大江田信のプロデュースで、リズム&ペンシル松永良平がお送りする新連載インタビュー企画 第2弾。
そのとき、その場所で、誰が何を感じ、音楽はどう鳴っていたのか? その感激を紐解く作業は、決してオールドタイム・ノスタルジーだけじゃない何かを、今ここで再び伝えられるはずだ。
20世紀の音楽の現場を、見て、生きて、感じてきた人たちとの、予習無しのリアルタイム・トーク。ゆくゆくは日本版「ポップ・ヴォイス」を目指しますか、大江田さん?
何はともあれ「20世紀のことも知らないで、21世紀を生きるなんて遅れてる〜!」のハッタリがモットー!
第2回 菅野ヘッケル
「音楽って商品じゃないからね」
ボブ・ディランの日本盤レコードを買ったことのある人なら、頭のどこかに「菅野ヘッケル」という奇妙な名前の人物が刷り込みされているハズだ。前回「ボブ・ディランとハワイ」なんて不謹慎な原稿を書いた僕も、御多聞に漏れず、よく知りもしないのに、お会いするまでは勝手にヘッケルさんを「ディランのご意見番」扱いして、「僕なんかが話訊いてもいいんですかねえ」と後込みしていた。
輪郭が大きくなりすぎて、とらえどころが無い。フォーク、シンガーソングライターの頂点的存在でありながら、等身大に音楽と人間性を考えることが禁じ手とされている。果たせるかな、今回のインタビューは、現在のディランを僕らが勝手に追いやっている、そんな窮屈なイメージの世界を捉え直すヒントを与えてくれている。ヘッケルさんはディランとの三十数年を、レコードのコレクションや、七面倒くさい理論武装なんか全然相手にしないで、「好きになってしまったものはしょうがない」で押し通している。恋心というヤツだ。人が人を好きになるのを見るのは、気持がいい。
ご存じの方も多いと思うが、実際にはヘッケルさんは、ディラン・フリークであることはもちろん、黎明期のCBSソニーの洋楽部門で痛快な存在感を持っていたA&Rマンでもあった。一見ぶっきらぼうかつ簡単な話で済ませたのは、御自分のことを話すのが照れくさかったからに違いない。かつて、レコード会社の社員が持っていたものは、厚い名刺の束なんかじゃ無く、音楽と添い遂げたい!っていう野心の塊だった、ということを想像させるに余りある態度に、僕は恐縮しつつも惚れ惚れとしてしまったことを告白しておきます。
ディランをやりたいがためにCBSソニーを受けた
松永:大学を卒業された1970年にソニー(CBSソニー)に入社されたということなんですけど。
菅野:うん。ソニーは68年に出来たのかな。
松永:やっぱりディランがソニーにいたからですか。
菅野:そう。大学のときに、就職のこと考えるわけじゃない? 堅い方向に進むべきか?とか。でも自分の一番好きなこと何だろう?って考えると、それはディランだったからね。63年、高校一年の秋にラジオでPPMで知ってた「風に吹かれて」のオリジナルを聴いて「何ちゅー声だ」と、すごく興味持って、それ以来、もうずっとだから。だから、僕のアタマの中では、最初に買ったレコードって、もうディランしかないわけ。それまでもいろいろ聴いたり、買ったりはしてたと思うんだが、とにかく常時音を聴いていたいがためにレコードを欲しい、と思わせるような存在なんて、ディランを聴くまでは居なかったんだ。
松永:面接のときも、やっぱりディランの話ですよね。
菅野:(笑)だって、何で受けたか、って言われたら「ディランやりたいから受けた」って言うしかないもんね。今の会長が面接官だったんだけど、若造が延々と「ディランやらせろ!」っていうことを言ったわけで(笑)。たまたま若い会社で、社員も少ないし、「ディランやりたい」なんて自分から言うヤツがいるんなら、ってことで採ってくれたんだよね。今では、とても(苦笑)。
松永:実際にディランを見に、アメリカに行かれたのは・・・。
菅野:74年の、8年振りのコンサート・ツアー。
松永:「偉大なる復活」ってヤツですね。すごい寒いシカゴの街で御覧になったそうですけど。
菅野:初日がシカゴだったんだけど、当時は、まだ情報がデタラメなんだ。最初に聞いてた場所が、結構シカゴの南の方にある、コワイ場所だったんですよ。初めてだから、早い時間に行くじゃない。でも、行ってみたら、全然そんな雰囲気がない。そこら辺にいた人に訊いてみたら、「それはシカゴ・スタジアムの間違いだ」って(笑)。慌てて、そっち向かってさ。
松永:日本からレコード会社の人がそういう場所に行くときって、チケットとかもらえたりするんじゃないんですか?・・・あ、当時はディランはワーナーだったんだ!
大江田:くやしくなかったですか? このままワーナーから戻ってこないんじゃないかって。まあ、2枚で戻ってきたわけですけど。
菅野:最初はもちろんそう思ったよ。ワーナーに僕も移ろうかと真剣に考えたりもしたし(笑)。そのとき、たまたまアメリカのコロンビアのオフィスに行ったら、日本からソニーの大賀さんが来ててさ。「お前何しに来てんだ」って訊かれて、「いや、ディランで」って言ったら、「アイツはヨソのアーティストだろ!」って(苦笑)。
だから、会社休んで行ったんだ。有給とか、いろんな手を使って一ヶ月休みを取って。行きゃあ何とかなると思って行った。そしたら、シカゴ・スタジアムに着いたら、運良くディランとザ・バンドの連中が楽屋入りする光景にぶつかって。それを目撃したときは、やっぱりすごい感激したね・・・。バスから降りてきて、ディランが歩いて楽屋に入って行くんだよ。こっちは茫然と見てるしかないんだけど(笑)。しばらくしたらサウンドチェックの音が中から少し漏れてきて。ドアに耳押しつけて聴いてたんだ。そのときが、マイナス20度で(笑)雪はほとんど降ってなかったんだけど、ものすごく寒いんだ。シカゴって「ウィンディ・シティ」って別名があるくらいだから、風がやっぱりすごいんだ。でも、こっちはすごい興奮してるからさ。若さもあったし。でもやっぱり顔が痛いんだよね(笑)、寒くて。でも、しばらくそこにいたんだよね。
松永:その一ヶ月間は、ほとんどディランに付いて回ったわけですか?
菅野:シカゴは2日間。そのあと、ボストン、フィラデルフィア、ニューヨーク。ずっと見てた。当時は昼夜やってたりするんだよね。まだそういう時代だったんだよ。今では考えられないでしょ。昼2時間やって、また夜は夜で2時間くらいやって。ロサンゼルスは日本からも小倉エージ、矢吹申彦、(吉田)拓郎とか、見にきてたみたいだけど。何回も追いかけて日本から行くっていうのは、当時はまだ少なかったと思うけどね。
あのときは(河村)要助に訊いて、安いホテルを教えてもらったんだよね。まだ1ドルは360円だし、いわゆる貧乏旅行だよ。それで、ニューヨークで泊まったホテルは1週間で40何ドルとかね。でも、シャワー付いてた。しかも、そのホテルはね、ホテル・アルバートっていって。ワシントン・スクエアのそばにあって。あのアーチのところから50メートルくらいのところにあって。それは、当時の貧乏ミュージシャンたちが定宿にしてたところで。ディランも泊まったことがあるというし、フロントの壁にはティム・バックリィの写真が飾ってあったり、由緒ある貧乏宿なんだよ(笑)今はもうホテルじゃなくって、アパートになっちゃってるんだけど。あと、当時、ポール・ウィリアムス(※注/同姓同名の音楽評論家の方)がニューヨークに住んでたからね。よく遊びに行ったりしてたんだけど。
大江田:金延(幸子)さんと一緒になられた方ですよね。
松永:ディランの「トーキング・ニューヨーク・ブルース」の気持で、ニューヨークを歩いたり。
菅野:それはあるよね(笑)、当然ながら。当時はまだ知らなかったけれど、ディランがニューヨークで住んでた家とかあるじゃない。
大江田:ミネアポリスにもディランがニューヨークに出る前に住んでたアパートがあって。ささやかな色街みたいなところのそばでしたけど。
菅野:ディラン・ファンは必ず行かなきゃいけないんだよ、そういうとこは(笑)。今年の夏、ウェスト4thストリートの方行ったときに、ディランが最初に居たアパートのとこで、「貸し部屋アリ」みたいな看板が出てて、「借りれるんだ」ってわけもなく思った(笑)。
ディランに会ったらよろしくと
松永:実際に初めてディランのライブを見てしまった後の感想って、どんなもんだったんですか。
菅野:ま、だいたい1曲目から判んないわけだよ。「ヒーロー・ブルース」だって、後から判ったけど、知らないじゃん(笑)。だから、最初から「ええーっ」と、もうドギマギするだけだよね。それほどメチャクチャアレンジを変えてるわけじゃないけれども、ほとんど馴染みのない曲が初っ端だったんだからさ。
松永:そういう意味では、時代によってどんどん変化してゆくディランに対してのとまどい、みたいなものはないのですか?
菅野:ない。だってねえ。僕にとってディランと言えば、何やったってOKって存在だし。否定する時期は無かったね。会社入って初めて僕が担当したレコードが『セルフ・ポートレート』だから。あれが70年の8月だからね。最初にジャケットが送られてきたとき、変な絵しか描いてなくって。中身も、それまでのファンとか評論家の人たちが「これは何だ!」ってケチョンケチョンにする人も出て来て。こっちは「これがディランだ」ってことで、言葉巧みに良さを説明しようとするじゃない。だから、その頃からすでに「どんなものでも、いい」という姿勢になってたね。特に、僕が入ってからCBSソニーで新譜で扱ったのって、『セルフ・ポートレイト』でしょ。それから『ニュー・モーニング』があって、『ディラン』さらに『ビリー・ザ・キッド』って続くわけだから。まともな、キチッとした格好のレコードってなかなか無かったんだ。だから売る側にしたら、なかなか辛いものもあるわけで(笑)。
松永:入社と同時に、ディランがハードルを次々に用意したような感じですね(笑)。
菅野:そうだねえ。当然あんまり売れもしないし。だからこそ、キャンペーンとか打って、旧譜をまとめて出したりして。
大江田:「ディランに会ったらよろしくと」って本も作ってましたよね。
菅野:73年かな。小冊子。僕の書き下ろしと、向こうの記事とか勝手に訳して、写真まで入れちゃって(笑)。当時は権利関係とかみんな無視だからね。そのときに『Mr.Dユsコレクション』って貴重な曲を集めた特典盤も作って。10枚買った人にはあげますよ、って。あれはかなり功を奏したね。
大江田:ディランを議論する基礎的な部分ってのがよやく出来てきたのも、この辺からですよね。今思うとね。手掛かりが出来た。片桐ユズルさんとかが詩の持つ意味を紹介し始めたり、日本のミュージシャンでも友部正人とか、中川五郎とかが出てきたり。
松永:初来日(78年)というのも、ポイントとしてあると思うんですけど。
菅野:そうだね。初めてだからね。生のディランと会うのが。
松永:『アット武道館』ってアルバムを作りたい、という動きもそれからだったんですか。
菅野:うん。どうせなら絶対作りたい、と思って交渉始めてもらって。最終的には、とりあえず日本発売のみで、ってことで制作のOKが出て。
松永:アルバート・グロスマンと交渉したわけですか?
菅野:いや、当時はもう違った。亡くなってた・・・?
大江田:いや、亡くなってはいないですけど、ベアズヴィルの方でもう仕事してて。
松永:映画「ドント・ルック・バック」見ると、ものすごく怖い、やり手のオッサンですよね。
菅野:アルバート・グロスマンって、すごくアーティスト思いなんだと思うよ。アーティストを守る、っていう姿勢がすごく強いから(ハタから見ると怖いこともする)。
大江田:やっぱりディランはそれにすごく感謝すべきだったと思います。
菅野:そうね。そういう意味では、まったく自由にさせてもらったわけだし。才能を信じてる人に関しては、本質的なところには一切口出しはしなかった。・・・周りに恵まれてるよ、ディランは。
あの『武道館』のツアーは日本が最初で、あそこからディランはまったくアレンジを変えたんだよね。ローリング・サンダー・レビューが76年に終わって、77年には何もしてないから。今思うと、離婚と映画(「レナルド&クララ」※注/「ローリング・サンダー航海日誌」サム・シェパード著を参照のこと。河出文庫で出てます)でお金使っちゃって、という状況があって、ワールド・ツアーやったんだろうけどね。
松永:ついにディランと接するわけですが。
菅野:最初は羽田空港。迎えに行って、ゲートから出てくるところで見たのかな。それは「見た」。「会った」んじゃなくって「見た」だけ(笑)で、羽田東急ホテルで記者会見を即やるんで、その記者会見の前に、直接本人に会ったんだ。握手をしてもらって。すごい・・・こりゃまた当然、感激。(笑)そこに居るんだもんね。
松永:何か言われたらどうしよう?とか。
菅野:そんな冷静なこと考えてないよ(笑)。多分、何か言ったんだと思うけど。「ずっとファンでした」とか(笑)。それが2月の18日かな。
大江田:ツアー中に、ライブが終わってからホテル行ったりとか、食事行ったりとかはしなかったんですか?
菅野:全然。帰る直前に、一回だけソニー主催でパーティーみたいなのを銀座のマキシムでやって。基本的には、そういう場所に出てくること自体がすごく珍しい。まあ、日本は初めてだし、スタッフもすごく親切にしてくれたから、お礼にってことだと思うんだけどね。関係者には当時のコンサート・ポスターを額に入れてサインして、みんなに配ってくれた。基本的にすごくいい人で、優しい人なんだよ。でも、すごく人見知りするって言うか、すごくシャイだから。
松永:人付き合いも下手・・。
菅野:下手って言うか、付き合わなくてもいい、と思ってるんだろうけどね。社交的になる必要ないわけだから。でも、何故か結構僕のこと気にいってくれてね・・・。ロスに『武道館』のテスト盤持って、最終OKもらいに行ったときも、まったく問題無かったし。
大江田:じゃあ、その後も結構お付き合いが。
菅野:いや、ほとんど無い。でも、85年に日本でビデオを撮影したんだよね。倍賞美津子やジュリーとかも出てるプロモーション・ビデオを。で、そのときに「会いたがってる」って連絡が入って、会いに行ったんだ。
松永:覚えててくれたんですね。
菅野:今でも「年に一回は会おうよ」って約束はしてるんだけども。
「何でもあり」を生き続けるディラン
松永:ディランの歳の取り方、ってどう思われます?
菅野:昔はね、すごい歳が違う人、みたいに思ってた。でも、考えてみると、僕とそんなに違うわけじゃないんだよね。6歳しか違わないからね。
まあ、ディランはあんまり歳を感じさせないよね。元気だし。特にここ10年間くらいは年100回コンサートみたいなのをやってるからね。ファンの間では「ネヴァー・エンディング・ツアー」って今は呼んでるんだけども。基本的にバック・ミュージシャンも若い子たちが多いし。88年に今のかたちのライブを始めたときは、ほとんどパンク・ロックぽかったし。
ディランは、ホントにステージが好きなんだよね。今回やってるポール・サイモンとのジョイント・ツアーでも、過密スケジュールの合間を縫って8月だけでも4、5回、千人前後の会場で単独ライブやってるわけ。それも40ドルくらいの入場料で。ポールとのライブは、スタジアムに1万とか2万人集めて、125ドルだからね。ライブが好きっていうか、ファンのために、って思いがあるんだよね。
松永:ディランにもデッドヘッズ(グレイトフルヘッズの熱烈な追っかけ集団)のような一団があるんですよね。
菅野:まあ、デッドヘッズとかなりダブるんだけど。87年にデッドと組んでツアーやったじゃない。そのときにフィラデルフィアでディランと会ったんだけど。デッドヘッズの連中って、Tシャツとかでも目立つじゃない。そうすると、ディランはね、ちょっと愚痴っぽい感じで(笑)「デッドヘッズばっかりじゃないか!」って。面白いよねえ。
松永:そういう嫉妬心みたいなのって、今でもあるんですね。
菅野:まあ、嫉妬心って言うかねえ。デッドがああいうファンを持ってることをうらやましくは思ってたんだろうけどね。「デッドのシャツとか着てても、ディランのときも集中して聴いててくれるし。みんなアナタのファンなんだから」って僕なんかは言うんだけど。でも、目に見えるそういうファンの姿や、彼らの一種独特の踊りとかにうらやましく思う部分があったんだと思う。そういうことでネヴァー・エンディング・ツアーもやることにしたんじゃないかな。で、今では、ディランにもそういう集団が出来てきたし。
今のツアーでは、下手したら半分くらい前日とセット・リストが替わるなんてこと平気でやってる。よくステージで打ち合わせして、次にやる曲決めてるし。ひどいときはバンドの連中が演奏始めたら、すぐ止めさせて。すぐ曲変える、とかね。そのバンドでは一回も練習してない曲を平気でやる、とかそういう感じだから。その場の雰囲気とかインスピレーションで、自分がどういう歌い方出来るか、とか、バックが何をやってくれるか、というものを引き出すことを求めてるわけだから。そのためにも絶対に曲は替えていかなきゃいけない、と思ってる。ファンもそれを期待するしね。人によってはね、レコードで聴いてるのと同じようにやんないからイヤだ、って人もいるみたいだけど(笑)。
大江田:やっぱりディランは、自分が昔見てたブルースマンみたいになりたい、って気持が今でもあるんでしょうね。
菅野:うん。それは絶対あるよね。すごい古い曲とかも結構大事にして、最近よく歌うんだよね。名も知らぬブルースマンの曲とか、ゴスペル・ナンバーとか、必ず1、2曲は歌う。と同時に、新しい歌もすごく気にしてて。
大江田:86年の来日公演で、リック・ネルソンの「ロンサム・タウン」歌って、すごくビックリしたんですけど。
菅野:あのね、ディランはね、多分、死んだ人に対する敬意がすごく強い人なんだよ。あれは、リックが死んでそんなに時期が経ってないころだったでしょ。それを思い出して、歌ったんだと思うよ。あのとき、あれもやったでしょ。「上を向いて歩こう」をインストで。あれも(坂本)九さんが亡くなったすぐ後くらいなんだよね。今デッドの曲、よくやるのもそれがあるんだよね。
松永:どんどんディランは「何でもあり」になってる、と。
菅野:そう。今年のニューヨークでは、シャルル・アズナブールの曲もやったし。その一週間くらい前に、シャルル・アズナブールが何かの記念でイベントみたいなのをニューヨークでやったんだよね。それを思い出して、歌ったんだ。だから、どんどんディランを見に出掛けないと。
大江田:多分、今の若い人には手掛かりが無いんだよね。ディランって、大きすぎて。「ボブ・ディラン全詩集」なんて、こんな厚い本が本屋にあったりしちゃって。レコードもいっぱいあって。そういう意味では、入り口を失ってる、って気がしますね。僕もそういうキライがなきにしもあらず。
菅野:例えば、僕の場合は、こないだの『タイム・アウト・オブ・マイ・マインド』ってアルバムでもね、「トライング・トゥ・ゲット・トゥ・ヘブン」って曲があって、ディランは自分が天国に行けるかどうか、天国の扉を叩いたら入れてくれるかどうか、とか考えてるんだ、とか思ったりするわけじゃない? 「ハイランド」の中では「ニール・ヤング聴いててボリューム上げると、いつも誰かが『うるさいから下げろ』って言う」とかいうフレーズとかあって。そういうちょっとした言葉がすごいおかしいじゃん。そういうので、ひっかかってくるんだ。
もちろん、文学的、英詩論的に解釈する人もいるだろうし。ノーベル賞候補にもなったりしてるわけだし。でも、聴き手がそれぞれ、ひっかかる言葉があれば、それで十分だと思うんだ。
松永:今、本当にボブ・ディラン入門に適したテキストって、生のライブなのかもしれないですね。名盤としてはいろいろあるのかもしれないけど、現在進行形で生きてるディランが、実は一番面白いんじゃないか、って気がしたんですけど。
菅野:そうだね。面白いね。「何でもあり」ってことには、逆に出来不出来もあるけどね。でも、ここ2年くらいはすっごくいいね。最近の傾向としてはリード・ギターをよく弾くし。今のバンドにはチャーリー・セクストンもいるんだけど。リードはほとんどディラン。
ストーンズも悪くないけど、もう完全にパッケージじゃない。大掛かりな仕掛けとか作って。ああいうの要らないと思うんだ。
松永:最近、僕、81年のストーンズのライブ『スティル・ライフ』がすごい好きで。あの下手くそで、じゃらじゃらした安っぽい感じがすごい良くって。そのときの反省で、89年以降のツアーはレコードに忠実なアレンジで、ってことになってるらしいんですけど。それって間違ってるなあ、って思うんですよね。
大江田:逆に、レコードに忠実ではない方が、実は身体にはこたえるのかもしれない。
菅野:まあね。スタジアムでやろうとしてる限り、そういうことになっちゃうんだろうけどね。
大江田:僕は若い頃のディランがすごい好きなのは、野心がある、と思うんですよ。いい意味でね。ジョニー・キャッシュの「アイ・ウォーク・ザ・ライン」じゃないけど、ミネソタって場所からニューヨークまで、自分がどうやって行くか、ってことを考えているディランがすごく好きで。行ってしまったら、それはそれで故郷のミネソタのことを思い返してるディランもいたりする、ってことがね。「ドント・ルック・バック」で、エレキ・ギターをじいーっと見てるディランが、割と僕の中ではひとつになったりするんだけど。
菅野:まあ、野心というのはあるよね。でも、あのギターは「いいなあ、欲しいなあ。高いなあ」とホントに思ってたんだろうけどね。
大江田:でも、実際に65年のニューポートで、ポール・バターフィールドたちとエレキ・ギター持ってステージに立ったら、すごいブーイングが起きた、とか何とか。
菅野:あれはね、いろいろ説があるけど。一番最近の説として信憑性高いのは、ひとつには「時間が短すぎる」と。みんなディランを目当てに来てるのに、ディランのステージはすごい短かった。エレクトリックでやれるのは3曲しか無かったしね。それだけでステージが終わっちゃった、とお客さんがみんな思っちゃって(ブーイングした)。それが最大の原因。もう一個の説は「ミキシングが悪くて、ディランの声が聞こえない」。初めてだからね、ああいうデカい野外でエレクトリック・バンドでやるってこと自体もね。
松永:確かに「フォークしか聴かないから、電気楽器なんかケシカラン」って過剰反応は変ではありますよね。話としては判りやすいかもしれないけど。
菅野:マスコミとかがね、「ああいう神聖なフォークの場所でロックをやったので非難された」って報道をやって、それが全世界に広まって。だから、その後、ザ・バンドと行ったイギリス公演では、みんなが「これはブーイングしなきゃいけない」って雰囲気を作っちゃった。純粋フォーク信仰者たちは「ディランがエレクトリックで出て来たら、ゆっくりした手拍子をしてブーイングをする」って打ち合わせまでしてたんだから。そういう話が、そのまま日本まで伝わってきて定説になっちゃったんだ。
大江田:ピート・シーガーの自伝の中にも、自分がそんな反応をしたっていうことが書いてありました。
菅野:そう。ピートはね、音があまりにも大きすぎるから、PAのケーブルを切ろうとしたんだ。
大江田:それをピーター・ヤロウ(PPM)が止めたんですよね。ピート・シーガーを非難するわけじゃないけど、「自分がどんな風にして自由になるか」を歌う人より、つまんない歌歌ってんだけど、その人はすごく自由に歌ってる、って歌の方がすごく力があるんじゃないか、って最近思ってるんですけどね。例えば、ジョニー・キャッシュみたいにね。
菅野:ジョニー・キャッシュは、ディランをデビューの頃から、すごい支持してた。同じコロンビアだったし。キャッシュはもうスターだったけど。手紙のやりとりとかしてて。ファースト・アルバムが5000枚しか売れなかったときも、重役連中に(契約を続けるよう)説得したりして。すごくディランを後押ししてたんだよね。そういういきさつもあって(『ナッシュビル・スカイライン』で)デュエットとかしたりしてるけどね。
何でヘッケルって言うんですか?
大江田:ところで、何でヘッケルって言うんですか?
菅野:これは、「ヘッケル&ジャンケル」ってアメリカのカラスの漫画があって、それが僕に似てるんだか似てないんだか知らないんだけどさ。ソニーに入った瞬間に、付けられちゃった。もう一人、菅野さんって人が居たのよ。その人はねえ、「ミスター・CBSソニー」って言われるくらいハンサムでねえ(笑)。で、「同じ名前じゃイカン」ってことで、そうなったと思うんだけど(笑)。
松永:70年代アタマには、CBSソニーのCはシカゴ、BはBST(ブラッド・スエット&ティアーズ)、Sはサンタナと言われてた時期がある、って聞いたことがあるんですけど。
菅野:そりゃあ、宣伝のために誰かがつくった文句だよね。CBSソニーは新しい会社だから新しいことをやろう、って、ニューロック・キャンペーンってのをやってたし。それにその3つは来日もしたしね。ニュー・フォーク・キャンペーンってのもやった。エリック・アンダーソンとかね。
大江田:その頃、「新譜ジャーナル」の島本さんのところにたまたま僕はいて、「これからヘッケルってのがプロモーションに来るから」って言って。それが僕とヘッケルさんの出会いなんですよ。もう26、7年前かな。
菅野:へえ。そうだったっけ。
大江田:その頃、もうヘッケルさんは有名だったんですよ。一番覚えてるのが、普通、プロモーターってレコード持ってきて、うんちゃぶんちゃセールス・ポイントを言うじゃないですか。でも、ヘッケルさんはレコード持ってきたら島本さんに渡して、島本さんが「何か言わないの?」ってヘッケルさんに訊いたら、「いいの」とか言ったきりで(笑)。「聴いて」ってひとこと。それをすごく思い出すんですよね。
菅野:まあ、自分で好きなヤツ以外はやりたくないからね。うん。好きでもないものを、人に「これがいいから」なんて説明出来ないから。
松永:今のレコード会社の人が聞いたら、ビックリしちゃいますよ(笑)。
大江田:でも、その頃は運がいいことに担当してたのがディランだったり、スプリングスティーンだったり、ブルース・コバーンだった、ってことですよね。
菅野:まあ、人数も少ないから、好きなのを獲れるわけよ。
大江田:スプリングスティーンのばかでかいポスター作ったり、ってこともありましたよね。
菅野:B倍ってヤツね。
松永:B全の倍ですか!
大江田:「会社の中でいかに壁を取るか、ってのが最初なんだよ」って僕によく言ってましたよね。
松永:ソニーにいる間は、もうディラン一色だと思ってました。
菅野:いや、もちろん他にも担当はしたよ。ディラン以外も一応聴いてますから(笑)。ピンク・フロイドとか、ボズ・スキャッグスとかポール・サイモンとか。スプリングスティーンもやったし。エリオット・マーフィーもやったな。
スプリングスティーンは最初のアルバム(『アズベリー・パークからの挨拶状』)が向こうで出たとき、すごく興奮した。当時は担当が違ってて、ソニーは出さなかったけどね。出さなきゃいかん。レコード会社の責任は大きいよ。まあ、売れないアルバムばっかり出してちゃヤバイけど。あの頃、ダン・ヒックス出したりとかね、パチェコ&アレキサンダー出したりとかね。そんなの誰が買うのか?って自分でも思ってたけどね(笑)。
松永:ダン・ヒックスのEPIC盤って、日本盤あるんですか!?
菅野:そう。出したんですよ、あの『オリジナル・レコーディングス』(笑)サンプル盤を600枚くらい作って、売れたのが400枚(笑)。ジャケットがねえ、確か表が渋かったから、裏ジャケのメンバー写真を表にしたんじゃなかったっけ?
大江田:ヘッケルさんに「レコード会社で仕事するって、どういうことなんですか?」って訊いたことがあって、そのとき、ヘッケルさんは「アーティストを尊敬することから始めるんだ」っておっしゃってたんですよね。
菅野:まあ・・・、音楽って商品じゃないからね。そういう考え方って、営業マンとしては失格だったかもしれないけどさ。
(9月7日 セヴンデイズ・オフィスにて収録)
菅野ヘッケル
ヘッケルさんは最初から業界の有名人だった。ディランに関して造詣が深いのは言うまでもなく、そのほか本文中でも触れられている数多くの素晴らしいアーチストを担当されていた。初めてお会いしたまだ学生の僕を会社に遊びに来るように誘ってくれ、仕事ぶりの一端を見せていただいたりした。ヘッケルさんを良く知る方たちは、一様に親愛の気持ちを込めた口振りでヘッケルさんのことを語る。ハイファイにみえたとあるディラン・ファンのお客様が、L.A.でコンサートの開演を待つ列の中でヘッケルさんと会い、会話を交わしたことをうれしそうに語ってくれたが、その気持ちが良く分かる。僕らにとって、ヘッケルさんと話をすることは、まるでディランと会話をする様なものなのだ。ヘッケルさんは、まるでディランなのである。
フィル・レッシュ&ヒズ・フレンズとボブ・ディラン&ヒズ・バンドのツアーが11月から始まること、Greatest
HitsのVolume1とVolume2が音も良くなって再発されたこと(ちなみにライナーはヘッケルさんです)という最新ニュースを教えてもらいました。
ヘッケルさんへのインタビューは僕の長年の夢でもありました。どうもありがとうございます。(大江田)
| 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8
|
▲このページのTOP
▲Quarterly Magazine Hi-Fi index Page
|