|
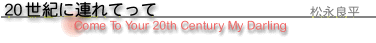
| 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8
|
第8回 椿正雄
「〈フラッシュ・ディスク・ランチ〉は最初は〈フラッシュ88〉になるはずだったんだ」
〈フラッシュ・ディスク・ランチ〉で椿さんに怒られた。そういう経験をお持ちの方は多いんじゃないかな。で、自慢じゃないけど、僕はそういう経験ありません(エヘン)。でも、椿さんと話をするようになったのは、つい2、3年前のこと。未だに呑みに行く約束は果たせてないが、以来、何となく親しくさせていただいている。
とはいうものの、この連載で椿さんに登場していただくのには、少し逡巡があった。明快で強い(激しい、とすら言える)意志と、歯に衣を着せぬ物言いと、無邪気な光を帯びた深いまなざし(時に二日酔いでトロンとしていることもあるが)を前にして、果たしてちゃんと話が訊けるだろうか? 一度、店内で椿さんがアメリカ人のディーラーと大声でやり合ってるのを聞いたことがあるが、あんなことになったら堪らないよ! そう物怖じしている僕に大江田さんはあるとき言った。「松永くんは追いつめられたり、無理をして何かをしようとするときに、とんでもない力を出すことがある。いや、むしろ、そういうときの方が文章はイイ」。猿もおだてりゃ木に登る。ならば、一年数ヶ月ぶりの再開となるこの連載。その初っ端を飾っていただくのは、尊敬する人物にして同時に難敵でもある椿さんしかいない。そう決心して申し出た。
この連載初めての同業者でもあるわけだが、ビジネス対談というわけではないので、少年時代から〈フラッシュ〉開店までの話で締めくくらせていただいた。まだ無敵になる前の椿さん、という感じで面白いんじゃないだろうか? 椿さんといえども、弱かったり、ビビったり、驚いたり、当たり前だが少年だった時代があったりして、下北の若者たちに付け入るスキ(共感とも言う)を与えてしまうんじゃないかな、という多少の心配もあるにはあるんだけど…。でも、これだけは言える。僕は椿さんのような人が好きだ。
取材は〈フラッシュ〉閉店後、場所を移して終電までの時間で行った。今回は大江田さんが都合により欠席ということで、片島くんに同席してもらった。彼がいなければ、とても質問なんか切り出せなかったかもしれない。感謝してます。
なお、文中でも少し触れてますが、この日、〈フラッシュ〉で松永はウィングスの『ワイルド・ライフ』を、片島はフォー・フレッシュメンの見慣れないアルバムを買ったことを付記しておきます。祝・開店20周年!
生まれも育ちもお店もずっと下北沢
松永:この連載で、いつも一番最初にみなさんにお訊きしてるのは、子供の時の音楽の一番古い記憶なんです。
椿:なんだろう…? あんまりちゃんと覚えてないんだけど『ピーターと狼』かなあ。
松永:クラシックの?
椿:あれって、お話が入るでしょ。その日本語版のレコードがあったんだ。それとも、あれかな。ビーヴァーが歌うやつ。チップマンクスみたいな。テープの早回しで3人くらいでハモって歌うやつ。
松永:失礼ですが、椿さんってお生まれは何年なんですか?
椿:(昭和)33年。この11月で44歳。多分、その『ピーターと狼』が小学校2年とか3年生の頃じゃないかな。いや、もっと前だったかもしれないけど。後で、デヴィッド・ボウイがやったりしてたよね。まあ、それより全然前の話だけど。
松永:お生まれも東京で。
椿:そう。オレは生まれてからずっと下北なんですよ。渋谷の日赤産院で産まれて、住んでいたのもずっと下北。
松永:その頃の下北はどうでした? 今とは全然違います?
椿:オレも子供だったし、よくは知らないんだけど、まず南口が無かっ たのね。井の頭線のガードがあるでしょ。ガードをちょっと行ったあたりに、地下に入るトンネルがあるのよ。今は入り口に蓋がされてるだけで、トンネルはあるらしいんだけど、そこをくぐって行くと反対側に出るのね。反対側に出て、北口から電車に乗ってたもの。ちょっと記憶が曖昧なんだけど、その記憶はあるんだ。
松永:小田急線は通ってたんですよね。
椿:通ってたけど、南口っていう出口は無かった。もともと下北は北口の一番街の方が栄えてて、こっち(南口)は、うちの親父が言うには、50年くらい前に越してきたときはお店は二軒くらいしか無かったらしいよ。
松永:じゃあ全然、若者のメッカでも何でも無く。
椿:オレが小学校に上がったくらいの頃には多分、もう南口はあったんだけど、だいたい今のマクドナルドの向かいあたりに、厚化粧のお姉さんというかおばさんが大体立ってて、子供が通ると「坊や、かわいいわね」みたいなノリで、ちょっとおっかなかったね。色街ってわけじゃなかったけどね。本多劇場ってあるでしょう? あそこの本多さんって人は、当時このあたりでいくつかバーをやってたらしいんだけど、それで成功してああなったらしいよ。まあ、オレもよくは知らないんだけど。で、そのバーっていうのが、割と大人の店なんだ。女の人が絶対いるような。そういうバーがここら辺には本当にいっぱいあって、そのいくつかはまだ残ってるんだよね。こういう街だから目に入らないんだけど。今、〈ロフト〉とか〈251〉(南口徒歩5分ほどになるライヴハウス)とかあるでしょ。あのあたりから先は、女の人が夜一人歩きしたら危ない、って言われてたんだよね。もっとずっと先に行くと「痴漢に注意」って看板だけが立ってて、場末のあんまりいいイメージの無いような場所だったね。
松永:じゃあ、当時はみんなが遊びに行くんだったら、一番街の方に行くか、それとも渋谷とか? 新宿とか?
椿:まあ、だいたい渋谷・新宿あたりで呑んできて、帰りに電車降りて、ここら辺で怪しげなバーの客引きに引っかかって…、ってパターンでしょ。小学校か中学校のときに、うちの親父がその辺のおねえちゃんがいるような店の客引きにつかまってさ、「お勘定が6万円になります」って世界で(笑)、家にいっぺん取りに来たことがあるよ。で、うちのお袋が親父に「北沢警察に通報します、って言え」って言われて(笑)。そしたら、帰ったらしいけど。
外道にはやられた。
松永:下北に一番最初にライヴハウス出来たのって、いつ頃ですか。
椿:とにかく、西荻窪とか荻窪とかよりは新しいよ。〈ロフト〉はそのどっちかが最初で、オレ荻窪はよく覚えてないけど、西荻はドラムとかが無いような感じじゃなかったかな。当時はフォーク・ブームだったから、〈ヤング・フォーク〉とか〈ヤング・ギター〉とかいう雑誌があったし、RCサクセションがまだ三人でフォークやってたし、かぐや姫とかもすっごい流行ってたし。下北の〈ロフト〉は、一応バンドで出来る感じだったな。
松永:それが売りになっていた、という感じですか。
椿:どうなんだろうね。今から25年くらい前なのかな。あと、その四つ角のミナミってパチンコ屋のところに〈マライカ〉ってライヴハウスもあったんだ。ちょうどその頃、町内にあった金子総本店っていう葬儀屋さんの娘さんの金子マリちゃんがデビューしたり(笑)、京都のバンドがこっち来てたよね。ウェストロード・ブルース・バンドが東京にやって来て、だいたい、メンバーは笹塚とかここらへんに住んでた。そういう人脈で、関西系の人たちがわりと集まるようにはなってたね。それでね、〈Zem〉っていうブルース・バーが交番のある踏切を向こうに渡ったあたりにあったんだ。矢吹(申彦)さんってイラストレイターのの妹さんがやってたの。オレらは高校生くらいからそこによく行ってたわけ。そうすると、ウェストロードのメンバーだとか、ウィーピングハープ妹尾(隆一郎)だとか、ちょこちょこ関西からツアーに来る人たちが寄ってたりしてて。あと、ミッドナイターズっていうジャンプのバンドがあったのね。それから、吾妻光良がまだ大学生で、スインギン・バッパーズ始める前にダーティー・ダズンってバンドをやってたんだ。そのバンドはアルバート・コリンズとかゲイトマウス・ブラウンとかをコピーしてやるバンドで、当時はジャンプ・ブルースが注目を浴び始めてたんだよね。〈THE
BLUES〉みたいな雑誌でもそれが盛り上がって取り上げられたりしてて。それで思い出したけど、東京には当時、ジューク・ジョイント・ブルース・バンドっていうかっこいいバンドがいて、それもウェストロードの弟分みたいな存在で、レコードとかは出せなかったんだけど、でも当時は一番かっこいいバンドだったね。
松永:ブルースの話にいつの間にかなってますけど、椿さんがブルースにハマり出したのっていつぐらいからなんですか?
椿:高一になったぐらいかな。それまでは、初めはフォークとかやってて。あと、中三から高一くらいではロック・バンドをやってたね。あの頃、郡山で「ワン・ステップ・フェスティヴァル」(1974年)ってのをやっててね。オレの友達にも行ったヤツが二人くらいいるんだけど。そのときにNHKでドキュメンタリーみたいなのが放送されたんだよね。
松永:一年くらい前に「NHKアーカイヴス」で放送されてましたね。
椿:ああ、そう。スモーキー・メディスン(Charが在籍したバンド)って放送に出てたっけ?
松永:いや、放送されたのは、外道とか、イエローとか。
椿:そうだよね。外道が一番おいしいんだよね(笑)。そのとき、外道にオレは結構やられて、バンドでも外道をやってたんだよ(笑)。
松永:そうなんですか! 僕、外道は大好きですよ。
椿:「ゲー、ゲッゲッゲッゲッゲッゲ、ゲドー!」って(笑)。その頃はその「香り」って曲と「天国への道」をコピーしてた。あと、オレが覚えてるのは、加納秀人(ギター)がすぐギターのネックをしごくようにして音出すんだよね。当時はわかんないじゃん。どうやって弾いてるの? それは何なんだ!?って(笑)。オレ、最近もギター弾いてるけど、あの、チュキチューンっていう、あれだけは誰にも負けない、っていう風になりたいんだよね(笑)。
松永:弾けるようになりました?
椿:わりと…、上手いかもよ(笑)。
松永:あれ、かっこいいですよねえ(笑)。
椿:でもさ、外道のレコードは持ってなかったんだよね。
松永:じゃあ、どうやってコピーしてたんですか?
椿:いや、「香り」は歌詞なんて無いじゃん(笑)。で、もう一個の方は何か適当な歌詞を付けてやってたな。あと、すごいヘタッピイなんだけどオールマン・ブラザースとか。で、ちょうどその頃、オレのバンドのギターのやつが先輩のバンドのサイドギターに誘われて。その頃、その先輩はブルースに凝ってて、で、彼がそこでブルースを覚えて、オレたちに聴かせてくれたんだ。当時、放送委員会とか言って、放送室によく出入りしてたから、そこでよく聴いてたね。オレらの間ではマジック・サムの『ウェスト・サイド・ソウル』とか『ブラック・マジック』とか、ジュニア・ウェルズの『イッツ・マイ・ライフ・ベイビー』とかが名盤とされてたね。今聴いてもいいよね。こないだも店ですごい音で聴いてたんだけど。
松永:そこら辺が椿さんの現在への振り出しになりそうですね。
椿:だんだん人脈が広がってきて。バンドのメンバーにも、もっと上手いヤツ入れたい、ってことになると、他の学校のヤツとかとの付き合いが出てきて。中央線沿線の、荻窪とかあの辺のヤツらとバンドやるようになったのよ。で、ブルースと言えば、高円寺の〈次郎吉〉(現:JIROKICHI)じゃん。オレらも下北からよく見に行ってたし。だから、交流はあったよね。スイギンバッパーズでドラム叩いてる岡地(曙裕)とかね。そうだ、その頃ね、金子マリ&バックス・バニーの二人目のキーボードになった近藤大ってやつがいて、その人がオレの二年先輩で、その人とドンベエ永田ってヤツと岡地くんと、あと、今はマニピュレーターですごく有名になった藤井丈司くんがギターを弾いて、小坂忠の『ほうろう』のコピーをする、っていうバンドやってたんだよ(笑)。あと、ヴォーカルの人がひとりいた。オレは『ほうろう』って当時、オレは聴いたことなくてね。でも、そのバンドがやってる「機関車」とか聴いて、「おお、かっこいいなあ」って思ったりしてたことがあったな(笑)。
松永:椿さんはそこで何やってたんですか?
椿:いや、オレはそのバンドには入ってなくて。まわりで見てる方だったんだけど。自分のバンドではギターとヴォーカルやってたかな。まあ、ギター、あんまり弾けないんで(笑)。
松永:そうなんですか(笑)。すごいギターとかにこだわっててそうなイメージなんですけど。
椿:練習はしてるんだけど(笑)。あんまりものにこだわる方じゃないんで。いや、というか、変なこだわり方をするよね。なんだろ。自分の楽器が一番いいと思うからね。他人のすごいギターとか貸してもらって弾いてても、まあ、オレのギターがあるからいっか!みたいな(笑)。オレのギターの方がかわいいぜ、みたいな愛し方をするよね。
松永:下北と中央線沿線の高校生から見た音楽性の違いみたいなのは感じてましたか?
椿:まあ、昔はよく高円寺は行ったよね。レコード屋もあったし。でも、確かに、高円寺ってすごい近くて、友達もいっぱいいるんだけど、何故かそんなには会わないんだよね。
それに、ある意味、似てると思うんだよ。それぞれものすごい音楽的にも自給自足的なところがあって、どうしても用が足りなきゃ新宿とか渋谷に行く、みたいな。
松永:お互いには、近いようでいて電車で行くと一本では行けなかったりしますしね。
〈OZ LAST DAYS〉に行ったことがある
椿:ああ、中央線と言えば思い出した。吉祥寺に〈OZ〉ってライヴハウスがあってさ、中学の時にオレ行ったんだよ。『OZ LAST DAYS』って知ってるでしょ?(注:73年8月、ライヴハウスの閉店に際して行われたライヴの模様を記録した2枚組自主制作盤。。正式には『OZ
DAYS LIVE』。裸のラリーズ、タジ・マハール旅行団、南正人、アシッド・セヴンらの演奏を収めた。限定で関係者に配布され、幻のアルバムと言われている)オレ、あの一日にも行ったんだよ。アシッド・セヴンと南正人の日に(笑)。ああ、思い出したよ。ブルース・バンドをやり始めるころだな。他にその頃見た記憶があるのは夕焼け楽団とか、野毛ハーレムってバンドがすごいかっこよかった。神大(神奈川大学)のオールナイトっていうのを、その頃、毎年やってたんだ。
松永:え? その頃って椿さんはまだ15とか16歳くらいじゃないんですか?
椿:そうだねえ。なんか冒険しに行くような感じだったな。まわりはヒッピーばっかりだったけど。
松永:〈OZ〉ってどんなところだったんですか?
椿:まずねえ、靴脱いで上がるんじゃなかったかな。木造の二階なんだよね。中に柱がところどころに立ってて。雰囲気としては柔道場に柱が立ってるような感じ。畳だったかもしれないけど、とにかく地べたに座るんだ。まあ、最終的にはみんな立っちゃうんだけどね。
松永:今の吉祥寺で言うと、どのあたり?
椿:駅からちょっと歩いたら看板が見えた、っていう記憶があるんだよな。もしかしたら、今の〈スターパインズ・カフェ〉がある方に向かって行った右側じゃなかったかな。
松永:というと、割と風俗街があるあたり…。
椿:うーん。でも、木造の二階建てで、そんなイメージでも無かったな。ああ、そうだ。南正人がヒドイんだよ。その頃、二、三回は彼のライヴを見てるんだけど、だいたいワン・ステージ一曲なのよ(笑)。オレが見たときは、当時流行ってたヘレン・レディの「デルタ・ドーン」を「最近覚えた曲でいい曲なんや」とか言って始めるわけ。で、やるんだけど、もうそれだけ延々とやるわけ。一応。バンド編成で。で、そのうちみんな踊り出すみたいな、トランスとかそういうのに近い感じがあったね。どっかのオールナイト・コンサートで見たときも、簡単なコードの曲をまた延々とやるんだけど、最後はみんなもう列になって客席を練り歩いて踊ってるわけよ。ヒッピーみたいな熱心なファンもいたし。ある意味すごいな、とは思ったけど、率先してそれに加わって踊るというほど、いいとは思わなかったな。キャラメル・ママがバックをやった南正人のアルバム(73年ベルウッド)とかがまだ出る前だったかな。
松永:あのアルバムはすごくかっちりしてて、かっこいいですよね。
椿:そうだよね。ファンキーだしね。あの曲、「ウソの恋でもいい〜」ってやつ、「午前4時10分前」だっけ。今でもすごく好きだな。オレと一緒のバンドでベースやってたドンベエってのが、そこらへんから細野さんがすごい好きで、そのうち細野さんのローディーみたいなことやって、YMOのツアーでアメリカとかも行ったりしてるんだよ。で、ドンベエがローディーを辞めることになって、そのあと入ったのが藤井丈司なんだよ。ドンベエと藤井は、さっきも言った小坂忠のコピー・バンドを一緒にやってたバンド仲間だったというね。
松永:当時、見てたバンドで他によく覚えてるのはありますか?
椿:あと、その頃で印象に残ってるのは、友達のブルース・バンドが前座を務めた上田正樹とサウス・トゥ・サウス。初めて見たときはすごくて「これはいったい何だろう?」って思ったもんな。すごく覚えてるのはクンチョウって人がメンバーにいて、「こいつ黒人じゃねえか?」って思ったな(笑)。あと、有山さんがエレクトリック・セットになってもジャズ・マスターだったか何だったか、すごい渋いギターを上手く弾いててかっこよかった。それに、あの頃のキー坊(上田正樹)はかっこいいとか、そういうものをもう通り過ぎてるよね。とりあえずビックリした。いきなり「ほら! 飛ぶで! お前ら、気ぃ付けぇや!」だからさ。「飛ぶ」って何なんだよ(笑)。
松永:サウス・トゥ・サウスはあのライヴ・アルバム(『この熱い魂を伝えたいんや』)ですら、彼らの全盛期からしたら出来が良い方では無い、って言いますもんね。
椿:まあ、あのときの録音とか、ライヴのノリとかがそんなに良くなかったんだろうね。多分。よくわからないけど、ライヴバンドって、外道とかもそうなんじゃないの。だって、TVで外道見たときは、すごい、何だこいつら?って思ったけど、アルバムはね、それほどでもなかったし。あと、それから、ファニー・カンパニーが解散した直後に見た桑名正博もすっごいかっこよかったね。
松永:ファニー・カンパニーも最高ですけどね。
椿:あの「魔法の正体」って曲が入ってるアルバム、ファニー・カンパニーのファーストだっけ。あれしか聴いたことないけど、アルバム通して好きだな。「スイート・ホーム大阪」はヒット曲として知ってて、すごい好きだった。キャロルとかと同じ頃だよね。
松永:キャロルはどうでした?
椿:かっこいいとは思ってたんだけど、オレにはすごい入り込めるとは思えなかった。そしたら、そこに「スイート・ホーム大阪」が出てきて、こっちの方がかっこいいなあ、ってなったんだよね。とにかく桑名正博はかっこよかった。そういう意味ではサウス・トゥ・サウスはバンドとして「これは何だ?」って感じさせる存在だったけど、桑名正博の方は「この人はすごい!」って思えた。当時、バックス・バニーが出るコンサートが、どっかの学園祭であって、さっき出てきた近藤がバンドを手伝ってたから呼んでくれてね、オレも楽屋に出入りして、まだ高校生なのにビールとか呑んでフラフラしてたわけ。そしたら桑名正博が通りかかって「おい、ニイチャン、大丈夫か」みたいな感じでね。そのあと、ステージで見たら、すっげーかっこよかったんだ。うちの店で桑名さんのバンドでギター弾いてたやつがバイトしてたことがあって、そいつが言うには「桑名さんはロックをやらせると最高。歌謡曲をやると、ちょっとなあ…」って。
レコード、レコード、レコードの日々
松永:その辺が高校生くらいの話だと思うんですけど、大学はどちらへ行かれたんですか?
椿:大学は都立大に2年だけ行きました。
松永:中退? やっぱりそんなに面白くなかった?
椿:いや、もともとそんなに真剣に考えてなかったっていうか。大学行ってもしょうがないだろ、みたいな時代だったからさ。じゃあ大学行かないで何をするかといっても、とりあえずこれといってやりたいこともなくて。でも、中途半端な状態になるのはとにかくイヤで、浪人だけにはなりたくなかったんだよね。で、大学に入って。オレ、高校の頃からレコード好きだったから、受験が終わってからすぐにバイトするようになって、下手したら二月の終わりくらいからやってました。合格して上京してくる受験生を食い物にするようなバイトしてたから(笑)。不動産屋さんの看板持ち。で、まだ東京のこと何にもわからないヤツつかまえて「大学どこ? いい物件あるよ」とかいい加減なこと言って売ってたなあ(笑)。それで、バイト出来るようになってから、お金は全部レコードに使ってたね。
松永:その頃はどの辺で買ってたんですか?
椿:いろいろ。数で言えば〈ハンター〉が一番多かったな。金額で言えば〈ディスク・ユニオン〉。〈ハンター〉は、当時はありとあらゆるところにあったからね。
松永:その頃だと、銀座、渋谷…。
椿:大井町店がわりと穴だったんだけど、あそこまでは滅多に行かなかったな(笑)。〈ハンター〉ってセンター仕入れでしょ。そして各店に分けるんだよね。だから、客の少ない店の方がいいもの残ってるわけよ。
で、オレ都立大に行ってたから。都立大店って駅を降りて、ちょっと右に曲がるとあったのよ。それで、成り行きとしては、どうせ授業はもう十分遅刻してるわけだから、まず〈ハンター〉寄るじゃん。で、欲しいレコードあったら買うじゃん。で、一応、そのあと学校行くわけだけど、買ったレコード見てたら早く聴きたくなるじゃん。それで、学校なんか馬鹿馬鹿しいから、帰るわけよ(笑)。多分、学校行った回数より、〈ハンター〉行った回数の方が多い(笑)。
松永:僕もヒトのことは言えません…(笑)。
椿:あと、ディスコとかからの処分レコードみたいなのが数寄屋橋店とか行くと時々あってね。段ボールに山ほどあって見切り処分で投げ売りしてるわけ。その頃、ジェームス・ブラウンとかファンカデリックとかすごい安かったから。ファンカデリックなんて買うヤツいなかったから(笑)。新宿の〈帝都無線〉に行ってパーラメントの『Pーファンク・アース・ツアー』の二枚組を買おうとしたら、お店の知り合いの人に止められたもん(笑)。「お前、こんなの聴くのやめろよ」とか言われて(笑)。
松永:(笑)。
椿:その頃の雑誌の〈SOUL ON〉に出てた広告とかでも「黒人のKISS! 謎のファンク軍団、ベールを脱ぐ」みたいな調子だったからね。黒人のKISSだよ(笑)。
松永:レコード屋でバイトとかはしなかったんですか?
椿:しました。最初にバイトした店は〈DUN〉(ダン)って店で、今は〈シカゴ〉があるところかな。西新宿の小滝橋通り沿いの2階。もともとは〈シンセイ・サービス〉っていう大阪の古いインポーターがやってた店で。その〈シンセイ・サービス〉っていうのが、おそらく戦後最初に輸入盤取り扱いを始めたくらい歴史が古くて、ブルー・ノートが国外プレスを許さなかった時代(1970年代中頃まで)に、それを輸入して日本用のライナーとかを封入してた会社だったんだよね。あと、サヴォイ・レコードの商標の権利を持ってたんだよ。昔、中村とうようさんがサヴォイのジャンプとかジャイヴの編集盤作るときに、そこの社長に許可を取りに行ったらしい。
松永:じゃあ、その直営店が〈DUN〉。
椿:そう。そこの大阪にある体育館みたいな倉庫に行くと、もうホントにタイム・マシンに乗ったような感じになるくらいレコードがあったな。
松永:〈DUN〉にはどれくらい働いてたんですか?
椿:多分、一年くらいじゃないかな。
松永:それはバイトで?
椿:そう。当時のレコード屋って、アルバイトがいっぱいいるのよ。で、何をやってるかっていうと、例えば新宿レコードとかもそうなんだけど、アルバイトは柱ごとに立ってて、万引きを防止してるんだよね。でも、レコード屋でバイトしてる子って今も昔もあんまり変わらなくて、大学生とかが音楽好きだからバイトするわけでしょ。だから、ちょっと気を許すと二人くらい寄り添って好きな音楽の話とかしてて仕事しないわけ。で、オレ、最初は店に週2日とか3日くらい入ってたんだけど、あるとき、お客さんに「何とかのレコードある?」って訊かれて、確かあれはまだ5枚くらいあったはず、と思ってコーナーを見るんだけど、無いわけ。で、在庫を見ると、まだ数が残ってるわけ。前の日のバイトがタコだから、売れたのを補充してないわけだよ。だから、それからは、前の日の売上を見て、在庫が無いことになってるのをチェックするようにした。
松永:基本ですね(笑)。
椿:だいたい、その頃のバイトは縁故で入ってるのが多くてさ。だから、辞めるってヤツがいたら、新しく雇わないでそこのシフトにオレを入れてくれ、っていうことになって、最終的には週5日くらい入るようになって。「じゃあ、社員にしてください」って言ったのよ。そう頼んだら、大阪の社長が「あんた大学生やろ。社員になりたかったら大学辞めてこい」って言って。で、じゃあ、ってことで大学を…(笑)。
松永:辞めちゃった(笑)。
椿:それで社員になった。ところが、日本橋に新しくレコードの卸しの営業所を作るということで、そこに配属になっちゃったわけ。その頃、オレは〈DUN〉の店長さんを自分のレコードの師匠だと思ってて、その人の下で働きたいと思って社員になったつもりだったから、結構、荒れたね。
松永:椿さんの師匠!
椿:その人、古谷さんっていって、カントリーの大家なんだよ。(鈴木)カツさんとかもよく知ってる人なんだけど。ポピュラー系全般も強くて、黒っぽいのはほとんどダメだったけど。
松永:でも、逆に椿さんとジャンルがかぶらない分、学ぶものがあったというか…。
椿:とりあえず、オレが毎日店に行って、掃除とかするでしょ。そのときに必ずFENの〈アメリカン・カントリー・カウントダウン〉がかかってるわけよ。最初は、何でこう、こんなつまんないのかけてんのかな、と(笑)。そう思って掃除してた。でも、その人には彼が以前にいた〈帝都無線〉時代から付いてるお客さんたちがいて、仕入れてくる商品を「やっと入りましたよ」とか言って渡すと「ああ、良かった〜」って、みんなすごく喜んで買って帰るわけよ。そういう常連さんだから、オレもだんだん話もするようになるじゃん。で、オレが、この人いい人だな、と思うような人が、オレがつまんないと思ってるカントリーのレコードを買ってくわけ。その頃、オレなりに何となく思ってたのは、いい音楽を好きな人はいい人だろう、いい人が好きな音楽ならいい音楽だろう、と。ということは、この人が好きなカントリーっていう音楽もどっか面白いんではないかな、と思ったのが第一歩だったな。
松永:なるほどね。
椿:そしてある日、不良盤かなんかで戻ってきたメル・ティルスのレコードがあって。「デトロイト・シティ」って曲知ってる? それをかけてたら、その頃、オレがよく聴いてたキング・レコードのリズム&ブルースとかとすごくかぶって聴こえたのよ。うわ、これ、ちょっとかっこいいな。そこら辺からだよね。それが多分、レコード屋としての目覚め、みたいな感じだったよね。
松永:すごくわかります、その感じ。
椿:で、その頃、店長は黒人音楽ほとんどわかんないでしょ。だから、オレがそういうの仕入れて、〈THE BLUES〉みたいな雑誌とかに広告出すと売上上がりますよ、とか言ってたら、じゃあ広告やってみて、ってことになって、そこから自分で広告を書き出すことになったんだよね。
松永:まさに、それが今に至る手書きのスタートなんですね。
椿:ただ、当時は一生懸命、キレイにやろうとしてたけど(笑)。
レコード屋を開くためにバーテンやってたんだ
松永:ところが、さっきも話に出ましたけど、その店長さんと別れて日本橋で働くことになってしまって。でも辞めるというほどではなかったんですね。
椿:まあ、社員になったわけだからね。でも、その卸し屋の上司に藤原さんっていって、オレの第二の師匠になったと思える人がいて。それに、かえって良かったのは、その卸しを経験することで、カタログ的なこととか、いろんなことを覚えたのよ。多分、中古盤屋さんの人たちはそういうとこをわかってる人はあんまり多くないと思うんだけど。その頃、オレはハンターでよくジャズとか買ってたということもあって、ジャズ担当になったんだ。で、ECMってレーベルがあるんだけど、それがまだ当時はアメリカ盤が無くて、ドイツ盤しか手に入らない時代でね。そのドイツ盤の独占輸入権を持ってたのが〈シンセイ・サービス〉だったんだよ。それで、キース・ジャレットの新譜が出るとよく売ってたね。で、〈オザワ〉ってのがすごくユニークな店でさ。カット盤は、下の背中じゃない方(取り出す方)が切れてるヤツじゃないと取らない。
松永:ほおー??
椿:つまり、お客さんの方に向いてる背が切れてると、売り物にならない、と。
松永:(笑)。
椿:あと、その頃、結構学んだのは、船便でレコードを輸入してた時代だから、コンスタントに売れるものは在庫を持っておかなきゃならない。すべてのアイテムを各5枚とかではダメなわけ。売れるものは厚く、売れないものは薄く。それを結構覚えたよね。例えば、ラモーンズだったら、ファーストと『エンド・オブ・ザ・センチュリー』を厚く、とか。インパルスのカタログをお店に流して、注文を集めると、やっぱりコルトレーンの『バラード』が一番多く来るわけ。そういうことが、〈フラッシュ〉を始めてから役に立った。最初は基本的に廃盤しか売ってなかったんだけど、若者が来て「ラモーンズありませんか」って訊いてくるんだけど、「タワー行けばいいじゃない。安いんだから」って言うと、「いや、〈タワー〉行っても無いんですよ。『エンド・オブ・ザ・センチュリー』が欲しいんですけど」って。何やってんだ〈タワー・レコード〉は? で、それで、そういう風が吹いてるんだったら、中古盤に混ぜて、新品の再発盤とかを売っていこうかと。それでスライの『暴動』とか再発になったときに何百枚うちで売ったか。
松永:いや、それは本当にそうなんですよね。大きい店は売ってるものも多いけど、実は欲しいところに手が届かないという。今もあんまり変わらないですよ。ところで、ハイファイがファイヤー通りにあった頃、というか、ハイファイになる前のお店にレコードを卸しに行ってたという話を以前にお聞きしたんですけど、それはこの頃の話なんですか?
椿:いや、辞めてからだね。で、卸しじゃなくて、委託でやってたんだ。ハイファイの前の店は、〈フルハウス〉っていうレコード屋だったんだよ。
松永:それは聞いたことあります。
椿:そこはブラック専門店だったんだけどね。もともと卸し屋時代の取引先だったんだよ。向こうも新品だけじゃなくて廃盤も欲しいじゃん。だから、これこれ事情を話して、レコードを置かせてもらった、と。それで、入って横の棚が全部、オレが置いてたレコードだったんだよ。もともとはね、当時、〈マンハッタン〉が消防署の裏に出来て、行ったんだけど、欲しいレコードは山ほどある。でも、買えるレコードが無いんだよね。高い。せいぜいこれぐらいだったら買える、っていうレコードは、どっちかと言うと、あまり欲しくないものばっかりなんだよね(笑)。それで、もともと自分でレコード屋をやりたいと思ってたから。古谷さんの下で働いてたときから、アメリカの廃盤屋からリストを取り寄せて、まあ、カット盤屋なんだけど、そこからオイシイものを仕入れて、自分で売ってたんだよ。〈TSUBAKIレコード〉って言って。確かに、ラモーンズのファーストを新品で売ってるのも楽しいけど、手に入らないものを売るのって楽しいじゃない。それで、もっと自分の理想とする、安くて良いものを売るような商売って出来ないかな、って当時から思ってたんだよね。でも、自分の給料は高くないから、お金がたまんない。それで、会社を辞めて、バーテンをやったわけ。
松永:バーテンですか!
椿:バーテン時代はオレはすごい収入があったよ。バーテンって基本的に当時の時給は1000円で、一日だいたい10時間働いて、休みは月に1日しかなかった(笑)。それが70年代終わりかな。配膳会ってわかる? レストランとかパーティーにウェイターとかバーテンを派遣するところにいたんだよ。で、それをやりながら下北の〈Edison〉にレコードを委託で置いてて。そこが日本で最初にシンガーソングライター・ブームというかシンガーソングライターの高値を作った店なんだけどね。当時バーズの『バードマニア』とかを一万円くらいで売ってたんだから(笑)。まあ、オレはその頃からアル・クーパーとかバーナード・パーディーとか、今と同じようなレコード売ってたんだけどさ。いろいろコメント書いてね。
松永:へえー。
椿:あとね、卸しで働いてたときに、すごくレコード安く買えたのよ。これが何故かって言うと、Aっていう大きなお店に卸してたんだけど、あそこはものすごく条件が厳しいところでね。まず基本的にこっちの出し値は一番安いわけ。支払いも長い手形で。まあ、量だけはすごい売るんだけどね。で、なおかつ、返品枠っていうものがあって、納入したものの何%までは返品可能で返ってくるわけよ。それを、もともとあそこは日本盤をやってるところだから、日本盤と同じセンスで判断しちゃって、ちょっとスレがあったりしただけで返品になっちゃうんだよ。ほとんど聴いてなくて、封開けただけなんじゃないか?っていうものまで戻ってくるんだ。で、その戻ってきたレコードを、また200円とか300円とかの卸し値にしてAに再出荷させるんだよ。そして、それを目玉商品とか言って、道ばたに段ボール出して売るんだよ。そういうやり方って、すげー頭くるじゃない! みんな頭来てたわけよ。
松永:確かにそれはえぐい。
椿:それでさ、Aってさ、うちみたいな営業所に来るときに、必ず飯ドキに来るんだよね(笑)。担当者はそんなに給料高くないわけじゃん。だから、取引先で飯をおごらせたりとか、「今度、社員旅行があるから」とか何とか言うのよ。そうすると、こっちは日本酒の何本かとかあげなきゃいけないんだよ(笑)。そんでね、そういう感じだから、とにかく返ってくるのが癪だから、うちの所長のはからいでもって、働いてるヤツらがみんな欲しいレコードを、Aに戻す前にまず買っちゃうわけ(笑)。だから、だいたいのレコードは2、300円で買ってたね。新譜のレコードも一ヶ月くらい待てば、だいたい返品で買えてた。そういうのとか、とにかくありとあらゆるレコードを買ってたから、それを辞めてからは委託で売ってたんだ。それで大体に月々10万円くらい売上があったからね。それで生活して、バーテンの方のお金は毎月30万ずつ貯金してたんだ。
ついに初めての買付へ
松永:いよいよ話が〈フラッシュ・ディスク・ランチ〉に近づいてきましたね。
椿:で、お金が2、300万貯まったんで、アメリカに行くんだけど。
松永:買付ですね。80年くらいですか。
椿:そう。買付っていうか、初めはどういうことになってるのか見に行こうと思ったの。もし面白かったら、しばらく住んでもいいや、くらいに思ってたんだけど、そんときにもう、前のカミさんと一緒に住んでて。「アメリカに行くっていうのは前からの予定だったから、とりあえずオレは行くぞ」と、置いてったわけよ。でも、置いてって、やっぱり寂しいわけさ。結構早く帰りたいわけよ(笑)。行くときは、「いや、オレはもう向こう行って、帰ってこないかもしれない」とか言ってたのに(笑)。その頃の友達とかにも「バカヤロ。お前は最低だ!」とか言われたりしてたんだけど(笑)。
松永:(笑)。
椿:どうしようかな、と思ってたんだけど、とにかくこの金を使い果たせばいいわけだ、と。毎日ライヴを見に行って、毎日レコードを買って、そのレコードを送ったんだよ。で、その買ってきたレコードを〈Edisun〉とか、ハイファイのあったところにあった〈フルハウス〉にも置いたんだ。
松永:もうちょっと最初の買付のときの話をお訊きしたいんですけど、アメリカのどこに行ったんですか?
椿:オレはロスに行った。
松永:泊まってたのはモーテル? それともフラットみたいなのを借り たんですか?
椿:キッチンが付いてる週払いのホテルだった。
松永:ドルはまだ240円とかの時代ですよね。
椿:それはすごい大変だった。1ドルで買えば1000円で売ると思え、 みたいな。2ドルで2000円、3ドルで3000円とか、それに近いものがあったな。
松永:車は?
椿:いや、免許持ってなかったのよ。だから、免許を取った。
松永:えっ? 向こうで?
椿:日本人の教習官がロスにいてね。あっちのって教習じゃないんだよね。まず最初に陸運局みたいなところに行って、ペーパーテストを受けて、受かると仮免がもらえるの。仮免を持ってると、免許を持ってる人が付いててくれれば、路上で練習していいの。だから結構ビビったよ(笑)。日本人新聞とかに「教えます」みたいなのが載ってるから電話して、そしたらその人が来てくれて、とりあえずじゃあ行きましょうか、って人通りの少ない通りまで行くわけ。そこで「じゃあ、乗ってみましょうか」って。
松永:いきなり(笑)。
椿:それは特殊な車でね、助手席にもハンドルが付けられるんだ。ブレーキもある。ぶつかりそうになると「おっとぉ!」とか言って、ハンドル切ってくれるんだけど(笑)。
松永:ちなみに、その頃って、まだ買付ということ自体がまだ珍しかった頃でしょ。
椿:(深い声で)いやぁ…でも、素晴らしかったですよ、当時は。黒人街のすっげえ古そうなレコード屋行ってさ、仕切がすごく細かくなってるんだ。で〈F〉のところを見ると、〈Full
Moon〉ってのがあるわけよ。お前、仕切作ったってレコードあるわけねえじゃねーか!って思って見たら、シールドのフル・ムーンのファーストがドーンとあるわけさ!
松永:黒人街は怖くなかったですか?
椿:怖かった(笑)。でね、レコード屋ってさ、なにげにタチの悪いヤツらがたまるところなんだよね(笑)。ゲーム機とかが店の中に置いてあったりしてさ。床屋とかもさ、割と街の集会場みたいな感じじゃん。レコード屋も結構そうなんだよ。でもさ、レコードなんか、あっちではもう全然売れないわけよ。たまにお姉さんが来て「これ聴かせて」とか言ってさ、やっと一枚買ってった、みたいな世界なんだよ。そういうところで、こっちはレコードいっぱい買うわけじゃん。だから、なんかその悪そうなヤツらにも「こいつに構うな」みたいな指図して守ってくれた、っていうのはあったね。
松永:なるほど。
椿:実は〈フラッシュ・ディスク・ランチ〉っていう店の名前は、〈フラッシュ・ミュージック・スタジオ〉っていう、そのレコード屋が由来なんだよ。〈フラッシュ〉っていう名前の付いてる店が二軒あって、一軒はお母さんがやってて、そこにフル・ムーンのシールドがあったんだ。もう一軒はその息子がやってた。そこはね、60年代の終わりには多分、レーベルも持ってたんじゃないかな。黒人街のレコード屋って、伝統的にそういうところがあるんだよ。インディー・レーベルってそういうレコード屋がやってるパターン多いし。メジャー・ヒットになりそうになったら、メジャーに売るんだよね。
松永:それは秘話ですねえ。
椿:あとは、店を始めるときの相棒ってのがいて、そいつが「店の名前なんてなんでもいいんだ。ロゴさえかっこよければ、どんなんでもいい」って言ってたのね。でも、オレは、最初は〈フラッシュ88〉っていうアイデアがあって。それは「全品880円」にしたかったっていうやつなんだけど(笑)。それだけはやめてくれ、って言われたんだよね(笑)。
松永:(笑)
椿:だったら、次は〈フラッシュ・ディスク・スワップ〉っていうのを考えた。でも、それもやめてくれ、と(笑)。〈スワップ〉っていう言葉に、世間的に良いイメージが無い、と。
松永:英語圏だと、そうでもないんですけどねえ。
椿:それで、多分、〈ハリウッド・ランチ・マーケット〉とか、そういうのが頭のどっかにあったのと、アメリカ行くとさ、〈何とかランチ・マーケット〉みたいな名前の、卵とか野菜とか売ってるところあるじゃん。それで〈ランチ〉がいいな、と。〈フラッシュ・ディスク・ランチ〉、それで行こう、と。逆にちょっとぐらい長くてわかりにくい名前の方がいいだろう、ということで決めたんだ。
松永:結局、その最初の買付はどれくらい行ってたんですか?
椿:2ヶ月で200万円レコードに使って、60日間居て60本ライヴを見たかな。そのとき見たのでよく覚えてるのが、ライブの一部と二部の合間によくコメディアンが出てくるんだよね。で、〈パリジャン・ルーム〉って言って、レッド・ホロウェイってサックス吹きがやってる店だったんだけど、レコードも出してるリナルド・レイってヤツが出てて、そいつが、客をいじるのよ。オレなんかすごい怖かったもん。何故かっていうと、オレより前にウェストロード・ブルース・バンドのホトケ(永井隆)が彼女とその店に行ったときに、「今日はファー・イーストからお客さんがいらっしゃってます。さっきからニコニコ笑ってるけど、何言ってるのかわかってるのかな?」みたいに、その彼女がさんざんいじられたらしいんだ。それを聞いてたから、すごくビビってた。こっちに飛んできませんように、って(笑)。でも、その店にオレ何回も行ったから、ネタとか覚えちゃって。例えば、あるとき、オカマに道で出会った、と。そのオカマが「まあ、なんて素敵な靴を履いてるのかしら? その靴は何の革で出来てるのかしら?」ってしつこく絡んでくるんだって。面倒臭いじゃん。だから「It's
dick skin, man.」って(笑)。そしたら、オカマが「Kick my ass!!」って言う、っていうね(笑)。それが結構十八番だったんだよね。(注:このジョークの意味が知りたい人はハイファイ松永までメールください)
松永:(爆笑)。
椿:そういうネタをさ、わからないで笑ってると「お前、わかってるのか?」ってそいつに突っ込まれそうで。それがオレにとっての「英語の学校、その1」なのかもしれない(笑)。
「ブラック・ミュージック裏街道」のこと
松永:話は変わりますが、どうしても訊いておきたい話がありまして。〈レコード・コレクターズ〉誌上で連載されていた「ブラックミュージック裏街道」(1993〜95年)って僕はすごく好きだったんですけど、あれは中断したかたちになってますよね。あれは、なんとか単行本とかにまとまらないのかな、って思うんですけど。
椿:そうだよね。でも、オレも読み返したことあるけど、こんなに読みにくくて、つまんなかったかな、って思ったんだけど(笑)。
松永:そもそもあれをやろうと思ったキッカケというのは?
椿:あれは、結構、寺田編集長、佐藤副編集長と何回も打ち合わせをして大変だったな…(笑)。まあ、あれはある意味、すごく政治的だったとも言えるんだよね、オレにしてみれば。まず、自分に得になるっていう計算はちゃんとあったし。だけど、それを差し引いても、十分意味はある。オレの得にはなるけど、オレだけの得にはならないだろう、という風にはっきりと意識はしてたね。あんまりそうはっきりとその意図は言わなかったけどね。結局、あれはお店でお客にレコードを売ることの延長でさ、その中で、馴染みのヤツとは呑みに行ったり、一緒にスタジオに入ったりとかして、くだらない話をいっぱいするわけじゃん。そうしてるとね、いろんな情報が集まってくるんだよね。例えば、あるギター弾きがいて、こいつがかなり思いこんだら一直線な、勘違いもするヤツなんだけど、「椿さん、オレは最近気が付いたんですけど、コーネル・デュプリーとか、黒人のギタリストがああいう音を出す理由はね、頭の一拍目がアップストロークで弾くんですよ。そうすると、ああいう音になるんですよ」って言うわけ。確かにね、そういうこともあるんだよ(笑)。あるんだけど、それはたまたま彼がそう思いこんでるところに、コーネル・デュプリーがたまたまそういう風に弾いてるところを見ちゃったから、そう思いこんでるだけのことなんだけど(笑)。でもさ、そんなことも含めてさ、ほとんどガセに近いようなこととか、いろいろの情報が飛び交ってさ、それが話として面白いわけよ。それは実は〈DUN〉の広告を書いてたときもやってたことなんだよ。アルバート・コリンズってブルース・ギタリストがいて、すごい長いシールド付けてるんで有名なんだけど、そいつがライヴのとき、客席に降りて、延々シールド引きずって、ロビーにまで出て行って、そこに座って弾いてる、っていう話とかね。シールド長すぎるよ!って。そういうのを人から聞くのって面白いじゃない! だから「裏街道」をよく読んでみると、あれは結構、みんなの力を借りてるんだよね。
松永:僕みたいな読者の立場からすると、このレコードは何年何月発売の何番で、っていう話よりも説得力がありますよ。
椿:ミュージシャンから実際に聞いた話とかも面白いしね。例えば、山岸潤二から聞いたサンタナの話とかね。でも、実は、それ自体には汎用性は無いし、仲間内でしか通じない話だったりするんだけど、そういう話をわかりやすくするっていうかね。翻訳してるみたいなところはあるよね。で、それはある意味、お客さんに「カントリーみたいなレコードで良いの無いですかね」って訊かれたときに、「こういうのありますよ」とか、若いお客さんに何か訊かれて「これどう?」みたいな、そういうことと一緒なんだよね。
松永:そうですね。
椿:ただ、当時って情報が極端に少なかったから。オレはコツコツと情報を調べるヒマも無いし、そういうことは好きではあるんだけど、他にやんなきゃいけないこともあるし、食えないしさ。とにかく、今より情報が少なかったから成立してた部分もあると思うけどね。
松永:でも、情報が多すぎる世の中だからこそ、読み手は情報よりも「感じ方」みたいなものを欲しがってるんです。どういう風にこの音楽を感じたらいいのかな?っていうのがわからなくて悩んでる若い子たちって、いっぱいいると思うんですけどね。
椿:まあ、あの連載は中途半端に終わったような印象もあるんだけど、それにはいくつか理由があって。〈LA篇〉が終わって、次は〈NY篇〉か、大変だ、って思ったのもあるし。で、その中のひとつに、あれは、ある意味、ケース・スタディみたいに考えてたところがオレにはあったんだよね。大学とかでもさ「研究の仕方とはどういうものか」みたいなことを何かを例にとってやるでしょ。だから、そういう「やり方」をやって見せただけで、あとはみんなで勝手にやってよ、というか。今までだったら、簡単なキャッチフレーズで終わってしまってたようなミュージシャンたちについての書き方をさ、それは必ずしも合ってないでしょ?、っていうことが言いたかったんだ。ある意味、そういう考え方に読者がひとつ付いて行ければ、それは違うことにも同じように行けるでしょ、と。実際、橋本(徹)くんと話したときも、こいつもオレの知らないところでそれなりの筋道を立ててやってるな、と思ったもん。アプローチの仕方とか角度とかは全然違うよ、でも、彼は彼なりに筋があってやってるわけで、そういう意味ではすごい面白いな、と思ったね。そういう筋をみんなが見つけてくれたらいいな、と。
〈フラッシュ・ディスク・ランチ〉の20周年
松永:〈フラッシュ・ディスク・ランチ〉は、最初から、今の場所ですよね。
椿:昔は今の半分だったけどね。
松永:そして今年で20年。20年間、下北の音楽好きたちを相手にしてきたわけですけど、それに対する思いはありますか? 漠然とした質問ですけど。
椿:そうね。最近、すごい面白いね。
松永:そうですか?
椿:何故かって言うと、多分、松永くんたちもわかってると思うけど、長年積み上げてきた歴史や、いっときの主流だったレア盤が、ここ最近でかなり崩れ去ってるでしょ。逆に、サンタナとかを大音量でかけてると、「これ何ですか?」って飛びついてくるヤツらを相手にしてると楽しいんだよね、すごく。「これ、サンタナっていうんだよ、知ってる?」って言うと、「去年流行った人ですよね!」「そうそう!」っていう。
松永:さっきもお店でウィングスの『ヴィーナス・アンド・マーズ』の話しちゃいましたけど。
椿:オレ、ああいうレコードもすごい好きなんだよ。例えばさ、松永くんだってさ、うちの店でウィングスの『ワイルド・ライフ』買ったりするわけじゃん。オレ、そういうのが好きなんだよね(笑)。今やマニアックな廃盤のレコードに対する熱っていうのはどんどん醒めていってて、「もうどうでもいい」ぐらいのところまでもう来てて、逆にそういう普通のが売れたりする。本当に面白いよ。だいたい、この道に入ってしまうとさ、どんどん微に入り細に入り、になるじゃない。どんどん行くんだけど、ふっと気がつくと…、まあ、たいてい気が付かないんだけどさ(笑)、本当にこれ面白いのか?って思うという。まあ、どんなものでも、ある意味面白い、とオレは思う。ただ、そういう深みを追いかけて、こだわればこだわるほど、みんな同じになってるというかさ。じゃあ、カントリーのコンサートに来る人はみんなボウタイしてなくちゃいけないのか?って。そういうのの方がよっぽど保守的じゃん。それで、若い客層が来て騒いでると「最近の客はどうのこうの」とか言うわけでしょ。そういうのって、もっともくだらないことだと思うからさ。
(2002年10月7日 下北沢にて)
|
|
 |
フラッシュ・ディスク・ランチについて、ご存じ無い方のために少し補足をさせていただくと、なによりその良心的な価格と、幅広い品揃えで知られる輸入中古レコード店で、今や下北沢名物、いや東京名物とでも言って良いほど有名な存在。レコード・コレクターズ誌をお読みの方ならば、毎号に掲載される手書きの広告を思い出される方もおられるだろう。文中でも触れられているように、レコードの見方が悪い客を厳しくしかる店主、椿さんが恐れられていることでも有名な店で、買ってからのレコードをどんな風に扱っても良いとまでは言わないまでも、お店の商品をドタバタ手荒く扱うのは言語道断なのだから、椿さんのその態度には、僕は実に共感を感じている。
かつて僕自身もレコードや本を買わせてもらった。たまたま店頭になかった本について"予約"をお願いして帰ったところ、それから二月ほども経って忘れた頃に入荷した際に丁寧なご連絡の電話をいただいたことや、ニルソンのアルバムを店頭で購入した際に、「随分安いんですねえ」と思わず声をかけたところ、椿さんが「高くして売ってる店は、嫌いなんだ」と驚くほどの語気で語ったことなど、僕の"フラッシュ・ディスク・ランチ"体験は、すっかり忘れられない記憶となっている。
椿さんは、ロックな生き方で、ロックを売る人である。ロックを売りながら、ロックとかけ離れた生き方をする、これは嫌いだ。ロックを売りながら、売り方そのものもロックであろうと努力する人が好きだ。
インタビューの現場に立ち会いながら、お話の御礼をすることは出来なかったので、ぼくなりに近いうちにお店にお邪魔したいと思っている。どういう言葉でお礼をするか、それはフラッシュの2階にあがる階段を上りながら、考えることにしよう。(大)
| 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8
|
▲このページのTOP
▲Quarterly
Magazine Hi-Fi index Page
|