|
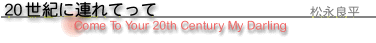
| 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6 | 7
| 8 |
第7回 若山弦蔵
「本質的な意味でのディスクジョッキーを僕はずっとやりたかった」
若山弦蔵さんは、007のション・コネリーを始め、TV・ラジオでその声を聞かない日は無い、というほど活躍されている日本の声優の草分け的存在にあたる。しかし、僕が若山さんにより強く興味を持ったのは、TBSラジオで毎週月〜金、夕方4時半から放送されていた「東京ダイヤル954」の粋なナビゲーター“弦さん”としてだった。数年前、夕方、僕はよくこの放送を聴いていて、若山さんの重厚な声に似合わぬどこかユーモラスで知的な語り口と、単なる埋め草ではないポップスの選曲センスに秘かにしびれていた。中でも、毎週一日だけ若山さん自身が選曲をされている日があって(今回、それは毎週月曜日だったことが判明した。しかも、他の一曜日は大江田さんだった!)、その大人なセンスと選曲の若さの混ざり合いがすごく魅力的だった。番組は6年ほど前に残念ながら終了してしまったが、若山さんは現在も毎週日曜、午前10時から、徹底的にイージーリスニングをかける長寿番組「バックグラウンド・ミュージック」で、絶品の語りを聞かせてくれている。
ご存知の方も多いと思うが、大江田さんはハイファイの店長のかたわら、その「バックグラウンド・ミュージック」の選曲を手掛けている。今回はその縁もあっての実現である。
しかし、その引き金となったのは大江田さんのこのひとこと「若山さんはね、ポツリと『リンダ・ロンシュタットの<デスペラード>っていい曲だよねえ』なんて言うんだよね」であったことは言うまでもない。オーソン・ウェルズに憧れていたこと、60年代末頃にあの伝説の「パック・イン・ミュージック」のDJを務めていたこと、武道館に毎日のように通ってロックのコンサートを見ていたこと……。大江田さんの垂らした針にまたしても僕は引っかかってしまった!
光栄にも、インタビューはTBSの第3スタジオで「バックグラウンド・ミュージック」の収録後に行われた。真剣勝負そのものの収録を終えた直後のブースに入り、マイクを挟んでそのまま僕は若山さんと向かい合った。
低く渋い声一本で生きてきた孤高の貫禄。このたたずまいのいったい何処に、かつて僕が親しんだ「弦さん」が隠れているのだろうか? そんなこちらの緊張をほぐすように、若山さんはカバンから大事そうに一冊のパンフを取り出した。それは、1953年(昭和28年)の古いJATP(Jazz
At The
Philharmonic。アメリカで第一級の人気ジャズ・ミュージシャンがグループを組んでアジア〜ヨーロッパを公演旅行するという企画)のプログラムだった。こうして、僕は若山さんの手のひらに乗っかった。
JATPを見て、何でも聴いてやろうって気持ちになった
若山:当時、僕は札幌にいたんだけどね、東京に行く機会があって、そのときにクラシックの公演のチケットを出来るだけ集めといてくれ、って頼んでおいたわけ。そしたら、このJATPがね、当時A席1000円のB席600円だったかな。まるでクラシック並のいい値段だったんだな、当時としては。今だったら2万、1万クラスだよね。それで、多分、フィルハーモニックっていう字が入ってたもんだから、クラシックだと勘違いして取っちゃったらしいのよ。だけど、非常に気が進まなくてね(笑)。ジャズなんてそんなもん誰が聴くか、なんて思ってた頃だから。
松永:当時はクラシック一辺倒だったわけですね。
若山:クラシック以外は音楽じゃない、と思いこんでた頃だからね。当時、まだ21か、20歳になったばかりだったかな。そんなわけで非常に気が進まなかったんだけども、当日他にすることもないから、まあ、しょうがない。その程度の感覚で行ったわけなんですよ。
日比谷の交差点から銀座の方へ向かって歩いて行くと、当時、まだ数寄屋橋があったんだよ。数寄屋橋を渡ってくと、左側に日劇、今のマリオン。そこ行くとね、どうもね、雰囲気が変なの。……外人ばっかりなんだよ。軍服着たアメリカの兵隊ばっかり。そういうやつがいっぱいいてね、どんどん中に入ってくんだ。こぉら何か異様な雰囲気だぜ、って。
松永:ヤバいところに来たかな、と。
若山:そうだねえ。でもまあ、大丈夫だろ、と思って入ったわけですよ。そしたら、もう、客席の半分近くはGIばっかりだった。まわりからは英語ばっかり聞こえてくるしさ。息が詰まりそうになるような男性化粧品の香り、それと連中の体臭とが交ざり合ってね……(笑)。
ウオォーっという物凄い雰囲気の中で始まったら、主宰のノーマン・グランツが出て来てね、「ニッポンノミナサン、コンバンワ」と日本語でまず挨拶して。それで「私はJATPのプロデューサーだ」って言って、1曲目の「ジャム・セッション・ブルース」ってのが始まったわけ。……いや、これが、まあ、すごいんだわ。ジーン・クルーパとエラ・フィッツジェラルドは出て来なかったけど、他の連中は次から次へと全員出てきてね。これが20分以上やったのかな。
松永:順々にソロを回してゆくんですよね。
若山:うわっ、これはまぁ、物凄いものに出会ったわい、と思ってね。当時、まず、こういう管楽器類がまともな音で鳴る、っていうのを見たのは初めてなんだよね。クラシックのコンサートだってね、ラッパなんかたいてい吹き損なうのが当たり前だったんだから、あの頃は(笑)。だけど、この連中はトランペットの凄まじいハイノートなんかをラクラクと吹いちゃうじゃない。これはすごいものを見たぞ…と思ってね、すっかり興奮しちゃって(笑)。
まわりはみんなアメリカ兵でしょ。みんな口笛は吹くし、足は踏み鳴らすわ手は叩くわで…。客席とステージが一体になるコンサートってのは初めてこのとき経験したわけ。コンサートってのはさ、だいたいお客はお客、ステージはステージで、一曲終わるごとに行儀良く拍手して、ってもんだと思ってたのが、そんな雰囲気じゃまったく無いわけよ。それもね、最近のロック・コンサートみたいな、音楽を抜きにして一体化してるような感じじゃなく、ただ騒ぐためだけってのとは違うんだよね。それともうひとつ大きな違いはね、人間と楽器の生のぶつかり合いでもってね、人間と楽器が一体になって表現をする、っていう凄さがあるでしょ。電気の力を借りないで。
松永:あ、じゃあ、もちろんアンプとかも通さないで。
若山:そうそう。今はどんなコンサートでも、マイクとスピーカー通して聴くことになってるけれども、この頃はまったく生だからね。だからベースの音とか、ハーブ・エリスのギターなんかも聴こえないくらいなんだけど、それが耳を澄ましてると、ものすごいブラスの音に交じって、ちゃんとギターの音が聴こえてくる。これが醍醐味なんだね。
音楽っていうのはさ、やっぱりそういうところで、演ってる人の心から聴いてる人の心へ流れ込んでくる、っていうのがホントなんじゃないのかな、って思うんですよ、僕は。クラシックってのはまさに、そうだと思うんだよね。
松永:それをクラシックだけで感じていたものが、このときJATPのコンサートで開かれた、ということなんですね。
若山:それまでは自分の興味の無かった種類の音楽にはまったく目を向けていなかったことが、えらい損だったなぁ、って思い知った。それからね、クラシックも聴くし、ジャズも聴く、歌謡曲も聴く。何でも聴いてやろう、っていう風に考えが変わったんですよ。そういう意味では、このコンサートは僕にはすごくエポックメイキングなコンサートでしたね。
で、この20年くらい後に、このときのライヴ録音盤が出たんだね。そのときに驚いたのが、この連中ってのが、幕が降りた後に、「さあ、これからはオレたちの時間だ!」ってジャム・セッションを演りだすんだね。それもレコードに入ってて、それがまたいいんだな。そんなこと無いでしょ、今のロックコンサートじゃ(笑)。いかにこの連中が音楽を愛してたか、ってことが判るじゃないですか。そういう時代の音楽が今忘れられてる、ってのがちょっと寂しいですね。
劇団で一番若かったのに、悪役か老け役しかやらせてもらえなかった
松永:この連載企画で、どの方にも必ずお訊きしてるんですけど、音楽についてのもっとも古い記憶って何でしょう?
若山:僕は姉が3人いて、僕は末っ子で長男なんです。小学生の頃にね、姉が会社で「名曲鑑賞クラブ」みたいなのに入ってて、レコードをみんなで持ち回りで持って帰ってきて聴く、みたいなのがあったんですよ。その中で姉が最初に持ってきたのが、メンデルスゾーンのヴァイオリン・コンチェルト。それを聴いて、「こんなキレイな曲があるのか」なんて思ったのがね、まあ、始まりみたいなもんですかね。
一番最初に好きなレコード買ったのが、スッペの「軽騎兵序曲」。何でそんなもの選んだのかって言うとね、やっぱりラッパの音が好きだったんだよね。一番最初のラッパの音がえらく好きでね。
松永:割と管楽器がお好きだったんですね。
若山:管楽器、……うーん、好きですねぇ。何て言うか、人間の叫びみたいな感じがするんですよね。
松永:人の叫びみたいな音がする、っていう感じ方をしてたってところに、声の仕事をするという意識の芽生えみたいなものってあったんでしょうか?
若山:いやぁ……。そういう意識はまったく無かったですね。だって、僕にとっては自分の声っていうのは、声変わりしたときからコンプレックスの種だったから。人前で声出すのがイヤでね。それを何とか克服するために、高校2年の時に放送局(札幌NHK)に通い始めて、放送劇団に入って。それからが苦労の日々が続いたわけですよ(苦笑)。「お前の声はマイクにゃ乗らねぇ、マイクが壊れる」って言われて(笑)。ロクな役ももらえないしね。
松永:(笑)
若山:昔の常識で言えばね、二枚目ってのはテノールでしょ。バリトンやバスなんてのは、だいたい悪役か老け役、そのどっちかが相場なんですよ。ナレーションなんてのは論外。「お前みたいな声でナレーション出来るわけないだろ」ってアタマから言われてたからね。それが悔しくて。どうしたらマイクに乗る声ってのが出せるんだろう?って考えて。
松永:まだ御自分はお若いのに、いきなり可能性が限定されてしまって。
若山:そう。劇団で一番若かったのにね、年寄りの役ばっかりやらされてね(笑)。こりゃ何とかしなくちゃな、って思い始めて、結局到達したのが「声楽の勉強やろう」ってことだったんですよ。21、2歳の頃に、地元で名の通ってた学芸大学の先生のところに弟子入りして、3年くらいやったかな…。
松永:要するに、クラシックの発声とか、そういうことですよね。
若山:最初の日に呼吸法と発声練習を一時間くらいやったところで、もうイヤになってたけどね(笑)。でも始めたんだから、やんなきゃな、って思って。我々の年代ってのは、始めたことをすぐやめちゃうってことの出来ない年代なのよ(笑)。それだけでもって3年続けたんだ。
松永:最後は卒業ってかたちで止められたんですか?
若山:いや……、挫折(笑)。何で挫折したかと言うと、どう練習しても僕の声はバスに必要な高い音が出なかった。先生いわく、「まあ、バス用の譜面で駄目だったら、さらにそれを1音か2音下げて移調して歌うってことは出来なくもないんだけれど、オペラはそれじゃ出来ないんだよ(笑)」って言われてさ、そりゃそうだわな。……、オペラをやりたかったからね、あの頃。生意気にも。
セリフに大事なのは「間抜け」の「間」じゃないんだ
松永:オペラは実際に御覧になったりしてたんですか?
若山:札幌に来たものはだいたい観てましたけどね。あとは、東京出てきたときにいくつか観たかな。
札幌ってのは、昭和20年代の終わり頃は、ホントに文化からはずれたところでね。あの頃はひどい田舎町よ。芝居も何にも来ないんだもの。音楽会なんかも、みんな映画館でやるんだから。ホールなんか無いんだ。戦後に来たアーティストたちは、メニューイン、ハイフェッツ、アイザック・スターン、ギーゼキング、フルニエ…、みんな映画館で演ったんだ。N響でさえ、そうだったんだから。
松永:東京にいらっしゃったのは、JATPのときが初めてだったというお話ですけど、そのときはあくまで訪問っていうことだったんですよね。
若山:その2年後にもう一回来たのかな。昭和30年頃にね。そのときに文学座の「ハムレット」を観て。芥川比呂志さんがハムレットやったときの。これが何が凄かったかというとね、福田恆存という演出家がね、「ロンドンでハムレットを観ると2時間で終わる、日本で観ると何で3時間かかるんだ」って疑問から演出を引き受けて。それで、俳優さんたちにとにかく「速く喋って、速く喋って!」って言い続けたんだよ。今までの新劇のセリフってのが、いかに非現実的でトロトロしたものだったか、っていうことの証でもあったんだね。物凄いスピード感があって、すごいリアリティがあって感動した。そうだ、セリフってこれなんだ!って思ったのね。
もうひとつセリフに関して、そのとき感じたことがあって。寄席に行ったんですよ。あの頃の名人たちの舞台を生で見て、「うわ! これは福田さんの考えてた日本語のリアリティってものと共通するものがいくつもあるなぁ」って思ったんだよね。セリフのやりとりの「間」の問題とかね。「間」ってのは、間が開くのだけが「間」じゃ無えんだから。ピッタリくっついてても「間」は「間」なんだよ。それがいかに活きた「間」になるか、ってことが勝負なんだよ。それから落語のテープとか、放送するやつを一生懸命録音して「セリフって、これが本当なんだよな」って思うようになってきたんですよ。
だから、その後、札幌に帰ってからは、ひたすら「速く喋って、それを正確に表現する」、それだけ考えて稽古してた。こっちは意識して速く喋ってるつもりでも、聞いてる人には速くは感じられないんだよ。今まで、僕らがセリフってこういうもんだ、と勝手に考えていたものが、客観的に聞くと、もうトロいの。活きてない。
松永:つまり、それは「間」っていうよりも「テンポ」っていう感覚が大事なんだってことなのかもしれないですね。その「テンポ」が日本にはなかなか根付いていない、って言うか。「緩急」って言うか。
若山:まさにそうだね。今でもそうだけど、放送局の(ドラマの)ディレクターなんてね、学生の頃から演劇が好きで、自分のやりたいことをやるじゃないですか。何でもそうなんだけど、自分の頭の中で出来上がってるものっていうのは、過去のものしか無いわけだ。新劇とか歌舞伎とかさ。それしか頭に無いから、僕らにもそれを要求する。こっちは何にも知らないから、その通りやるじゃない。
速く喋る、っていうのは意図的にやるんじゃなくてさ、自分たちの日常生活を考えてみたら、それが普通のテンポなんだよね。それを芝居になった途端にね、何でこんなにゆっくりならなきゃいけないんだ、って。
松永:それと、若き日の若山さんを振り返る上では、かなり重要な要素に映画という存在もありますよね。
若山:はいはい、それはもう。芝居の勉強を始めてから、本当なら生の舞台をいくつも観なくちゃいけないんだけど、幸か不幸か、札幌には芝居は来てくれなかったから(笑)。
特に外国映画っていうのは、あの頃、すごい勉強になった。英語が判るわけでもないし、フランス語が判るわけでもないけれども、やっぱりセリフのニュアンスってのは判るじゃないですか。それに比べて、日本の映画ってのは、セリフがヘタクソで、何も勉強にならなかった。間抜けの「間」ばっかりだよ、それこそ(笑)。だから狂ったように洋画を観ましたね。
松永:その中でも特に「第三の男」というのが、とりわけ印象深いと。
若山:そうそうそうそう。もう、何回観たかな、あれ。まず、ロードショー行ったんだ、金も無いのに。
松永:生活的に楽でも無かったそうですが、どうしてわざわざ「第三の男」はお金の高いロードショーに行ったんでしょう?
若山:いや、これはねえ。その前の年に、同じキャロル・リード監督の「邪魔者は殺せ」っていう映画があったんですよ。それがすごく好きだったのね。で、彼がカンヌか何かで賞を獲ったときの作品が来る、っていうのを聞いて、これは絶対観なきゃイカン、って思って。お金貯めてロードショー行ったんだ。指定席なんてところにも生まれて始めて座ってさ(笑)。あれ、5円くらいだったかな、10円だったかな?とにかく、ロードショーでちゃんと観る、ってことは滅多にないことでね。
松永:始まってみたら、これは今まで観たのと全然違う映画かもしれないぞ、っていう感じで、映画の中に入っていかれた。
若山:ジョセフ・コットンがなかなか良かったですよ。そうそう、トレヴァー・ハワードもすごい好きだったね。でも、やっぱり何たって、オーソン・ウェルズが出てくる、あの最初のシーンですよ。
松永:オーソン・ウェルズという人のキャラクター自体に惹かれるものも結構あったということですが。
若山:……それから後、吹き替えの仕事するようになってからも、もし、日本語吹き替えで「第三の男」のオーソン・ウェルズが回ってきたらいいな、ってずっと思い続けた。でも、やらしてもらえなかったけど(笑)。
松永:え? そうなんですか。60年代に田宮二郎さん主演の映画(「複雑な彼」1966)で、若山さんがこの「第三の男」のオーソン・ウェルズのような謎めいた役柄で登場される、ということだそうですけど。
若山:いやいや。オーソン・ウェルズとは、かなり違うけどねえ(笑)。
TVの最初はみんな生放送で吹き替えしてた
松永:結局、最終的に東京にいらっしゃる結論を出されますよね。こっちにいらしてからは、割と順調に仕事をされたんですか?
若山:昭和32年の6月に出てきてね、その年の10月にはもうレギュラー持ってたから。ま、運も良かったんでしょう。
松永:何かそういうキッカケがあって、東京にいらっしゃったからですか?
若山:いやいや、全然。知り合いは東京に何人かいましたけどね。その知り合いの縁で、一番最初に主役もらったのがNHKラジオの、海外の名作をやってた海外名作劇場で。「ゴンチャーロフの日本渡航記」って一時間ドラマをやったんですよ。それが一人称のドラマで、一時間出ずっぱりで僕が喋ってるというもので。
松永:全国放送で、大抜擢ですよね。
若山:大抜擢でしょう。今は考えられないよ、そんなこと。まったく無名のやつをいきなり主役だなんて。
それで、ある程度認められたというところがあって。それから、ニッポン放送に売り込みに行って、「忘れ得ぬ人」っていう連続メロドラマの準主役っていうレギュラーをもらったんですよ。それが東京でのレギュラー番組の最初だった。これは北原三枝主演で。
松永:北原三枝さんと言うと…。
若山:石原裕次郎さんの奥さん。あの頃、まだ映画スターで、日活でバリバリ映画撮ってたな。
松永:じゃあ、若山さんの役は北原さんの恋人?
若山:いや、悪役(笑)。でも、そのとき東京新聞に初めて僕の名前が載ったんだ、「悪役の有望な新人現る」って(笑)。
あの頃、15分くらいの連続ラジオ・ドラマっていっぱいあったんですよ。それで「忘れ得ぬ人」で目付けられて、同じニッポン放送で3本くらい一日に掛け持ちしてましたね。
松永:声優として、ついにスタートを切ったというわけですね。
若山:まあ、その頃はラジオしかやるつもりは無かったけど。うんと年取ったら舞台でもやるか、ぐらいには思ってて、結局、やってないけど(笑)。怠け者だからね(笑)。
松永:TVの洋画劇場みたいな仕事っていうのは、いつ頃から始められたんですか?
若山:それはもう東京に出てきた次の年から。昭和33年の秋から、もうレギュラーでTVやりだしたんですよ。TBSで「ローン・レンジャー」ってのを。それと日本テレビで「モーガン警部」っていうシリーズを。それ以前にも、小さな役でいくつかTVの吹き替えの場数は踏んでたけれども、レギュラーはそれが初めてで。
「ローン・レンジャー」なんてのは、半年間、生で吹き替えやったんだよ。生放送だよ(笑)。
松永:想像つかないですよ(笑)。同時通訳でも大変なのに、生で吹き替えなんて。リハはやるんですよね。
若山:リハは前の日に4時間くらいかけてやるんだよね。本番までに3回くらいは映像を見るかな。それで本番はアナウンス・ブースみたいな狭ーいスペースにTVモニター置いてね、そこにマイク一本。今はヘッドホンなんてのをみんな付けるけれども、その頃はまだイヤホンだよ。しかも3つぐらいしかイヤホンが無いから。
松永:いっぱい出演者がいるときは、お互いに奪い合い(笑)。
若山:それがイヤでね。だから、「オレはイヤホンなんかいらね、全部、目で見てやる!」って言って、それでやっちゃった。そのために、随分アドリブの技術みたいなものは身に付いたわけ。
松永:洋画をよく御覧になってて、字幕じゃなくてニュアンスでセリフをつかんでた、っていうところも役に立ってたんでしょうね。
若山:当時、洋画を、特に喜劇を観に行くと、アメリカ人がいっぱいいたわけじゃない。それで、画面でギャグがあると、みんなすぐ笑うでしょ。何とかあいつらと一緒に笑ってみたい(笑)っていうのがあったんだよね。「笑い」っていうのは役者の中でも難しい技術なんだよ。日本人の場合ね、外人みたいな笑い方ってあんまりしないじゃない。その笑い方を何とか覚えてやりたい、それには喜劇映画を観に行って、外人たちの笑うあの笑い声を写し取ってやろう、って思ったわけだ。それで、スーパー・インポーズ(字幕の挿入)を見ないで、画面でやることと同時に一緒になって笑う、っていう、これも稽古だったんだ。そのうちに笑いもただ単に「ワハハ」じゃ無えな、って判ってきて。「笑い」でもって芝居ってすごく作れるなぁ、って思うようになった。いろんな種類の笑いを映画学校から盗んだ…。
一番影響されて、好きだったのはリチャード・ウィドマークだったんだ。彼がデビューしたのが「死の接吻」って映画で。ギャングの親分みたいな役で出てくるんだけど、これがすごくてね。怖くてね(笑)。笑い声がすごいんだよ。鼻で笑う、って言うかね。オレも絶対やってやろう、って、人のいないところで一生懸命稽古した(笑)。
松永:やっぱり、どっちかというと主役よりも、個性の光る脇役に目が行ってたんですね。
若山:自分もどうせ主役なんか出来ないと思ってたからね。こりゃしょうがないですよ(笑)。
なんで主役がどんどん来るようになったか、そのきっかけはね、TVの「ローン・レンジャー」も「モーガン警部」、みんな正義の味方だったんだ。そしたら、途端にラジオから来る役もみんないい役ばっかりになっちゃった(笑)。面白いもんでね。
松永:まだTVとラジオの力関係が逆で、ラジオの方が強かったってこともありますよね。でも、まだ勢力の弱かったTVから火が付いた。モーガン警部その人に、ラジオで悪役はやらせられないですもんね(笑)。
その後は「鬼警部アイアンサイド」も有名なんですが、僕ら世代(昭和43年生まれ)には、何と言っても007、ショーン・コネリーなんですよ。
若山:僕の前にショーン・コネリーやった人いるよ。知ってます?
松永:いえ、全然。
若山:日高悟朗って人がやったんです。
松永:やっぱり低い声で?
若山:全然低くない(笑)。ギャラが低い、っていう理由だけでやらせてたんだ、多分(笑)。
ジェームズ・ボンド・シリーズってのは当時、放映権を買うのがものすごく高かったんだよ。ところが、満を持してそれでオンエアしてみたら、何の反響も無かったんだよ。TBSの担当者が怒ってね、「作り直せ!」って。だから、僕のところに話が来たんだ。
松永:思い入れは人一倍という感じですか。
若山:うん。ショーン・コネリーは年を追うごとにどんどんいい役者になってきたしね。あの人は僕よりも5つくらい上かな。今でも、もちろん現役でしょ。
松永:実際にお会いになられたことは?
若山:無いんだよ。
松永:自分がその俳優さんの声を代表するような関係になった方と、現実に会う、という機会はいろいろとあったでしょう?
若山:それは随分ありましたよ。「モーガン警部」にも「アイアンサイド」にも会ったし。「保安官ワイアット・アープ」のヒュー・オブライエンってのとも会ったし、「バークにまかせろ」のジーン・バークにも会ったし。もちろん、リー・マーヴィンも。連中がね、みんな僕の声のことを「低い声」とは言わないんですよ。「深い声」って言ってくれるのが、すごいうれしくてね。“deep
voice”ってのは、いい言葉だよね(笑)。「スパイ大作戦」のピーター・グレイヴスなんてね、「僕の顔で若山さんの声があれば」なんてこと言うんだよね(笑)。
ロックを「感じられる」ようになりたくて毎晩、武道館へ
松永:ラジオとの関わりの中で、今に至るまで若山さんが続けてらっしゃるラジオDJの仕事について、お訊きしたいと思います。60年代の末頃に「パック・イン・ミュージック」を八木誠さんとやってらっしゃいますよね。「パック・イン〜」というと、野沢那智&白石冬美さんの“ナッチャコ”や福田一郎さんが有名なんですけど、水曜日の若山&八木コンビの放送がとても面白かった、という声が実はあるんですが。
若山:「パック・イン〜」以前にも、いくつかはやってましたけどね。一番、影響を受けたディレクターのひとりにTBSの平川清圀(きよくに)という方がいまして、この人が僕のことをいろいろと買ってくれてね、「本質的な意味でのディスクジョッキーとしての仕事を一緒にやりたい」っていう風に僕のことを見てくれてた人なんですよ。平川さんにしてみたら、僕を「パック・イン〜」に呼んでくれたというのは抜擢だったと思うんですけどね。
僕はポピュラー・ミュージックに関してはまったく門外漢だったし。ディスクジョッキーの仕事っていうのは、それまでは誰かが台本を書いてくれて、その台本を読めばいいんだ、って思ってたから。それが平川さんとの仕事に最初に入ったときに、「台本ください」って言ったら「台本はありません」って言うわけ(笑)。ええっ!?ってなっちゃって。「じゃあ、どうやってやるんですか?」って訊いたら、「これがあります」って曲目表だけ渡されて。「どうやってもかまいません。あなたはディスクジョッキーって言うくらいなんだから、音楽を自由に扱って、自由に喋ってくだされば結構です。音楽を自由に扱うその専門家は八木誠というのが付きます。あなたは八木誠の音楽に関する補足はもちろん無理にしても、番組全体の味付け、色付け、そういう仕事をあなたにやってもらいたい」って言われたわけ。
だけど、どうやったらいいのかまるで見当もつかない。だから、一応は資料なんかを調べて、データを持って行くわけですよ。そしたら「そういうの要りません。誰でも知ってるような話はしないでください。弦さんの感覚でその曲から感じたことを喋ってくれればいいし、八木ちゃんと2人の話の中から、今あなたが喋りたいと思ったことをそこで喋ってくれればそれでいいんです。余計な準備はしないでください」。
……手も足も出ない(笑)。
松永:(笑)
若山:だけどね、悔しいじゃないですか(笑)。「音楽は八木ちゃんが全部やります」だ? オレだって音楽やりたい、って思うわけ。やらしてもらうためには、僕だってポップスとかロックとかいうものを知らなきゃなんないでしょうが。
それで悔しいから、ロックを「判る」ってのはイヤな言葉だけど、「判る」んじゃなくて「感じられる」ようになるためには、やっぱり生を聴かなきゃ駄目だろう、と思ったわけだ。それから毎晩、武道館行ってたからね(笑)。
そのうちに何となく「こいつは有名だけどちっとも良くねえな」とか、「無名だけど、こいつは面白えな」みたいな感じ方が出来るようになってきたんですよ。で、そういうことが番組の中の喋りに少しずつ反映出来るようになってきてね、「じゃあ、弦さんのコーナーを作りましょう」って話になって(笑)。2時間の生のうちの15分くらいを僕にくれるようになったの。
松永:僕らが入手したプログラムだと、そのときは若山さんはニーナ・シモンやディオンヌ・ワーウィックをかけてらして。
若山:八木ちゃん、女性ヴォーカルが苦手だったからね。八木ちゃんに対抗するには女性ヴォーカルしかない、と思ってたから(笑)それで、そういうレコードをヤマハに買いに行って、必死になって聴いたんですよ。
中でもディオンヌ・ワーウィックが一番気にいったのね。それもね、僕は変なんですよ。僕が彼女を好きになったのは、彼女がバカラックと別れて『ソウルフル』ってLPを出したときなんだ。それまでのバカラックの生ぬるい音楽じゃなくて(笑)、すごいソウルフルなLPだったの。それを聴いてしびれたんですよ。それから、いろんな人に訊いてみたらね、「あんたは間違ってる」って言われて(笑)。バカラックを外してディオンヌ・ワーウィックがあるものか、みたいな言い方をするんだよね。でも、「オレ、バカラックなんか好きじゃないもん」って平川さんに言ったらね、「それでいいんです」って。「別に系統立てて聴く必要は何もない。あなたがいいと思ったもの、それがあなたにとって価値があるものなんだから。それをその通り喋ってくれればいいんです」って言われて、ようやく安心したんですよ。そんな風にして、僕のディスクジョッキー修行は進んでったんですよ。平川さんという人と出会えなかったら、おそらく今、DJなんかやってないでしょう。
松永:つまり「東京ダイヤル954」も「バックグラウンドミュージック」も無かったと。
若山:まあ、おそらく。あの人は僕にとって大師匠であり、大恩人なんですよ。
生で見て面白かったロック……、KISS!
大江田:「パック・イン・ミュージック」時代に、洋楽のシングルに日本語のタイトルを付ける、なんてことも頼まれてよくやってらした、ということですけど。
若山:あれは八木ちゃんと2人でやって、まあ、ほとんど八木ちゃんがやってたんだよ。ホセ・フェリシアーノの「雨のささやき」とかね、随分あるんだよ。
松永:八木さんとはすぐに意気投合されて?
若山:いやあ、意気投合もなにも。彼のあの感覚にはとても敵わないからねえ。イントロの長さとか全部、頭の中に入ってるからねえ。「なんで知ってるの?」って訊くと、「いや、勘ですよ」って(笑)。どうしても敵わないから、その頃からストップウォッチ持って、頭から何秒で歌に入るか勘定して、それでもって一生懸命、イントロの間に曲を紹介する練習やったんだけど、ありゃ八木ちゃんには敵わなかったな。
八木ちゃんはウルフマン・ジャックみたいに、ワンマンでプレイヤー手元に置いて、ヴォリュームの上げ下げしたりなんてスタイルをやりたかったんだよな。松宮(一彦)はちょっとそんな感じでやってたけど、まあ、あれは八木ちゃんのやってたことの真似なんだよな。あれだけ音楽を知り尽くしているというか、ああいうDJっていうのは彼しかいなかったんじゃないかなあ。
でも、あのイントロ紹介ってのは評判悪かったんだよ。
松永:そうなんですか?
若山:エアチェックの邪魔だから(笑)。曲は最初から曲として聴かせるべきだ、みたいな抗議の手紙が来るんだよ。
僕なんか八木ちゃんみたいにデータ的なことなんか出来ないから、歌詞の中身をイントロで喋ったらどうだろう、みたいなことはあの頃から考えてて。でも、やるとね、すぐ攻撃が(笑)。エアチェック出来ない、って(笑)。
松永:あと「デイヴ・クラーク・ファイヴを応援しよう」ってコーナーとか。
若山:ああ、ありました。「売れるまでやろう」ってね。
大江田:ショッキング・ブルーがそれで売れたんですよね。
若山:一回の番組の中で4回ぐらいかけてたんだもの。そういう思い切ったことをやらせてくれたのも平川さんならでは。他の人だったら絶対にやらせませんよ、そんなこと。
「パック・イン〜」は一年しかやらなかったんですよ。その後、日曜の昼間に「ホリデイ・イン・ポップス」ってのをやって、そこで随分いろんなことを勉強させてもらったんだね。それと並行して平川さんといろんな番組をやった。「JALミュージック・ツアー」とか。
大江田:文明堂のカステラ提供の、洋楽のライヴ収録番組もありましたよね。
若山:うん。「ハニーサウンド」ね。ウド・ユルゲンスとか、ムスタキとかね。
松永:生でライヴを御覧になった中で、印象に残っているアーティストっていますか?
若山:ロックの中で? そうだな……、へへへ(笑)、KISS
!
松永&大江田:(笑)
若山:それとね、ロックと言うより、ショウとして凄いなと思ったのは、ロスで見たポール・アンカ。それと同じ時に、ジョン・デンヴァーがディナー・ショウで、フランク・シナトラがレイト・ショウっていうのを見たんですよ。前の年にシナトラは初めて日本に来て、それも武道館で見たんだけど、あんなガチガチのシナトラじゃなくて、野球帽なんか被って、普通のスポーツ・シャツかなんか着て歌っちゃうんだけど、これが凄くて。リラックスしてて。
それで、やっぱり本物のライヴ見るにはアメリカだな、って思うようになって毎年通いだして、ブロードウェイ行って、ついにはヨーロッパ行くようになってきて、そこからはオペラだね。
まあ、いろんな節目ってのがあるんだけど、武道館やアメリカに足繁く通ってた頃っていうのは、何とかポピュラー・ミュージックを感じよう、っていう意味で平川さんとの戦いだったんだよね。
松永:大江田さんによると、若山さんはポロっと「リンダ・ロンシュタットの歌うデスペラードっていい曲なんだよな」って漏らしたりされて、すごいビックリする、っていうことなんですが。
若山:リンダ・ロンシュタットは好きだったね。ボビー・ジェントリーとかね。
大江田:武道館によくいらっしゃってた頃って、何年頃になるんですか?
若山:70年代前半でしょうね。僕が行くのを止めたのは、ディープ・パープルと、プロコル・ハルムのお別れコンサートの頃だったかな。あまりの音のデカさに耳がおかしくなっちゃって(笑)。これ以上通うと、オレは難聴になる、と思って止めた(笑)。あの頃から観客総立ちってのも始まったしね。
あ、そうだ。今でもすごく覚えてるのはね…、チェイス。……あれは良かった。武道館の6割くらいしか客は入ってなかったけどね。あれもトランペットですよ。幕が開くと、スポットがピンと当たって、真ん中にトランペットがぽこんと浮いてるんだ。それが物凄いハイノートで噴き出して、そこにドラムがドコドンドンドンドンって入ってきて、……カッコイイんだ(笑)。いい年こいて、そんなのばっかり聴いてたんだな、オレは。
大江田:名前の割につまんないな、と思われたのは?
若山:スタイリスティックス。それとCCR。
……チェイスは良かったぁ(笑)。スリードッグナイトも良かったね。あと悔しいのはね、アメリカ行ってたのにエルヴィスを聴き損なったことね。いつでも聴ける、って思ってたから。リトル・リチャードとチャック・ベリーのジョイント・コンサートなんかも見たよ。サンフランシスコのサークル・シアターっていうのがあって。真ん中にお盆みたいなステージがあって、出てきて演奏始めると、そのお盆が回るんですよ(笑)。
チャック・ベリーはね、あの映画がお気に入りなんだよ。
松永:「ヘイル・ヘイル・ロックンロール」?
若山:そうそうそう! あれは面白いねえ。キース・リチャーズがね。
チャック・ベリーのあのやり方ってのは面白いよね。自分ひとりでツアーに出掛けて、バックは全部地元のヤツらにやらせる、っていう。あれはまさに勝負だしね、JATPで力の限り吹きまくってたトランペッターたちとも通じるものあるもんね。
松永:声一本で勝負する若山さん、ギター一本のチャック・ベリー、JATPのトランペッターたち、それぞれ通じるものがありますよ。
若山:やっぱりね、勝負ってのはいいよね。僕が東京に来て、ラジオの仕事やりながら、毎日が他流試合だった。札幌にいるときは毎日同じ劇団で、同じやつらとやってるじゃないですか。でも東京だと、映画とか舞台とかで名前だけしか知らなかった人たちとラジオで共演出来る、ってことがとても面白くって。いつかひと泡吹かせてやろう、なんて思いながら(笑)。そればっかりだったね、考えてたのは。主役を食ってやろう、って。
大江田:最後にひとつお訊きしたいんですが。ラジオは好きですか?
若山:いやあ、ラジオは好きですよ。やっぱり、イメージの問題なんだね。TVみたいに具体的にパッと見て「あ、キレイだな」っていうのとは違って、音だけの世界でもって、その中に自分が浸りきれるようなイメージを持てるっていう世界だと思うんですよ。僕はラジオから出た人間だから余計、そう感じるんだろうけど。ラジオ・ドラマの面白さっていうのもそういうところかな、と思うんですよ。演じてる人間が誰であれ、そのドラマの中に聴く人を引き込める、っていうのは、やっぱり音だけの世界の力なんじゃないかしら。だから、ラジオでは先入観を持ってしまう人材の起用ってのは間違いだと僕は思う。新人を発掘すべきなんだろうね、ラジオのディレクターってのは。だって既成概念でもって聴かれちまったら、イメージの広げようがないもの。
松永:平川さんも、それを考えて音楽の新人として若山さんを起用されたんじゃないですかね。
若山:まあ、僕は吹き替えで結構名前も売れてたから、ネームヴァリューの問題もあったんでしょうけどね。でも、何より僕がディスクジョッキー番組をやりたい、って言い続けてたことをあの人は聞いててくれたんですよ。
札幌にいた頃にね、「ディスクとともに」っていうDJ番組がありまして。僕はものすごくその番組をやりたかった。いつかオレも洋楽を扱えるディスクジョッキーという仕事をやってみたい、と思い続けてて。
ラジオ・ドラマも好きだけども、そういう意味では、やれるものならクラシックのDJをやりたいね。今、ほとんど忘れられてるクラシックのポピュラー音楽的な側面、小品みたいなものってラジオの電波にほとんど乗る機会がないんだよ。あれはもったいない、と思うんだ。そういうクラシックの心のやすらぐ小品を自由にかけられて、自由に喋れるような音楽番組、やってみたいな、今でも。これだけBSだのCSだので電波が余ってるんだからさ(笑)、そういう番組のひとつくらいあってもいいんじゃないですかね(笑)。
(12月12日 赤坂TBS第2スタジオにて)
冒頭でも触れられていますが、若山弦蔵さんがDJをされていた番組「東京ダイヤル954」を僕も大好きでした。サラリーマンになり立ての頃、というともう25年近くも前のことですが、営業先を移動中の車の中で、毎日のように聞いていたものです。実に気の利いた選曲を楽しみにしていました。夕暮れ時、5時の時報のあとに、若山さんが毎日必ず「お疲れさま」と添えておられていたのも、とても印象的でした。
まさか若山さんと仕事をご一緒させていただくことになるとは想像だにしなかったのですが、こうしてじっくりとお話を聞く機会を持つことが出来たのもまた、大変に幸せなことです。
自分自身をよりどころに言葉を読む、寄るべきは自分だけ、という世界に長く生きてこられた若山の言葉の端はしに、生けるヒントがある、そんな風に読ませてもらいました。(大)
若山弦蔵さんは月刊「えいじれす」にて自分史を連載中です。ご興味のある方は、下記あてにお問い合わせ下さい。
「えいじれす」編集部
新宿区上落合2−10−6−307
電話5330−4741
yoshiko.i@jeans.ocn.ne.jp
| 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6 | 7
| 8 |
▲このページのTOP
▲Quarterly Magazine Hi-Fi index Page
|