|
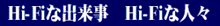
| 1
| 2
| 3
| 4
|
5
| 6
| 7
| 8
|
●亜米利加レコード買い付け旅日記 5
大江田信
1954年7月、エルヴィス・アーロン・プレスリーは、メンフィスのサン・レコードのプロデューサー、サム・フィリップスの手によってレコード・デビューをした。カントリー歌手の新星、というのが触れ込みだった。地元界隈の反響に自信を得たサムは、カントリー音楽の殿堂、天下のグランド・オール・オープリィにエルヴィスを出演させたいと、古くからの友人でオープリィのマネージャー、ジム・デニーに売り込んだ。ジムはエルヴィスの歌には感心しなかったけれども、サムの熱意に負け単発の出演を認めた。10月2日土曜日の夜、エルヴィスはグランド・オール・オープリィのステージに立ち、「ブルー・ムーン・オブ・ケンタッキー」を歌った。
このオープリィ出演は、彼の生い立ち物語のなかで、一つの惨めな失敗談として伝えられているという。「それは、エルヴィスが、グランド・オール・オープリィの舞台で不当にあしらわれたうえに、オープリィのマネージャー、ジム・デニーからは”トラックの運転手に戻るように”と言われて追い返され、失望のあまり帰りに車のなかで泣き続けたという、いささか感傷的な逸話である」(グレイト・カントリー・ソングス・エルヴィス・プレスリー 前田 糸旬子氏の「訳者あとがき」より BVCP−6001 BMGジャパン)。
ナッシュビルからメンフィスまでは、ハイウェイ40号線の一本道をひた走る。山の尾根を越えたかと思うと谷を下り、また山を上る。はるか延々と山道だ。ハイウェイには道路を照らす照明はなく、夜は車のヘッド・ライトだけを頼りに走ることになる。前後に車のライトが消えると、バック・ミラーは漆黒の闇を映し出す。周りには街もなく、人家の明かりは全くない。途方もなく広い広野に、独りぼっちになる。
ナッシュビルからメンフィス間は3時間27分の所要時間と、手元の最新版ドライビング・マップに記されている。夜道だともう少しかかるだろう。全米の高速道路の整備が完了したのが1956年とされていることからすれば、もしかするとプレスリー一行が走った当時の40号線は、まだ今のような充実した道路ではなかったかも知れない。1954年10月、今から45年前、傷心の19歳のエルヴィスを乗せたサムの黒い51年型キャデラックは、メンフィスまで、どのくらい時間をかけて走ったのだろう。
テネシー州の州都ナッシュビルは、人口50万人にも満たない小さな地方都市だ。保険、銀行、印刷が経済を支え、南部の「ウォール・ストリート」の異名を持つ。信者2600万人を擁するアメリカ最大のキリスト教宗派バプティスト協議会、それに続く信者1250万人を擁する第2の宗派、メソジスト教会がそれぞれ本拠地をかまえ、ギデオン聖書の本部もある。南部のハーヴァードと言われる1872年設立のヴァンダービルト大学を擁する南部随一の大学都市でもある。
そんなナッシュビルを世界の音楽ファンに有名にしているのは、なによりカントリー音楽である。ダウン・タウン周辺にはレコード会社のオフィス、スタジオ、音楽出版社、アーチスト・マネージメント・オフィス、ライヴハウス、楽器店などが所狭しと立ち並んでいる。なかでもナッシュビルの代名詞として有名なのが、毎週末にオープリィ・ランドにあるホールで行なわれるカントリー音楽番組のライヴ・ショー、グランド・オール・オープリィだ。このショーのために全米各地からナッシュビルに帰ってきたオール・スターがステージに勢ぞろいして、ヒット曲を披露しあう。4400人の聴衆の熱気で、会場は沸きに湧く。その模様はその昔はラジオで、現在はラジオとTVで全米に生中継されている。1925年に始まった番組は、もはや半世紀を越えるに至った。
一方でナッシュビルには、イーグルスやバーズなど70年代ロスアンジェルス生まれのカントリー・ロックと見紛うばかりのアーチストや、オルタナティブ風なアーチスト、シンガー・ソングライターなど、新たなカントリー音楽の展開も見られる。こちらはナッシュビル市内に10以上もあるライヴ・ハウスで、夜ごとホットな生演奏が繰り広げられている。そのうちのいくつかが、ピックアップされメジャー・レーベルよりCDとして発売される。こうしたカントリー音楽の新たな展開を聞くと、今なおカントリーが若い世代のクリエイティヴィティの受け皿になっている現実が見てとれる。
「ナッシュビル」、「カントリー」と来て、「テネシー・ワルツ」と並ぶと、出来の悪い三大噺のようだけれど、やっぱりここでは「テネシー・ワルツ」の歌詞を挙げておくことにしよう。ただしこの歌詞、正確に言えば「訳詞」ではない。
テネシーワルツ
ふたりであの時
聞いたテネシー・ワルツ
古いレコードの
ざらざら聞こえる
針の音まで
私は忘れない
あの小さな酒場の匂いさえ
あなたのシャツの色も
あの日が最後の別れの日だから
私は忘れない
真夏の昼下がり
人気のない街
私は歩いてた
どこかで誰かが
あのテネシーワルツ
口笛吹いていた
知らないまま通りすぎる
渇いた日差しのなか
あのとき聞こえたあのテネシー・ワルツ
私は忘れない
もう25年以上も前のこと、ふとラジオから聞こえた「テネシー・ワルツ」を手もとのメモ用紙に書き留めたものだ。歌っていたのは加藤登紀子で、恐らく彼女による歌詞だろう。もしかするとこの歌詞で録音されたレコードもあるのかも知れない。
もともとの英語詞の「テネシー・ワルツ」は、恋人とワルツを踊っていると古い友人が現われ、彼に紹介したら、その夜のうちに自分の恋人が奪い取られてしまった、こんな内容だ。今になって失った愛の深さを知り、二人が踊ったあの美しいテネシー・ワルツを思い出している。いささか荒唐無稽なストーリーである。
この英語版「テネシー・ワルツ」には、歌が心に引っ掛かる巧妙な仕掛けが用意されている。歌を聞き進むうちに、歌の登場人物たちが踊っていたのは、今耳にしている「テネシー・ワルツ」に違いないと、思わされる。そういうふうに演出されているのだ。古い例で恐縮だが、「星影のワルツ」「東京ブギウギ」手法の歌である。
この「仕掛け」を加藤登紀子は、歌の主人公たちが(おそらくSPの)「テネシー・ワルツ」を「聞いていた」シーンに置き換えている。原詞では主人公たちが踊ったテネシー・ワルツを、日本語詞では主人公たちに聞かせている。巧みな翻案だと思う。ラジオをぼんやり聞いていたはずが、思わずハッとして手元に書き留めたのは、そんな理由からだった。
英語の原詞には、もうひとつ仕掛けがある。繰り返し歌われる「Beautiful
Tennessee
Waltz」が、それだ。曲の最後のところで、このフレーズが歌われる。そうすると、やるせない悲しい物語が、「Beautiful」と「Tennessee」の言葉によって、いやされていく。歌の全体が、一つの響きを生む。この響きが強く心に残る。
ナッシュビルからハイウェイ40号線を南下して、メンフィスを訪ねた。メンフィスはミシシッピー川沿いの港町だ。1800年ごろには川を行き交う船の船頭たちが酒場や売春宿で酒を浴びるように飲み、暴れ回る宿場町だったという。やがて蒸気船、そして鉄道の中継地として発展し、綿や米、煙草などの南部の産物の売り買いや、奴隷売り買いの中心地になった。奴隷制度が解放されてからは、ディープ・サウスの黒人たちが、仕事を求めて北に向かうときに最初に落ち着いた所だともいう。もっと北のシカゴ、デトロイトなどの工業地帯に旅立つ者もいたが、メンフィスで仕事を得たものも多かった。貧しい白人たちにも仕事があった。プレスリー一家は、エルヴィスが高校に入学して間もなくミシシッピー州北部の都市、テュペロからメンフィスに(エルヴィスの回想によると)一文無しで引っ越してきた。テュペロには家族を養うだけの仕事が無いというのが理由だった。両親が仕事を得た一家は、住宅公社に住むことが許されている。
現在のメンフィスは人口68万人。そのうち約3分の1が黒人だ。街を歩いてみると、窓を締め切り大音量でヒップ・ホップを聞きながら運転している車と何台もすれ違う。交差点に止まる車の中で、両手を振り回して大声でヒップ・ホップを唄う黒人もいる。ナッシュビルとは比較にならないほど多くの黒人の姿が目に止まる。数ブロックごとに教会がある住宅街には、どことなく気品のある雰囲気が漂う。
CDショップでサン・スタジオやプレスリーのシングルを最初にオン・エアーしたラジオ局WHBQ、それにスタックス・スタジオ、ファリー・ルイスの住んでいた家とお墓など、メモリアルがどっさり書きこまれた手書きのコピー地図をもらう。サウス・セカンド・ストリートのメンフィス・ミュージック&ブルース・ミュージアムには、数多くの展示物に混ざってボ・ディドリーのギターやガス・キャノンのバンジョーが飾られているとある。そこにはエルヴィスのギターもある、と書かれた記事がコピーされている。コットン・ロウのビール・ストリートのクラブもいくつか記されている。夜更けまで熱気のこもった音楽が響く界隈だ。B.B.キングのクラブもビール・ストリートにある。
エルヴィスはメンフィスのラジオをよく聴き、ビール・ストリートに通って、黒人のR&Bを学んだという。そこには”黒い”フィーリングが熱く渦巻いていた。高校生のエルヴィスは、他の学生よりも髪を長く伸ばし、ポマードでなでつけ、すそをつぼんだズボンをはいた。これは当時のR&Bのミュージシャンの間で流行していたファッションで、白人社会からは異様なものと見られていたらしい。ファッションだけではない。エルヴィスの音楽も黒かった。エルヴィスがグランド・オール・オープリィのステージで唄ったカントリー音楽は、ナッシュビルの白人の聴衆にはさぞかし馴染めなかったに違いない。彼のオープリィ出演は、生涯を通してこの一度だけだった。エルヴィスの音楽は、保守的なナッシュビルでは受入れられなかった。
メンフィスで忘れられない失敗をやらかした。キーを掛けたままで、エンジンのかかったままの車のドアをロックしてしまったのだ。去年は何十年ぶりの寒い冬とかで、珍しいことに南部の街メンフィスにも雪が舞っていた。すぐに車に戻るつもりだったので、シャツにセーターを羽織っただけの薄着だった。本当に寒い。しょうがない、まずは電話を探しに歩く。レンタカーのオフィスにつなぎ、事情を説明し現在地を言う。するとオフィスまでキーを取りに来れば、無償でスペア・キーをくれるという。「オフィスはどこにありますか?」。「エアポートにオフィスがあります」。「ここからどれくらいかかりますか?」。「30分くらいだと思います」。往復で1時間か。阿部を残してエンジンのかかったままの車を放っておいて、一人で出かける訳にはいかない。「ほかに方法はありませんか?」ワラにもすがる思いで聞く。「鍵屋さんに合鍵を作ってもらって、現場まで行ってもらうことも出来ます。ただしお客様がJAFかAAAに加入されていなければ有料です。30分ほどで着くそうです」。それだ!有料でも構わない。時間の方が大切だ。「いくらですか?」「45ドルです」。「そ、それ、それをお願いします!」。 そういえばアメリカ人って、やたらといっぱい鍵を持っていた。さあディナーに行こうとボブがジーンズのポケットからキー・ホルダーを取り出したとき、そこには10個以上の鍵が付いていた。どれがどの鍵か判るんだろうかと思った。UPSのヨシエさんが、僕らに紹介しようと車にエンターテイメント・ブックを取りに席を立ったとき、まるまると太ったキー・ホルダーが彼女の手にあった。鍵の絵がデカデカと書かれたトラックが街を走っているのを、見かけたこともあった。もしかすると、あれが鍵屋だったのかもしれない。僕らみたいなのが客だったということか。どこかの街には、つい鍵を無くして家に入れなくなって、必死で鍵屋に電話をする一人暮らしの女の子だっていることだろう。
40分ほどして鍵屋の車がやって来た、と思う。腕時計も車のなかだった。あまりの寒さのあまり、一寸の遅刻にも僕は不機嫌だった。車のボディには24時間営業の広告文字が踊っていた。背が低くころころと太った親父が、車から降りて来る。口笛を吹きながら、車のドアに新品のキーを差し込む。ドアがあく。彼はにっと笑い、僕の方を向いた。45ドルを渡して、礼を言う。ドル紙幣を数え終わると、彼は言った。「あっ、それから税金、税金。あと3ドル40セントだ」。
(大江田信)
●
| 1
| 2
| 3
| 4
|
5
| 6
| 7
| 8
|
▲このページのTOP
▲Quarterly
Magazine Hi-Fi index Page

|