|
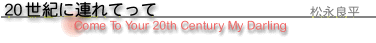
| 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8
| 9 |
第9回 トム・アルドリーノ 前編
「良い音楽と一緒に育つことができて、とてもラッキーだったよ」
確か、前回の椿さんのときにも同じようなことを言っていたような気がするけど、なんと、前回からまたしても2年振りの再開。
今回は、念願かなってぼくの大切な友人をお迎えした。トム・アルドリーノ。デビュー35年を今年で迎えたNRBQで、ドラマーの座を30年に渡って務める愛すべきアメリカ人だ。
破天荒でジャンル縦横無尽、それでいて、ぐっと泣かせるグッドタイム・ポップもお手の物。アメリカの良き音楽を構成するあらゆる要素をシェイクしてロックしてロールする。休むヒマもなく、毎年毎月毎週とライヴをやり続けるNRBQの35年の歴史は、はっきり言って、ただの35年じゃ済まされない。
トムは、そんなバンドをパワフルなドラマーとして支えてきた。そしてなおかつ、トムの凄みは、それだけにとどまらない。世界中の音楽マニアが束になっても叶わない、愛情優先で育まれた圧倒的な音楽意欲とレコード知識。この深みに、ぼくは知り合って以来、もうずっとハマりっぱなしなのだ。
| これまでも公私に渡っていろいろトムとは話をしてきたし、気の向くままにお互いに編集したカセットのやりとりも続けてきた。今年は、念願かなって、彼が高校生のときに録音していた、自宅地下室での多重録音テープを、ぼくの手でCD『ブレイン・ロック』(バンブルビー・レコード)として発売することもできた。 |
|
Tom Ardolino
「ブレイン・ロック/Unknown Brain」

|
言うまでもなく、彼の音楽への接し方、全身全霊でレコード文化を愛し尽くす生き方に、ぼくは相当の影響を受けている。今、ハイファイで人気商品になっているもののうちのいくつかはトムが教えてくれたものだ。さらには、彼が与えてくれたヒントのおかげで魅力がわかったことも数知れない。NRBQだって、トムが加入していなかったら、35年目の現在は、まるで違ったものになっていたような気がする。もっとも、そんなことを言っても、彼は謙遜して「ミャーオ」と、いつもの調子で恥ずかしそうに縮こまるだけなんだけど。
ぼくだって、トムに「良い音楽に気付かせてくれてありがとう」と面と向かって言うのは照れ臭い。だから、この場を借りて、話を訊くふりをして、それを言っておきたかった。そして、あわよくば知っておきたかった。トムが育った少年時代と、トムを育てた音楽と、アメリカの50年代、60年代のことを。それは正真正銘、アメリカで一番の音楽好きの少年が見た、雑誌や資料には書かれることのない音楽の真実なんじゃないかと思って。
今年、来日したNRBQのツアーをサポートするスタッフとして参加したぼくは、幸いにもトムと長い時間を取って話をすることができた。インタビューは全部で三回、東京、大阪、東京で行った。そのうちの第一回分を今回は掲載する。年齢にして0歳から9歳まで。それだけでもう一万五千字近いなんてね!
さらに、いつもなら、話をまとめるときにテープ起こしから編集をすることが前提になっているのだが、今回は、ほとんどそれをしていない。脱線も話の重複する部分を除けば、ほぼそのままだ。でも、この脱線の面白さは、編集に勝るはずだ。密かにそう確信している。
松永:じゃあ、始めよう。パート1。
トム:トプシィ、パート・ワン(低音で)
松永:コージー・コールだね。
トム:えへへ。
|
|
Cozy
Cole「Topsy」

●R&Bドラマー、コージー・コールのジャングル・インスト。超低音のMCでオープニングする。
|
松永:トムが生まれたのは、1955年だったよね。
トム:1月だね。55年に生まれてラッキーだったと思ってる。フィフティーズの音楽を記憶していられるギリギリのところだったから。2、3歳ぐらいから音楽についての記憶は始まってるよ。ぼくには兄貴がふたりいて、ふたりともシングル盤を買ってた。小さいときから、ぼくはレコードが大好きな子供だった。ビートルズがアメリカにやってきたときぼくは9歳だったけど、もう用意は出来てたってわけさ。良い音楽と一緒に育つことができて、とてもラッキーだった。本当にね。
松永:今回は、トムが生まれた年からNRBQに入る74年まで、順々に音楽の記憶を辿って行きたいと思ってる。長くなりそうだから、何回かに分けるかもしれない。だから、“パート1”なんだ。で、最初は55年からでいいのかな? それとも、生まれる前からにする?
トム:えへへ。ママのお腹の中にいたときは、ペリー・コモを聴いてたよ。まあ、それはどうだか(笑)。実際に覚えているのは、一番上の兄貴が持っていたシングル盤。ハリウッド・フレイムズの「Buzz
Buzz Buzz」だ。特に裏面が好きで、「Crazy」って曲。それから、コースターズ。「Searcin'」で、裏が「Youngblod」。あとは、デル・ヴァイキングスの「Come
Go With Me」。この3枚がぼくが覚えてる最初の3枚のレコードだ。
松永:57年か58年だね。
トム:ターンテーブルのそばに居たのをよく覚えてるよ。そのころ家にあったのは小さいやつでね。レコードのレーベルが回ってるのを見るのが好きだった。中でも一番好きだったのは“Dot”のレーベル! それから、レコード・プレイヤーの匂いを嗅ぐのも好きだった。今でも思い出せるよ。
松永:ふたりのお兄さんは、よくレコードを買っていたの?
トム:そんなにたくさんは持ってなかったよ。
松永:年はどれくらい違うの? |
|
Robin
Ward「Wonderful Summer」

●この曲はもうちょっと後、63年のヒットですが、Dotのデザインはこんなでしたということで。もちろん、トムはロビン・ワードの方も大ファン。 |
トム:一番上の兄貴とは15歳違うのかな。その下とでも13歳ぐらい違う。ぼくはすごく離れて生まれた末っ子だった。ふたりはロックンロールに夢中な年頃だったよ。
松永:それに、自分たちでレコードも買うことが出来る年だったってわけか。
トム:その通り。でも、子供向けのレコードもどういうわけか、家にはあった。どうして家にあったのかわからないんだけど、たぶん、両親が買ってくれたんだ。「Scuffy
The Tugboat」だ。今でもそのシングル盤は持ってるよ。
松永:物語レコード?
トム:歌だね。タグボートの歌。わかるかな? スカフィはおもちゃのタグボートなんだ。ふだんはバスタブの中にいるんだけど、そこから飛び出して大都会へと向かうんだ。大きな船とか、いろんなものに驚かされたりしながらね。それで、スカフィが「ぼくを家に戻してよ。やっぱりバスタブが一番だ」って歌うんだ(笑)。その他にも、何枚か子供向けのアルバムもあったと思う。
松永:58年のクリスマスは、トムにはかなり重要だと思うんだけど。
トム:58年のクリスマスと言えば「Chipmunk Song」さ! まったくその通り!
松永:最初はラジオで聴いたの?
トム:ラジオとテレビ両方だね。ぼくは毎日テレビで『American Bandstand』を見てたからね。その番組で、この曲が流れた。「子供たち、この曲に合わせて踊りましょう」だって。それってかなりヘンな話だよね(笑)。でも、クリスマスには、この曲はものすごいヒットになった。ぼくも大好きになったんだ。
松永:そして、これがトムが初めて自分で買ったシングル盤になった。
トム:自分で? まあ、確かにそうかもしれないけど、実際はおねだりして買ってもらったということだよね。「お願い、あのレコードが欲しいんだ。ぼくは『Chipmunk
Song』が欲しいんだ」って。
松永:ピクチャー・スリーヴは付いていたの?
トム:もちろん! 昔のチップマンクスの絵の方さ。
松永:ちょっとブキミな。
トム:そうそう。本物のシマリスみたいでね。最初の3枚のアルバムでは、リアルなチップマンクスが使われているよね。最初のチップマンクスのアルバムが出たときも、すぐに買ってもらったよ。
松永:チップマンクスのテレビ番組も見てた?
トム:『Alvin Show』だね。あれはもう少し後。60年代の初めだった。
|
|
David
Seville & The Chipmunks「Let's All Sing With The Chipmunks」

●リアル・チップマンクス時代のファン、実はハイファイ的にも多い。
|
松永:リアルなチップマンクスとかわいいチップマンクスのどっちが好きだった?
トム:うーん…(本気で考える)。あえて言えば、昔の方が好きだよ。すごくブキミだけど。つまり、ぼくはリアルな頃のアルヴィンのキャラクターが好きだからさ。まあ、みんなそうだと思うけど。
松永:あの頃は、チップマンクスのニセモノもいっぱい居たよね。
トム:いっぱい、いっぱい居たよ。グラスホッパーズとか。
松永:ニセモノも買ってみたりしたの?
トム:うん。グラスホッパーズは買ったよ。でも、アルバムの中で一曲だけ良いのがあったな。他のはちょっと聴けたもんじゃなかったけど。確か、「Puppet
Show」って曲だ。えへへ。
どうしてムシ声に反応しちゃうのか自分でもよくわからないんだ
松永:1959年。4歳になったね。
トム:4歳か…。この年もシングル盤を何枚か買ってるよ。58年とごっちゃになってるかもしれないけど。ディッキー・ドゥ&ドンツの「Click
Clack」、ビリー&リリーの「La Di da」…。この曲も『American Bandstand』で流れたんだ。それからシルエッツの「Get
A Job」(この曲はNRBQのライヴでのトムのレパートリー)…。この年はチップマンクスのファースト・アルバムも買った。確か、セカンド・アルバムも年末に出たんじゃなかったかな。
松永:資料では翌年の60年発売になってるけど。
トム:そう? でも確かに見たよ。チップマンクスのアルバムが出るなんて情報は子供だったから知るわけもなくてね。お店で偶然に見つけたんだ。ぼくは興奮しちゃってさ。あの光る銀紙ジャケット(チップマンクスの初期のアルバムは銀紙貼りの特製ジャケットだった)が、「どうかぼくを買ってちょーだい」って呼びかけてきたんだと思うよ。とにかく、チップマンクスのレコードはぼくの一番古くて長いフェイヴァリット・レコードなんだ。
松永:ムシ声でチップマンクスのライヴァルと言えば、大事なのを忘れてない?
トム:そうだ。59年の末には、ナッティ・スクワーレルズが登場した! これはぼくには大事件だったよ。「Uh!
Oh!」のシングルが出たときのこともよく覚えてる。どうしてムシ声にこんなに反応しちゃうのか自分でもわからないんだけど、あの曲もすぐに大好きになったよ。
松永:あれってヒットしたんだっけ?
トム:ヒットしたとも! トップ10さ。
松永:「Uh! Oh!」のヴィデオ・クリップを見たことがある、って以前に言ってなかったっけ? |
|
Nutty
Squirrels「Uh! Oh!」

Nutty Squirrels「Nutty Squirrels」

●上はシングル盤、下はファースト・アルバムのジャケット。
|
トム:ナッティ・スクワーレルズの5分間番組をテレビでやっていたっていうのは聞いたことがあるんだ。シリーズもので、90本もあるらしい。ぼくは信じてないけどね(笑)。曲が少ししかないのに、5分間番組が90本も作れるわけないよ。単なる噂だと思うんだ。でも、確かに実在していたっていう記事は読んだことがある。
松永:ナッティ・スクワーレルズを出したハノーヴァーってレーベルは、スティーヴ・アレンがやってたんだよね。
トム:そうなんだよ。彼はちょっと前に亡くなったね。
松永:だから、ナッティ・スクワーレルズのファースト・アルバムに関しては、マスター・テープは永遠に行方不明になってしまったというわけ。
トム:たぶんね。でも、ぼくはハル・ウィルナーにナッティ・スクワーレルズをリイシューしないか?ってずっと言い続けてるんだ。何とかしてテープを見つけたい。そして、リリースしたい。
松永:ハル・ウィルナーもナッティ・スクワーレルズのファンなの?
トム:彼もあのアルバムは大好きなんだ。そう言えば、こんなことがあったよ。翌年(60年)の1月。ぼくの誕生日が来た。いつも誕生日には両親に頼んでアルバムを一枚買ってもらうことにしてた。「ナッティ・スクワーレルズがアルバムを出してたら最高だな」なんてことを、家族のみんなによく言ったりしてたんだ。そしたら、ぼくのためにレコード屋さんに頼んで取り寄せてくれたんだ。びっくりしたよ。それからは、他のどのアルバムよりもナッティ・スクワーレルズのアルバムを聴いた。だから、あのアルバムの曲だったら隅から隅までわかる。今でもね。だって、そのときのアルバムを今でも持ってるんだから。ずいぶん、キズだらけになっちゃったけど(笑)
松永:あのファーストって、アメリカでも全然見つからないんだよね。
| トム:うん。たぶん、あんまり作らなかったんだよ。そうそう。ぼくとテリー(アダムス)でスティーヴ・アレンのライヴを見に行ったこともあるよ。二年くらい前かな。ぼくの街の近所にあるコメディ・クラブでショウをやったんだ。 |
|
Steve
Allen「Plays Hi-Fi Music For Influentials」

●こんな顔。
|
松永:テリーも行ったの?
トム:あいつも大ファンだからね。演奏は素晴らしかった。帰り際に、ぼくたちはお互いに持っていったアルバムにサインをもらった。ぼくは『Funny
Phone Calls』ってレコード、テリーはスティーヴ・アレンが音楽を付けたジャック・ケルアックのアルバム。それからそれから…、ショウの合間のことだ。それぞれ客席のテーブルにカードを置いてあってね。「スティーヴ・アレンに何かご質問は?」だって。それを集めて、あとでステージの上から彼が答えてくれるわけ。それならぼくの質問はこれしかない。「あなたはハノーヴァー・レコードを経営していたんですよね? ナッティ・スクワーレルズのことを覚えてますか?」(笑)
松永:彼は何て答えたの?
トム:ぼくの質問には答えなかった(笑)。残念。絶好のチャンスだったのに。えへへ。
松永:彼はすごくいろんな才能の持ち主だよね。
トム:ホント。おもしろい人だよ。
松永:テレビでも有名だったんでしょ?
トム:自分のテレビ・ショウを持ってた。深夜のトーク番組でね。
松永:ピアニストでもあり、アレンジャーでもあり、曲も書き…。
トム:まったくすごいよ。
松永:さらに、いくつかとんでもなくヘンなレコードも出してる。
トム:その通り。ヘンな人だよ。ハノーヴァー・レコードをやってたんだから。
リトル・リチャードのSPで従姉が踊り狂ってた
松永:そろそろ1960年に行こう。この年の誕生日にナッティ・スクワーレルズのアルバムを買ったわけだ。
トム:だけど、60年の他のことはちょっと頑張って思い出さないと(笑)。確か、チップマンクスのサード・アルバムが出た年だね。『Around
The World』だ。
松永:この頃はどんな子供だったのかな?
トム:楽しくやってたと思うよ。
松永:お兄さんたちはまだ学校に通ってたの?
トム:覚えてるのは、兄貴たちが“レコード・ホップ”に行くんで、パパが車に乗せて行ってたことだな。ぼくも一緒に連れてってもらったことがあるんだ。ついでに中にも入って、雰囲気を見てた。レコード・ホップっていうのは、ティーンエイジャーたちがレコードに合わせて踊るパーティーなんだ。レコードをかけるDJ役の子もいてね。ぼくは子供だったから少しの間しか居られなかったけど、それを見てるのは楽しかったな。
松永:映画とかでは、よくそういう場面は見るけどね。
トム:親戚の家に行ったこともよく覚えてる。従姉が三人いるんだ。あるとき、一番上の女の子が、地下室でパーティーをやってたんだ。彼女はティーンエイジャーだった。近所の友だちが集まって踊り狂ってた。そのときはSPでリトル・リチャードをかけてたね。そういう場面を実体験出来たってことはすごくラッキーだったと思ってるよ。感じる部分がいっぱいあった。
松永:幼稚園にはもう行ってた?
トム:キンダーガーデンに通ってたね。一年生のときはすごく楽しかった。でも、二年目と三年目のときは先生が厳しくてね…。
松永:友だちは出来た?
トム:何人かね。
松永:みんな音楽は好きだったのかな?
トム:それほどでもないよ。この頃の、近所の友だちで覚えてるのはふたりだけだな。ひとりは女の子で、ジャニスっていった。なぜ覚えてるかっていうと、彼女のお兄さんがドラムを叩いてたから。それを叩かせてもらったのが、ぼくの最初のドラム体験だったんだ。あともうひとりは、ブルースっていう男の子。三人でよく遊んでたけど、何をしてたのかは思い出せないな。でも、ジャニスで思い出すのは、なんと彼女もチップマンクスのファースト・アルバムを持っていたことなんだよ。彼女が持っていたのはモノラル盤だった。盤の色は黒。ぼくの持ってるのはステレオ盤で、色は赤。なんでかわからないんだけど、ぼくは黒いのが欲しくなった。だから、彼女のとトレードしたんだよ。でも、それが両親にバレちゃって、結局、元の鞘に収まることになったんだ。でもこれって、ヘンな思い出だよねえ(笑)。
松永:なんでモノラル盤を欲しいと思ったんだろ?
トム:違う違う。ステレオとかモノラルのことはまだわかってなかった。赤いレコードがイヤだったんだろうなあ。たぶん、赤いのに飽きてたんだ(笑)。
松永:(笑)。
トム:あとは、とにかくテレビだね。ほとんどカートゥーン(テレビアニメ)ばっかり。
松永:どんなのが好きだった?
トム:ワーナー・ブラザーズの古いやつ。
松永:「バッグス・バニー」とか?
トム:なるべく古い方ね。そのうちハンナ・バーベラのカートゥーンもテレビ放映が始まった。ハンナ・バーベラの方は新作でね。「珍犬ハックル」「チュースケとチュータ」「クマゴロー」とか好きだったな。
松永:まだ家のテレビは白黒だった?
トム:うん。64年までね。65年にカラーテレビになった。でも、その頃でもまだ結構白黒の番組は多かったよ。半々くらい。
松永:ふーん。
トム:でも、やっぱりカラーは素敵なものだったよ!
63年のヒット曲からは最高のフィーリングがあふれてる
松永:じゃあ61年。6歳だ。
トム:うーん。ほとんど60年と同じだな…。レコードがどんどん好きになってはきてたけど、まだそんなにたくさん買えないんだもの。
松永:さっきも言ってたチップマンクスのテレビ番組『Alvin Show』がこの年に始まってるよ。
トム:そうそう、そうだったね! 土曜の朝だ。でも、スタートしたときは夜だった記憶があるな。毎週一回の放送で、夜7時だったか7時半だったか。そのあと朝になったんだと思う。
松永:あの番組の中で、デヴィッド・セヴィルが別のキャラクターのミニ番組をやってたでしょ。
トム:「Clyde
Cruchcup」だろ。あれ、ヘンだったよねえ。
松永:あと、『Alvin Show』では、チップマンクスのレコードそのままを使って、ストーリーと音楽が作られているんだよね。
トム:そうなんだよ。よく見てた。大好きだったし。チップマンクスはCMもやってた。「ジェロ」(ゼリー菓子)とか「ソーキー」(お風呂用おもちゃ)とか。
松永:あの番組がきっかけでチップマンクスのキャラはかわいくなったんだもんね。他には何か思い出すことはある?
トム:(しばし考え込む)……、61年は『Alvin
Show』以外、思いつかないな…。
松永:音楽シーンはちょっと退屈な感じになってきてたのかもね。
トム:そうかもね。それでも、それまでに買いたかったのに買えずにいたシングル盤とかを買ったりしてたと思うんだ。うーん。そういう意味だと、62年も、あんまり面白い年とは言えないね。61年よりは少しマシかもしれないけど。
松永:そう?
トム:そう思うよ。でも、その次の63年は大好きだな。あの年のサウンドはみんな好き。一年中楽しく過ごしてたはずだよ。63年のヒット曲からは最高のフィーリングがあふれてる。うまく言えないけど、そうなんだ。
松永:63年は、坂本九の「スキヤキ(上を向いて歩こう)」が大ヒットした年なんだよね。
トム:そうとも! あれは素敵な夏だったよ。
松永:あの曲のこと、どう思った?
トム:だって、ぼくはあれをすぐに買ったんだよ! ホントさ。B面もよく聴いたよ。 |
|
Kyu
Sakamoto「Sukiyaki And Other Japanese Hits」

●このジャケでの復刻希望。選曲もバッチシ。
|
松永:あの曲のどこがそんなに気に入ったの? 声? 曲?
トム:うん。メロディ、そして声だね。なぜか、あのとき、アメリカ中の人にあの曲の魅力が届いたんだよ。とんでもない大ヒットだった。あの曲に「スキヤキ」なんてタイトルを付けるなんて、バカげてるよ。ひどい。まあ、ひどいは言い過ぎだけど、バカげてるのはホントさ。侮辱的だよ。
松永:日本語での意味は知ってるでしょ?
トム:もちろん。悲しみがあるよね。そして美しい。「上を向いて歩こう」の意味がわかったときは、胸を打たれたよ。だからこそ、なんであの曲が「スキヤキ」にならなくちゃいけないのさ、って思ってるわけ。まったくアメリカ人のバカさって言ったら(笑)
松永:アメリカではアルバムも一枚出たよね。
トム:ダイナマイトの箱の上に座ってるやつね、煙草持って(笑)。続いて出たシングルが「China
Nights(支那の夜)」。もちろん、それも買った。
松永:もう自分のお小遣いで買ってたの?
トム:そうだね。63年がぼくにとって大きいのは、それまでよりもずっとたくさんシングル盤を買えるようになったからなんだ。毎週レコード屋さんに通って買ってた。土曜になるとダウンタウンに行く。一軒、街で一番大きなレコード屋さんがあって、そこに10セントのシングル盤コーナーがあるんだ。宣伝用にわざと安く売っているシングルさ。ヒットさせたいと思うから、最初は一枚10セントで売りさばくわけ。売れてきたら、25セント。もっと売れてきたら39セントにする(笑)。その頃、レギュラー盤は77セントだった。
松永:当然、トムは10セント狙いだ。
トム:10セントばっかり。でもそうやってたくさん買うことで、レコードのレーベルについても、だんだんわかってきた。
松永:どのレーベルが好きだった?
トム:まだあんまり詳しくはなかったけどね。“Dot”の柄はずっと好きだったけど。一個当たりがあると、そのレーベルの他のシングルにもトライしてた。運試しだよ。
松永:63年だったら、ビーチ・ボーイズは聴いてたんじゃないの?
トム:そうだね。「Don't
Worry Baby」とかは聴いてたと思うな。でも、あの年の夏で思い出すのは、別のこと。近所に、プール+遊園地みたいな場所があって。大して大きくないんだけど、浜辺風になってるんだ。「ジョイランド」って名前だったな。
松永:「ジョイランド」?
トム:ジュークボックスがあってね、子供たちはそこに群がってヒット曲をかけてたよ。エセックスの「Easier
Said Than Done」を何回もかけたと思う。あのときのことを思い出すと、すごく楽しい。とにかく、63年には音楽はすごく良くなってきてたんだ。
松永:フィレスのシングルは好きだった?
トム:おお、そうだ! ロネッツの「Be
My Baby」の話をしなくちゃ! あの曲を聴くと、家で飼ってた猫のことを思い出すよ。名前はタイガー。ぼくが覚えてる一番最初に飼った猫。タイガーはぼくが学校に行くまで、うしろを付いてくるんだぜ。それから、また家まで一匹で帰ってゆくんだ。すごくかしこい猫だった。
松永:ホントに?
トム:ところが、実はタイガーはメス猫でね、突然、軒下で三匹の子猫を産んじゃったんだよ。それで、ある日、ぼくが家に帰ったら、タイガーがいなくなってた。両親が、子猫と一緒にどこかへやっちゃったんだよ。どうしてそんなことしたんだろう。ぼくは家を飛び出した。悲しくてね。そして、その日に「Be
My Baby」を買ったんだ。だから今でも忘れられない。タイガー。すごくいい猫だったのに。その週は、ずっと「Be My Baby」を聴き続けた。それが63年に起こった一番大きなことさ。
松永:……なんて言っていいか。
トム:まったくね…。(気を取り直すように)あの頃は夏休みには毎年海に出かけてたな。行き先はロード・アイランドの東の浜。コテージを借りて、一週間ぐらいゆっくり過ごす。まあ、どこの家でもよくやってることだけど。でも、ぼくが覚えてるのは、ロード・アイランドにはコミック・ブックを売ってる良い店があったってことだけ(笑)。とくに一軒、最高の店があってね。コミックばっかり読んでたな。「Archie」とか。
松永:ビーチには行かないの?
トム:行かされるんだけどさ、かたちだけ。でもほら、ぼくはコミック屋に行きたいし、行かないわけにはいかないんだからね。
松永:他人事とは思えないな(笑)。
トム:64年の夏に行ったときは、ぼくの従姉も一緒だった。親戚一家と近くのコテージを借りていた。彼女はヴィージェイから出てたビートルズのアルバムを持ってたんだ! ぼくはヴィージェイのは持ってなかった。キャピトルから出たのは持ってたけど。ヴィージェイのアルバムが、アメリカでは一番最初に出たやつなんだ。あそこのコテージにはレコード・プレイヤーもあったから、ぼくはもうそれを何回も何回もかけ続けた。でも「Ask
Me Why」だけは好きになれなかったんで、あの曲だけ飛ばしてかけてた。それは64年の夏の話だけど。
ビートルズがすべてだった
松永:64年にはすべてが変わった。つまりビートルズだったんだって。バンキー&ジェイクのジェイク(ジェイコブス)に話を聞いたときも、そう言ってた。ジェイクやジョン・セバスチャン、グリニッチ・ヴィレッジにいた若者たちはそれまでみんな熱心にブルースやフォークを追求していたのに、ビートルズが現れて、みんなぶっ飛ばされてしまった。そして「よし、おれたちも自分たちの曲を書こう!」って思ったんだって。それがラヴィン・スプーンフルであり、グッドタイム・ミュージックの始まりだったらしいんだ。
トム:ビートルズがすべてを変えたんだよ。あんなに大きなものはそれまでには無かった。実際に、ぼくが初めてビートルズのシングルを買ったのは、アメリカで最初に出たシングル「I
Wanna Hold Your Hand」。あれを買ったのはクリスマスの二日後だって、ぼくはずっと言い張ってるんだ。1963年12月27日。わかるかい? どの資料を見ても、あのシングルは64年1月1日発売だって書いてある。でも、ぼくは確かにクリスマスの二日後にあれを買った。人に話すと、おかしなやつ扱いされるんだけど、それは事実なんだ。あのとき、ぼく以外にもふたり、ちょっと年上の男の子たちがいて、「見ろよ、もう出てるぜ」とか言ってたのを覚えてるから。ピクチャー・スリーヴを指さしてね。誓ってもいいよ。
松永:ということは、もちろん64年の誕生日には…。
トム:キャピトルから出たビートルズのファースト・アルバムを買ってもらったよ。
松永:ビートルズのアルバムって、イギリスのオリジナルだと13曲入ってるじゃない。だけど、アメリカ盤はいつもちょっと少ない。
トム:11曲のときもあったよ。でも、最初はそんなこと知らなかった。でも、気が付いたのは、たぶん、早い部類だったんじゃないかな。気が付いちゃったら、もう大変だ。欲しくなっちゃって、どうしようもない(笑)。その前から、イギリスのオリジナル・シングルが欲しいなとは、ずっと思って探してた。イギリス盤のパーロフォンのレーベルが好きでね。
松永:アメリカでイギリスからの輸入盤を買うのは大変だよね。今だってそうだもの。
トム:まったくね。とくにぼくの地元なんかじゃね。輸入盤のことなんか気にかけてるやつなんか誰もいなかったよ。ホリーズの「Bus
Stop」がヒットしたのは、この頃だったっけ?
松永:65年じゃない?
トム:そうだったかな? まあいいや、どういうわけか、あれはイギリス盤のパーロフォン・レーベルで買うことが出来たんだ。そのときは舞い上がっちゃったよ。やった! イギリス盤が買えた!って。しかもビートルズと同じパーロフォンじゃないか。それはぼくにとってはとても特別なことだったんだ。だから、あれは今でも持ってる。
松永:64年にアメリカでヒットしたイギリスのグループは、他にはジェリー&ザ・ペースメイカーズとか…。
トム:いたいた。フレディ&ザ・ドリーマーズもね。フレディ大好き! イギリスのビート・グループはみんな好きだったよ。初期のゾンビーズにもすごく好きな曲があるし。でも、やっぱり一番はビートルズだ。ビートルズのグッズは何でも買った。ビートルズ・カードとか。
松永:ビートルズ・カード?
トム:ベースボール・カードみたいなものさ。
松永:『ブレイン・ロック』のライナー・ノーツに使った、きみの子供の頃の写真で、壁に4人の写真が貼ってあったよね。
トム:ビートルズはぼくのすべてだったからね。
松永:最初に誰が好きになったの?
トム:誰かひとり、ってこと? 特別なひとりなんかいないよ。ぼくは“ビートルズ”が好きだったんだ。
松永:ビートルズこそすべて、か。
トム:しばらくしたら、業界でも大戦争が勃発したよ。ビートルズ対デイヴ・クラーク・ファイヴだ。ローリング・ストーンズはまだそんなにビッグじゃなかった。デイヴ・クラーク・ファイヴこそがライバルだったんだ。ビッグ・No.2だよ。しばらくの間、ぼくはデイヴ・クラーク・ファイヴが大嫌いだった(笑)。ビートルズ絶対支持! すごく子供だったからねえ(笑)。
松永:デイヴ・クラーク・ファイヴはアメリカではエピックと契約してたから、レコード会社同士で張り合っていたんだろうね。
トム:それはあるだろうね。雑誌でもよく対決が煽られてたし。雑誌もたくさん買ってたなあ。ティーン・マガジンだったら何でもね。どの雑誌を見てもビートルズだらけ。全部取っておいたんだけどね。ママが捨てちゃって。
松永:アメリカの音楽はどうだったの? モータウンとか。
トム:モータウンは流行り始めたところじゃなかったかな。あとは、フォー・シーズンス、ビーチ・ボーイズ…。
松永:バート・バカラックの仕事とかは?
トム:うーん。ディオンヌ・ワーウィックの「Anyone
With A Heart」とか、ヒットし始めた頃だったかなあ。もちろん最高だったよ。でも、そう思えたのは、65年だったかもしれない。64年で確実なのはダイアン・リネイ。彼女は大好きだった。
松永:ガール・グループのヒット曲もあったと思うんだけど。
トム:フィル・スペクターがまだまだ頑張っていたよね。64年はとにかくレコードとビートルズで頭がいっぱいになった年なんだ。
松永:ビートルズのコンサートには行けなかったんだよね。
トム:まだ子供すぎたんだ。両親に頼み込んだことはあるよ。でも、「ダメ」。ひとことで終わり。あきらめずに何度でもトライしたけどね。ボストンでやったコンサートが一番のニアミスだったな。でも、行けなかった分、スクラップ・ブック作りに精を出したよ。雑誌や新聞からビートルズに関することなら何でも切り抜いた。今でも持ってるよ。誰かがビートルズについて言ったこととか、『エド・サリヴァン・ショウ』に出演した翌日の評とか。「あいつら最悪だ」とか、書いてある記事なんだけど(笑)。
松永:5年前にニューヨークのフリー・マーケットで、ビートルズへのラブレターだけを集めた60年代の本を見つけたことがあるよ。買おうと思って値段を訊いたら「200ドル」だって!
トム:へえ! それは現物を綴じたもの? それとも印刷?
松永:いやいや、印刷だよ。でも、手書きのがあったり、タイプライターで打ったのがあったり、すごく面白そうだったんだけどね。
トム:なんでそんなに高いの?
松永:レアなんだってさ。
トム:ふうん。覚えとこ。『A
Hard Day's Night』の映画が公開されたのが夏だったかな。あれも大事件だった。最初は、両親と一緒にドライヴイン・シアターで見たんだ。ふたりはあの映画は気に入らなかったけど、ぼくはひとりで興奮してた。その次に見たのは、友だちの家。有料チャンネルで放映されたんだ。まだペイパービューなんて全然知られてない頃で、ぼくの近所であれを見られた家はあそこだけだった。それから二番館でやるとき、また見に行った。
松永:大変だね。
トム:ラジオから「A
Hard Day's Night」が流れてきた瞬間にもうやられちゃったんだ。まだ映画を見る前でさあ。「今度上映されるビートルズの映画の曲です、ジャーン」。とにかく、ビートルズのやることすべてに打ちのめされてた。この年のクリスマスには、アメリカでは『Beatles
'65』が発売された。イギリス盤で言うと『Beatles For Sale』に近い内容だけど、11曲しか入ってない。でも、それをねだって、クリスマス・プレゼントにしてもらった。
松永:ドラムはまだ叩き始めてないの?
トム:そろそろだね。鍋とフライパンで始めるんだけど。あのときに『Beatles
'65』が出てなかったら、クリスマスにはドラムを買ってもらってたに違いないけどね。ビートルズのおかげでちょっと遅れたね(笑)
あの頃はみんなクレイジーなことが大好きだったんだ
松永:『エド・サリヴァン・ショウ』は当然見てたでしょ?
トム:毎週見てたよ。あの番組、必ず一組はビート・バンドが出てきたから。とくにビートルズが出演する週は絶対に見逃さない。でもさ、番組全部を見続けるのはしんどかったな(笑)。
松永:ヴォードヴィルとか、つまんないポップ・シンガーとかも一緒だもんね。
トム:今はそれも面白いんだけどね。中にはヘンな出し物もあったもの。だけど、まだ子供だったから、お目当てが出てくるまでが辛くて。
松永:エド・サリヴァン自身も、ちょっとヘンなキャラというか。
トム:すごくヘンだよ。
松永:全然笑わないし。
トム:ねえ! ストーン・フェイス(石みたいな顔)だよ。すごく変わってる。そう言えば、彼がしゃべってるレコードを二枚持ってるよ。一枚はカービー・ストーン・フォー。その中に司会でエド・サリヴァンが出てくる。もう一枚のは、66年くらいに出たやつだと思うんだけど、エド・サリヴァンにちなんだダンスが発明されてね。”サリー・ガリー”っていうやつで、エド・サリヴァンみたいなポーズで踊るんだ(笑)
松永:あの肩をしゃっちょこばらせた感じで(笑)
トム:それで、レコードの中でエド・サリヴァンがこのダンスについてしゃべってる。コロンビアから出てた。本人もテレビで踊ってたんじゃなかったっけ?
松永:彼は本当はそういうヘンなアイデアが好きだったんじゃないかな?
トム:そう思うよ。いいことだよ。あの頃は、みんなそういうクレイジーなことが大好きだったんだ。
松永:『エド・サリヴァン・ショウ』のコンプリートDVDがあってもいいくらいだよね。
トム:ホントにね。PBS(パブリック・チャンネル)では今も再放送が続いてるけど、あれはいろんなシーンを30分に編集したものなんだよね。本当は『エド・サリヴァン・ショウ』は一時間番組だったから。ビートルズの出演分がCM込みの完全復刻でDVD化されたのは、すごく嬉しかったよ。でも、みんながそう思ってるわけじゃないんだろうね。とくにアメリカ人はそう。気にしちゃいないんだ。
松永:そうとも言えないよ。少ないかもしれないけど、若いアメリカ人の中にも面白いセンスの持ち主が出てきてる。ハイファイのお客さんにも、ひとりすごく有望な女の子がいるんだ。彼女はシンシナティ出身で、大学でなんと“フランク・ザッパ学”を受講した。今は小学校の英語の先生をやるために日本に来てるんだけどね。彼女がお店に来たときに、ジョン・サイモンがメチャクチャな編集をしたマーシャル・マクルーハンの『Medium
Is The Massage』を聴かせたら、すごく面白がってた。彼女はあのレコードのことは知らなかったけど、聴いてすぐに「これは他とは違う!」って気が付いて喜んでくれた。だからって、彼女はすごいヘンな格好してたり、ヘンなこと言ったりってわけじゃない。普通に暮らしていて、だけど、ありきたりじゃない音楽に触れたいと思ってるのさ。
トム:いいことだね。アメリカ人の若い女の子がそういう風に感じることができるなんて素晴らしいと思う。珍しいよ。
松永:彼女はマザーズの『Cruising With Ruben
& the Jets』のオリジナルLPをずっと探してたんだよね。それをハイファイで見つけたのが仲良くなるきっかけだったんだ。
|
|
Frank
Zappa & The Mothers Of Invention「Cruising With Ruben & The
Jets」

●愛ある偽ドゥーワップ。最高です。
|
トム:ああそう! そうなんだ! あのアルバムって、CDだと気持ち悪いもんねえ。あのオリジナル・ヴァージョンってCDになったことないよね?
松永:その通りなんだ。ベースとドラムが80年代風のやつに差し替えになってるんだよ。
トム:サイアク! 『We're
Only In It For The Money』も最初それと同じ差し替えで出たけど、あっちは元通りになって出し直したよね。でも、『Ruben
& The Jets』は悪いヴァージョンのままなんだ。
松永:オリジナルのマスター・テープが紛失したからなんだってね。
トム:ぼくは信じないよ。なにか言えない理由があるはずさ。えへへ。
松永:『Ruben & The Jets』は、ぼくも大好きなアルバムなんだ。
トム:ぼくもだよ。
松永:彼女の話に戻るけど、彼女は「ほとんどのアメリカ人はわたしみたいな趣味じゃない」って言う。
トム:そうだろうね。彼女が素敵過ぎるんだよ。
松永:彼女はトムの『ブレイン・ロック』も買ったよ。
トム:オー・ノー(笑)。ぼくを嫌いになるんじゃない?
松永:そんなことないよ。気に入ってたよ。
トム:そう? それならいいけど。
松永:オーケー。じゃあ、パート・ワンはこの辺にしよう。次は65年からスタートだ。
トム:エンド・オブ・パート・ワン。インターミッション(低い声で)。
[続きは次回]
| 1 | 2
| 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8
| 9 |
▲このページのTOP
▲Quarterly
Magazine Hi-Fi index Page
|








