|
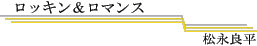
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
10 |
第10回 ハイファイ・スノック・アップタウン
わたしは道を急いでいた。代わり映えのしない田舎道を走っていたわたしのワゴンは、ようやくハイウェイに入った。ダウンタウンが見えてきた。あのビル街を抜けて、川を超えたら
あの店までもうすぐだ。
いつもはCDの配達と集金は妻に頼んでいるのだが、今日は隣のギター屋にも用事があった。頼んでおいた修理が終わっているはずだ。
駐車場に車を停め、ギター屋を覗いた。おやじが、ダルシマーをご婦人とその娘さんに見せている。最近、あの手の若い連中が、こういう店にまた増えてきた。
おやじはわたしを見て、「出来てるよ」という顔をした。窓越しにわたしも「わかった、後で寄るよ」と目配せをする。もっとも、わたしはそのつもりだが、あっちにはそう伝わってるかどうか。だが、そろそろ長いつきあいになるおやじは、わたしのあんまり動きのない表情から、それを読みとってくれたようだ。
だから、今日は先に隣でCDの話を済ませよう。隣のレコード屋は、今日もささやかな賑わいを見せていた。
この街で一番大きなこの店は一風変わっている。まるで市場みたいだ。店主の大男は、自分の店をテーブルごとに区切って、ディーラーたちに貸し出しているのだ。そうすることで、ディーラーたちのライヴァル意識が燃えるのか、商品は常にリフレッシュされるのだというようなことをやつは言っていた。
「よお」
店主の好きなオールディーズが流れている。わたしはあんまりこの手は興味がないが、こいつの趣味は悪くないことはよくわかる。以前に、北の街のレコード屋に頼まれて、壁に大きな絵を描きに行ったことがあるんだが、一週間も若い連中のかけるテクノを聴かされて、ひどくへきえきしたのを思い出す。だけど、まったく、あれは楽しい一週間だった。だいたい、テクノなんか聴く連中が、どうしてわたしの絵に興味を持つんだか、不思議なもんだ。
「売れてるかい?」とわたしは訊いた。
「まあまあだ」と店主は答えた。「おっと、それって、うちの店のことかい? それとも、あんたのCDのことかい?」
「どっちもだよ」わたしは笑った。笑った、と思ってもらえるかはわからない。でもまあ、こいつもそろそろわたしのそういうタチをわかってくれてるみたいだが。
「ああ、そうだ」店主は、ふと何か思い出したのか、店の隅に声をかけた。「おい、ちょっと」
ひとりの大柄な中年が顔を上げた。白髪交じりで眼鏡をかけている。東洋人だった。
男はひょこひょこと店主のもとにやってきた。そして、ふたりで何やら話している。やや間があった。男はわたしを見て、心底驚いた顔をしていた。ごくたまにあることなんだが、今でもこういうときにわたしはどういう顔をしたらいいのかわからない。
やがて男は駆け足でもといた方へと向かった。すると、そこにはもうひとり、少し若めの東洋人がいた。小さくて短い叫び声があがった。
店主がわたしを見てにやにやと笑った。「あいつら、あんたのファンなんだよ」
「ファンだって?」
「日本じゃ、あんたのレコードは高いらしいよ。よく連中はあんたのレコードを探してる、って言ってたから」
わたしはレコードじゃないよ。わたしはわたしだがね。それでもいいのかね? と、つまらないことを考えて、少し可笑しくなった。
若い方が、太めに連れられて、おずおずとやって来た。その顔には大きなクエスチョン・マークが浮かんでいた。
わたしの視線に気が付いたのか、若者の体がぴくっと震えた。何か太めに話しかけているが言葉がわからない。当惑しているが、どうやら納得したという感じだろうか。若者をリラックスさせようと、わたしは手を差し出した。
「あなたの、ビッグ・ファンです。あの、その、お会い出来るなんて思っていなかったものですから…」ようやく若者は言葉を絞り出した。
「ああ、そうかい」
「初めて買ったレコードは『ハイファイ・スノック・アップタウン』ってやつです。もう10年くらい前です。ジャケットに描いてあった狼が好きになったんです。寂しそうで……その頃、あなたのことが何もわからなかったので、ぼくは文章を書いて、〈この人の情報求む〉なんてやってたんです。ハハ……で、何故ここにいらっしゃるんですか?」
きっと、言いたいことが多すぎて、こいつは混乱してるんだ。言いたいことが多い、わたしにはその感じがいつもよくわからないんだがね。
「わたしはここからしばらく西に行った町に住んでるんだ。この店で、わたしの最近のCDを売ってもらっている。あとギターの修理を隣に頼んでたんで…」
「あなたのCD? どこにあるんですか?」
わたしの答えを遮って、若者は言った。それとも、わたしのしゃべりが遅いのか。
「彼のCDはここさ」と、わたしの代わりに店主が答えてくれた。カウンターの下にあるショーケースに、あと二枚だけ在庫が残っていた。そうだ、わたしはこれを追加するために来たんだ。
「ちょっと待っててくれるかね?」わたしはその場に断りを入れ、いったん車に戻ろうと外に出た。ひどい雪が降った先週ほどじゃないが、まだ昼間でもマフラーが要るようだ。ついでにマフラーも取って来よう。
ギター屋では、まださっきの母子がおやじをつかまえたままだ。
わたしのファンが東洋にいるなんてね。知らないふりをしたいわけじゃない。だが、わたしのレコードはあの国では一枚も出たことがないはずさ。
CDを入れた箱を抱えて、店に戻る。すると、若者は心の準備が出来たという顔をしていた。
「いくつかお訊きしたいことがあるんですが、よろしいですか?」
まいったな。ときどき、こういうことはあるが、得意じゃないんだ。
問「あなたの最初のアルバムは、フォークウェイズから出ていますよね? 確か64年でしたっけ? あの頃、まったく無名の白人青年があそこからアルバムを出すのはすごく異例だったと思うんですけど」
わたし「フレデリック・ラムゼイJr.が、わたしの家の近所に住んでいたんだ。何かのきっかけがあって、彼はわたしの歌を聴いた。で、彼の家で4曲を録音した。それをモーゼス・アッシュに聴かせたら、気に入ってくれたんだろうね。すぐに録音が決まった」
問「そのあと、ヤングブラッズのレーベル、ラクーンでソロを二枚出しますよね。あれはどういうきっかけだったんですか?」
わたし「ワーナー(ラクーンの親会社)で、わたしは三枚アルバムをつくるはずだった。ところが、連中はわたしの三枚目なんかもう要らないと言ったんだ。そのうちレーベルも無くなってしまった」
問「ホーリー・モーダル・ラウンダーズのアルバムで、ジャケットのイラストを描いたのは何故ですか?」
わたし「頼まれたからだ。あれがレコードのジャケットを描いた初めての経験だったかもしれない」
問「あの…、あなたが『ペンギンズ』でやっている口トランペット、モック・トランペットです。あれは今もやっているんですか?」
わたし「ああ、やっているよ」
問「(うれしそうに)あれを始めたきっかけを教えてください」
わたし「昔、若い頃に町でプリッツェルを売っていた。屋台でね。退屈でどうしようもない仕事だったよ。その頃からわたしの興味は音楽のことばかりだった。だから、この退屈を紛らすためにずっと音楽のことを考えていようと思ったのさ。あるとき、口でトランペットの真似をしてみたら、ひどく面白かった。だから、それからしばらく帰り道は、ずっとそれを続けていたね。そしたら、ミルス・ブラザーズの古いレコードを聴いたとき、なんとあの人たちも同じことをやっていたんだ。三人でハーモニーまで付けて。わたしはうれしくなった。それを今でもやっているのさ」
その質問に答えるとき、懐かしくなって、ついわたしも笑っていた。彼にはそれがわかってもらえただろうか?
問「歌を作り始めたのはいつからですか?」
わたし「小さいときから、ずっとだよ」
この答えは正しくないかもしれない。わたしは歌を作ったことはない。歌は出来てしまうものだと、言ってしまってもいい。だが、わたしは歌を作って歌うことを仕事にしている。そう答えてしまうことは誠実とは言えないだろう。
問「日本であなたのライヴのスケジュールをいろいろ探ってみたりするんですが、全然見つからないんです。ぼくも含めて、日本の連中は、あなたはめったに人前に出ないと思っています。神格化してるんです。フレッド・ニールみたいに」
わたし「わたしにはわからないね。今でも年に50回は演奏しているよ。先週も友達のパーティーに招かれて、二、三曲歌ったばかりだ」
伝説だなんて。勘弁してくれ。わたしは今ここにこうして自分のCDを売りに来てるじゃないか。
そう思ったが、一生懸命わたしのことを知ろうとして、なおかつ、わたしを喜ばせようとしているこの若者に対して悪い気持ちはしなかった。だから、こう言った。
「気にしてくれてありがとう」
若者は一瞬ろうばいしたように見えた。しばらく黙ったあと、意を決したように彼は言った。
「みんなが、みんながあなたを気にかけているんです。少なくともぼくのまわりでは」
それはやさしさから出た言葉なんだろうか。あるいは、彼は真実を言っているのかもしれない。嘘だとしても、わたしはくすぐったい気分になってしまった。
わたしという人間は、そうなってしまうと、もう固まって、尻込みしてしまう。
わたしたちはしばらく無言になった。
別れ際に、二人の東洋人にサインを頼まれた。彼ら自身の分だけでなく、彼らの日本にいる友人たちの分もということだった。そのとき、若者が言った。
「ぼくには、あの狼の絵を描いてください」
狼はわたしの作ったキャラクターだ。もう40年以上も一緒にいる。
あれはわたしの自画像だというやつもいる。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。確かなのは、わたしはあるときあの狼を描いてしまって、今でも描き続けているということだ。
二人が帰ったあと、CDの精算を済ませ、修理の済んだギターを受け取り、わたしは帰路に就いた。
モック・トランペットをやった日、わたしはプリッツェルを売っていた。そうだったな。あの若者に訊かれて、ずいぶん久しぶりにそのことを思い出した。わたしは誰かのために歌ったことなんかない。「だから、あんたの歌はいい、正直なんだ」と言ったやつもいる。
わたしにはわからない。わからないまま、60年以上も生きてきてしまったけれど。
来週には、またあの角の店で歌うことになっている。今日受け取ったギターを使うことにしようか。
日が傾いてきたが、暗くなる前に今日は家に着けるかもしれない。
(おわり)
これはフォーク・シンガー、マイケル・ハーレイと実際に出会ったときのことを元にしたお話です。事実に基づいたフィクションだとお考え下さい。
●
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
10 |
▲このページのTOP
▲Quarterly Magazine
Hi-Fi index Page
|