|
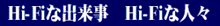
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|10
|11
| 12
| 13
|
●亜米利加レコード買い付け旅日記 13 大江田信
ハワイアンについて興味を持てば持つほど、様々なファンの方が様々に発言をして いることを気づく。ホームページをちょっと検索してみて、なるほどインターネット時代なのだと実感させられることも多い。おもわず軽々しい発言を躊躇させられるほどだ。
それでもハワイアンについて文章を書きたいと願ってきた。それもコンテンポラリー ・ハワイアンと称されるフォークやロック以降の影響下にある音楽について、思うところをまとめたいと思った。思いもかけず急速にハワイアンに傾斜することになった
ぼくの個人史もそこに織り込んでみたいと欲張った。ハイファイで偶然に入手したリ チャード・ナットの「Not Just Another
Pretty Face」に感激して、自身のレコード会社、エム・レコードからリイシューを決めた江村氏から、ライナー執筆の依頼を受
け、もちろんお受けした。これで思いのたけを書いてしまった。貯金を使い果たしてしまった気分だ。また勉強しなければ。
僕にとってなにかの一区切りとなった文章でもあり、そんな思いから2002年3 月15日発売「Richard Natto
/ Not Just Another Pretty Face」のライナーとして 執筆した原稿をここに再録させていただく。
ハワイに行ってレコードを買い付けてみようと思い立ったのには、大した理由はなかった。アメリカ本土行きの飛行機チケットを買おうとして旅行代理店をのぞき、その航空料金のうちで帰りにホノルルに立ち寄ることが出来ることを知ったからだ。渋谷の輸入中古レコード店、ハイファイ・レコード・ストアを切り盛りするようになって半年。そろそろ在庫も手薄となり、買い付けに出向く必要が生じてきた1994年秋のことだ。
そもそもぼくがハワイのポピュラー・ミュージックに関心を持ったのは、1973年頃 から毎週月曜日にFM東京で放送されていた片岡義男、安田南の両氏コンビによる深夜放送「きまぐれ飛行船」で特集されたプログラムを聞いてからで、ここで片岡氏がコメントされた内容や、選曲されたカジメロ・ブラザースなどの音源にとても心ひかれたことがきっかけとなっている。またこのころ勤務していた会社に、学生時代をハ
ワイアン・バンドとともに過ごした方が何人かおられ、インヴィテーションズやサー ファーズなどのコーラス・グループを教えてもらったこともある。ピーター・ムーン・
バンドのアルバムを入手したのも同じ頃だ。ほどなくして雑誌「ポパイ」が、サーフ・ ロックと称しカラパナを中心としたハワイ製ロックのキャンペーンを始めるが、サーファー達のファッションや車の趣味などになじめなかったぼくは、いまひとつ好きに
なれなかった。もちろんライ・クーダーとの競演を通して知ったギャビー・パヒヌイやその周辺のアルバムを入手して、折に触れては聞いていたものの、こんなところが
ぼくのハワイアン体験のすべてで、それほどの知識を持っていたわけではない。にもかかわらず、どうしてかよく分からないのだが、なぜかこのときハワイには素敵なポッ
プ・ミュージックがあるに違いないという漠然とした予感を抱いていたのだった。東京のアナログ中古レコード店には、トラディショナル・ハワイアンを扱う店が何軒かある。そうしたトラディショナルではない、なにか新しい切り口でハワイアンを扱う
ことは出来ないものかという気持ちが、ぼくを前のめりにさせていた。
西海岸からハワイに向かう飛行機がホノルル空港に到着するのは、夕方から夜半にかけての時間帯だ。ぼくらが到着したのも、もう夜遅い時間だった。空港内のレンタ
カー・オフィスで車を借りだし、フリーウェイを利用してワイキキのホテルに向かっ た。初めてのハワイで、初めての道筋、しかも夜。ただでさえ一方通行が多くてわか
りにくいワイキキ界隈を、やっとこさホテルまでたどり着いたときには、あたりはもう深夜にほど近い時間だった。
旅行代理店の紹介で予約を入れていたホテルは、ワイキキのビーチからほんの2ブ ロックほどのところにあった。せっかくのハワイに着いたのだからと、ぼくら、男二
人の一行は、ビーチの散策に出かけた。暗闇の向こうから、波の満ち引きの響きが聞 こえた。ジョギングをするランナーとすれ違う。海辺に張り出したレストランのさざめきが遠くに見える。ビーチに突き出た防波堤の先端まで歩いてみる。ほんのりと暖かく甘い空気が、頬をなでる。思わずクラッとなりそうなほど、魅力的な気分になる。
初めてのハワイはこんな風にしてはじまった。
翌日は朝からレコード・ショップを大車輪で廻った。この数年でオアフ島の中古レコード店の多くは閉店してしまい、アナログを探す楽しみはもう失われたも同然なの
だが、この時点では、まだ数軒のレコード・ショップが店を開いていた。勉強しなく ちゃという思いから、ピンとくるジャケットのアルバムはすべて買った。のちになっ
てハワイアン・コンテンポラリーの傑作と呼び慣わされCD化再発が行われたテンダー・リーフやレムリアのアルバムを買い付けて来たのも、この時のことだった。
東京に戻って買い求めたアルバムを聴くうちに、ハワイのレコードから流れ出す音楽にどうしようもなく惹かれた。聞けば聞くほどハワイのポップ・ミュージックには、
広々とした開放感があって、おおらかさがあり、充足感があることに気づく。ハワイアンの側に立ってアメリカ本土の音楽を見渡してみれば、なんとまあ孤独感に打ちのめされ、いらだちに満ち、ざらざらとした気分を発散し、ストレスにあふれているこ
とか。そうした避けがたい今日的なテーマを歌うことをとがめ立てることは出来ない ものの、なんとまあハワイの音楽には自然でのびやかな人間らしさがあることだろう、
ぼくはそう思った。まるで別世界だ。こうして何枚ものアルバムと出会ううちに、ハワイに暮らすアマチュアやセミプロに門戸を開いた一連のアルバム「Home
Grown」シ リーズ(1976年から1980年にかけてほぼ年に1枚ずつ4作が発表された。制作はホノ ルルのラジオ局KKUA)を聞いたことによって、新しい切り口のハワイアンという思いは、僕の中でひとつの形をなした。このシリーズ・アルバムはハワイに暮らす人たち
が、同じくハワイに暮らす人たちに向けて発信した音楽を創ろうというかけ声の元に集められたものだ。だから「Home Grown」。ハワイを誤解する人たちに向けた非ハワイ人たちによる趣味の悪い疑似ハワイ音楽ではない。ハワイ生まれ、またはハワイ育ちのポップ・ミュージックには、特別ななにかがあるに違いない。そんな確信に近いものが、ぼくの内に芽生えた。
それからもう一度、手元にあったトラディショナル・ハワイアンのアルバムを聴き直し、さらに新たに買い求め、そして山内雄喜氏という素晴らしいアーチストがわれわれのすぐ近くの日本にいることを知り、サンディのハワイアン・アルバム「サンデ
ィーズ・ハワイ」に込められた想いに敬服した。自宅の書棚をひっくり返して、片岡 義男のサーフィン小説を読み返し、また書店の本棚の前に立ち、ハワイについて書か
れた本を探した。単なる観光案内本の域を脱して、ハワイの歴史を踏まえて書かれた 書物はさほど数多くなく、いまのところ容易に入手出来るものとしては池澤夏樹氏に
よって書かれた「ハワイイ紀行」(1966年初版・のち2000年に「完全版」として新潮 文庫より刊行)に勝るものはないことに気づいた。同書のなかで池澤氏は、「楽園は可能か」と自問し、「楽園は可能だ、とハワイイはわれわれに教えている」と思うに至るのだが、このコメントはハワイのポピュラー音楽を考えるときにとても示唆的だと思うようになった。
こうして随分とメイド・イン・ハワイの音楽に親しんだためか、かつてはそれほどの共感を得ることが出来なかったカラパナの音楽に、この頃になるとぼくはとても親
しみを感じるようになってきていた。SSW的な資質を背負っていたマッキー・フェ アリー、ソフィスティケイトされたファンク〜ブラック・ミュージックに才能を見せ
るカーク・トンプソン、トラディショナル・ハワイアンに対する造詣をこののちに少しずつ明かしていくことになるバンド・リーダーのマラニ・ビリューと、よって立つところの違うアーチストが、だからこそお互いを親密に重ね会わせながら生み出した
音楽の構築に、実に真摯な想いが感じられる。それらを包み込むハワイのレイドバッ クした空気を感じる。サーフロックなどという、いかがわしい言葉に僕は目を奪われ
ていた。ハワイという場所でしか生まれ得ない芳醇なかおりをたたえた音楽だと、今 は改めて思う。
確かにトラディショナル・ハワイアンを演奏するアーチストは敬意を持って受け止 められるし、伝統音楽を演奏することの意味を、老若問わずハワイのアーチストは、
充分にわかっているはずだ。ことにハワイアン・ルネッサンスと呼ばれる70年代以降に起こった良きハワイの伝統を、音楽やフラ、レイ、食事やハワイ語に至るまで、幅
広く見直そうとした復権運動以降には、イズラエル・カマカヴィオーレをはじめとして、若い世代に熱心に伝統音楽を演奏するアーチストが数多く登場し、そうした気運
は今も引き続いている。
とはいえちょっと耳に挟んだだけではすぐハワイアンと気づかせないロック・ミュー ジックにも、AORにも実はハワイ音楽の魂が潜んでいるのではないか、と思い始めた。
歌詞にもそうしたことがよく歌われるということもあるが、ハワイの音楽の根本は、 自然と人の生への感謝がある。感謝とは、肯定でもある。音楽は「私」と「あなた」、
そして「わたしたち」の結びつきを広め、深めるためにある。そういう風に音楽が演奏され、そういう風に聞かれている。それはロック・ミュージックも、トラディショ
ナル・ハワイアンにおいても、それほどは違わないのではないか。ぼくはそう思うようになっていた。
本作の主人公、リチャード・ナットが組んでいたデュオ・チーム、「トマ&ナット」 のファースト・アルバム「Zoomin'
Away」(1978年発表)もまた、こうしてハワイで 入手してきたアルバムのうちの1枚だった。メインランドのシンガー・ソングライター
・ムーヴメントを受け止めているデリケートな内向する音楽センスと、ハワイ音楽に 共通して見いだせるおおらかな響きが共存している作品だ。伝統的なハワイアン音楽の影響は直接的には伺えないものの、屈託を包み込み、聞く者を慰撫するかのようなサウンドに、すぐれたトラディショナル・ハワイアンと共通する味わいを感じることが出来る。ぼくは驚嘆した。
そして繰り返しハワイに通うなかで得たとある友人が送ってくれた段ボール入りの レコード箱の中に、リチャード・ナットのアルバム「Not
Just Another Pretty Face」 は入っていた。そのころにはリチャード・ナットとデイヴ・トマの二人には、複数のアルバム・リリースがあり、彼らの音楽がシンガー・ソングライター・デュオ的なスタートから発展を見せ、80年代に入ると当時のロスアンジェルスの音楽シーン(日本ではA.O.R.と呼ばれることが多い)に呼応するかのようにシンセサイザーを主軸とした音楽に変わりつつあったこと、またそれは彼らに限らずハワイの音楽シーンに登場
したいくつかのバンドに於いても見られること、などを知るようになっていた。ロスアンジェルスに進出し、共同生活をしながら成功を目指したカラパナのようなケース
もあるし、ロスアンジェルス録音によるアルバムを数多くリリースしているセシリオ &カポノのようなバンドもある。そうしたトマ&ナットの試みは、残念ながらぼくの耳には成功しているとは認めがたく、決して十全とはいえないハワイのスタジオ環境
の不充分さをかえって際だたせているようにも聞こえ、残念な想いを持っていたこともある。
だから初めてアルバム「Not Just Another Pretty Face」を手にしたときには、まずおやっ?と思ったように記憶している。ファースト・アルバムのリリースの2年後、
80年というこの時期にソロ・アルバムが発表されていたんだという驚きが先に立った。 そしてレコードに針を乗せた瞬間に、おもわず脱帽した。ひっそりとしたたたずまい。
しゃれたコード・ワーク。やんちゃな彼の地のママがうかがえる作品もあるし、何らのエゴイズムを感じさせることなく、まるでハワイの美しい風景の一コマのように投
げ出されている「House Is Not A Home」もある。すばらしいアコースティックな響きに満ちあふれたSSWアルバムだ。気持ちのいいひとり。そんな言葉が胸に浮かんだ。
そしてぼくはリチャード・ナットのアルバム「Not Just Another Pretty Face」を、 これもまた素晴らしいハワイアンだと感じた。たしかに彼はひとりで音楽を演奏して
いる。しかし彼はひとりぼっちではない。社会に背を向けてはいない。音楽を演奏し終わった彼が、すぐそのまま振り向いてドアノブをひねれば、そこには仲間がいっぱ
い待っている部屋がある。そんな場所に彼の音楽はある。ぼくにはそう聞こえた。そ れはぼくにとって理想のハワイアンだった。
リチャード・ナットは1956年1月7日に、ニューヨーク州ウェスト・ポイントで生 まれた。両親はハワイの出身。陸軍士官学校に勤務していた父の仕事のため、少年時代は全米各地を転々とした。アラスカで過ごしていた8歳の時にビートルズの映画
「ビートルズがやってくるヤア!ヤア!ヤア!」を見た日から、何時の日にかミュー ジシャンとなりたいとの夢を持つ。ギターの練習を始め、バーズの「ミスター・タンブリンマン」やラヴィン・スプーンフルの「デイ・ドリーム」をカバーし、ドイツと日本人ハーフの少女、パティのために初めて歌を書いたのもこの頃のこと。ドラムの練習も始めた。13歳の時にはサウス・カロライナに引っ越し、スクール・バンドでは
サックスを学び、彼のポップ・ミュージックの好みには、ジェームス・ブラウンやドリフターズなど、ブラック・ミュージックの顔ぶれが加わった。
家族とともにハワイに戻ったのは1971年。このとき15歳。初めてバンドを組み、ビー トルズやアレサ・フランクリン、ハーマンズ・ハーミッツのナンバーをカバーした。
ギターを弾きボーカルもとり、一人で演奏するようになったのは、17歳の頃。プロのミュージシャンを目指して、より真剣に音楽に向かうようになった。初めてのソロ・
ライヴ・パフォーマンスは、ワイキキのバム・スター(おそらくコーヒー・ハウス、 あるいはクラブの名称)で行った。これが彼のプロ・キャリアのスタートだ。ビートルズ、スティービー・ワンダー、エルビス・プレスリー、ディーン・マーティン、トニー・タム・シング(ホノルル市東地区、カイムキの教会牧師で、彼が弾くガット・
ギターの響きに魅せられてリチャードもガット・ギターを手にするようになったという)が、彼の大好きなアーチスト達だった。
1973年のハロウィーンの夜、日系ハワイ人、デイヴ・トーマと出会った。ともにギ ターを持ち寄って二人で演奏を始めると、それは「まるで一種の魔法のようだった」
とリチャードは回想している。ふたりのハーモニー、ギター・コードの選択、また作 品づくりに至るまで、二人の息はぴったりとあっていた。6ヶ月間にわたって毎日、
毎日、二人は練習したという。
1978年にフラ・レコードからトマ&ナットのファースト・アルバム「Zoomin' Away」を発表。アルバムの制作にいたるプロセスに関わったスタッフとして、彼はマネージ
ャーのデイヴ・ケリー(Dave Kelly)とエンジニアのクリス・ヘンショウ(Chris Henshaw)、プロデューサーのジャック・ディ・メロ(Jack
De Mello)の名前を上げて いる。デイヴ・ケリーはボブ・ディランとも親交を持っていたフォーク・シンガーで、 リチャードは彼から歌作りの基本を教わった。どのような状況で、どのようなプレッ
シャーの中においても自分を歌作りに向かわせるプロとしての技、またサビ、フックなどのメロディ作り、全体の構成の作り方などを、彼とのつきあいの中から学んだと語っている。またクリス・ヘンショウは初期のポール・リビアとレイダースのスタッ
フ。ジャック・ディ・メロは、70年代以降の主としてコンテンポラリー・ハワイアンの数多くのアルバムに名前を見いだすことの出来るプロデューサーで、その多くの作
品はやわらかいポップな肌触りに共通している。
リチャード自身は、自分の音楽的な資質をホセ・フェリシアーノ、ビートルズ、ホー ル&オーツ、そして山ほどのブラック・アーチストのコンビネーションだとしている。
同時に実にしゃれたギター・コード感覚、とくにmajor 7thとmajor 9thの使用に関し ては、カーペンターズの影響が強いと語っている。major
7thは60年代半ば頃からアメリカに流行したボサ・ノーヴァに多く用いられたことから知られるようになった和 声で、major
9thも含めともに主としてジャズ〜ポピュラー音楽において用いられてきたもの。それをカーペンターズの音楽から学んだとするコメントには、彼らの人気
の絶頂期に同時代を過ごした世代の共感が伺えると同時に、日本ではポップス・グルー プとして捉えられることの多いカーペンターズの音楽を一皮むいてみると、実はアメリカン・ポピュラー・ミュージックの王道を貫く音楽感覚と高い技術が息づいている
ことを図らずも物語ることでもある。ポピュラー音楽が、ロック感覚を従えた新鮮な音楽として時代に即した衣裳へと着替えていくなかで、カーペンターズは紛れもなく
先頭ランナーの一人だった。リチャード・カーペンターが作り出すサウンドには、実はジャズやブロードウェイ・ミュージック、あるいはハリウッド映画音楽が伝統的に用いてきた高いレベルの音楽技術が、巧みに生かされている。このほかmajor
7thを 効果的に用いているアーチストとして、リチャードはアメリカ、アンブローシア、ジ ノ・ヴァネリ、デヴィッド・ゲイツ、ブレッドなどの作品を上げる。なお余談だが、
トーマ&ナットのふたりはピーターとゴードンの「愛なき世界」をmajor 7thとmajor 9thをふんだんに盛り込んでカバーしていたといい、そのサウンドをリチャードは大
好きだったそうだ。
本作品はトーマ&ナットのセカンド・アルバムとしてレコーディングされる過程で、 あれほどに息のあったところを見せていたはずの二人の間に仲違いがおきてしまい、
途中からリチャード・ナットのソロ・アルバムとして方向転換されたものだ。詳しくはクレジットを見てもらいたいのが、ほとんどの楽器はリチャード自身による演奏で、
レコーディングの実態は宅録に近い。ほどなく二人はコンビを復活させることになるのだから、なんとも思いもかけないプロセスで、思いもかけず生み落とされた作品ということになる。
今回の世界初のCD化再発に際し、リチャード自身から、アルバム収録曲について コメントが寄せられた。 松永良平氏による翻訳でお読みいただこう。
--- Track Notes By Richard Natto ---
実は、このアルバムはトマ/ナットのレコードとして最初は進められたものだった。 でも、レコーディングに入るにつれ、僕らの間に意見の違いが生じ、そして、トマ/
ナットはコンビを解消してしまった。僕はこのアルバムをひとりで仕上げ、自分のソ ロ・プロジェクトにすることにしたんだ。結局、僕ら二人は別の仕事でまた一緒になっ
たんだけどね。
1. Bish's Hideaway
スティーヴン・ビショップの曲が僕はとても好きだ。彼は素晴らしいソングライターだよ。このアルバムの曲をじっくり耳を澄まして聴いてもらえたら、デイヴ・トーマ
のギターや声が聴こえるはずだ。この曲を僕らは一発録りした。でも、コンビ解消が もとでデイヴの入ったトラックが使えなくなった。だけど、彼の声とギターはとても
薄く僕の方のトラックにも入っていて、漏れ聴こえてくるってわけさ。この曲はアル バムの中ではとても好きなもののひとつだ。
2. Typical High School Romance
デイヴと僕が“ホノルル・ラピッド・トランジット”っていうバンドを連れてアメ リカ中西部ツアーをしてるときに一緒に書いた曲だ。インディアナ州のコロンバスっ
ていう街で、僕らは長期間のギグをやっていて、そのときとある高校の隣に泊まって いたんだ。その部屋には高校を眺めるのにぴったりの窓があって、キッズたちの姿も
よく見えて、それで僕らはあの子たちの青春ってこんな感じなんだろうな、っていう ことを曲にした。この曲のリメイクを僕らは『トマ/ナット・リヴィジテッド』っていうタイトルのCDで録音した。僕はそのヴァージョンが大好きだ。豊かなアレンジと、
上質の録音、そしてトーマ/ナットのトレードマークであるナイロン弦とスティール 弦のギターに育まれた二つの声のハーモニー、これぞ本物のトーマ/ナットのサウン
ドっていうやつさ。
3. Waited For Your Love
ときどき、僕は自分の頭に浮かんだことを曲にすることがある。必ずしも僕の人 生や自分に起こった出来事についてだけじゃなく、本当に僕が頭でこしらえたことを。
これはそうやって作った曲のひとつだね。
4. Passin' Things
もっといい感じの録音でやれたらよかったな、って。フルセットのドラムとアコースティックのピアノを付けて。この曲は本当に大好きさ。じきにやり直すときがくると思う…。
5. Got To Be Somebody
サウンド的にはあんまり似てないかもしれないけど、この曲はビートルズの『サー ジェント・ペパーズ』に入ってる「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」がもとにあるんだ。
ちょっとジャズっぽいけど、歌詞の中身とかアレンジはあの曲なんだよ。蒸し返すよ うだけど、これももうちょっといい録音だったらなあ、カクテル・ドラムとか使って
さ…まあ、いいか、次の機会にしよう。
6. What'cha Doin' To My Heart
かわいらいいポップ・チューンだね。
7. There's Only You 良くできたラヴ・ソング。
8. Teenage Love Affair
歌詞を満足に歌いこなせてないけど、この曲のドライヴ感は最高だね。この曲の入っ てるアルバムは僕の大好きなポップ・ロック・レコードのひとつだ。リック・デリン
ジャーは最高だ(そのレコードではボビー・コールドウェルがドラマーなんだよね!) 。
9. Prisoner Of Rock & Roll
エルヴィス・プレスリーについての曲で、彼がロックンロール界の偶像として生き 続けていたらこう感じたに違いない、ってことを曲にした。“生な”ドラムを使いた
かったな、この曲には!
10. It's Crazy
またしてもラヴ・ソング…アルバムの埋め草さ。
11. House Is Not A Home
僕が何とはなしに歌い始めたら、プロデューサーのジョンがテープデッキの“録音” ボタンを押した。そのワンテイク限りの録音で、ジョンはそれを気にいって、アルバ
ムの最後の曲にしたんだ。
(訳・松永良平)
ときおり実現できなかったアイデアへの心残りが顔をのぞかせているところもあるが、なにより彼の人柄がしのばれるコメントだ。なんせリチャードは、自身が書いた
ラヴ・ソングについてほとんど語っていない。たぶんとてもシャイな人物なのだろう。
アルバム全体の肌触りもとてもひっそりとしている。強い自我を表明するというよ りも、ひっそりと丁寧に作品への愛情が表現されている。それがとても微笑ましく、
だからこそかえってリチャードの音楽への深い情熱が示されているようにぼくには感じられる。
このアルバムを発表したのち、二人の仲は復縁し、音楽活動を再開している。1982 年と84年に発表されたシングル2作、そして85年のアルバム「Not
Nights」において 聞かれるサウンドは、本作、あるいは前作にあたるトーマ&ナット名義の「Zoomin' Away」のアコースティックなそれとは大幅に違っていて、シンセ・ポップ、あるいはハード・ポップとも言うべきサウンドに変化を遂げた。それが彼らの同時代感覚だったのだろう。その後のも彼らは定期的にアルバムを発表しつづけているが、「Third
Time Around」以降の作品については、残念ながら筆者は未聴だ。ここでリチャード・ ナット、そしてトーマ&ナットのディスコグラフィをまとめておこう。
--- Albums ---
Zoomin' Away [1978 Hula Records] *
Not Just Another Pretty Face [1980 Mountain Apple]
Hot Nights [1985 Premiere Records] *
Third Time Around [1988 Hip Jam] Richard's Street [1990 Rd Music]
Won't take No for an Answer [1994 Tropical Jam]
Toma/Natto Revisited [1995 Tropical Jam] *
--- Singles ---
Without Your Love [1982 Premiere Records] *
All My Love to You [1984 Premiere Records] *
(* Toma/Natto名義)
トーマ&ナットのふたりは、ハワイ最大のスタジアム、アロハ・スタジアムで開か れたハート、ビーチボーイズ、エア・サプライなどのコンサートのオープニング・ア
クトを、同じくハワイアン・コンテンポラリーの愛すべきバンド、クラッシュと共に努めたり、数々のクラブやライヴ・ハウスでの演奏活動を続けてきた。84年のシング
ル「All My Love to You」は、ハワイのポップ・チャートで1位を飾り、またハワイのグラミー賞に相当するホク・ハノハノ・アワードにノミネートされたこともある。
そのほかにもリチャードはテレビやラジオのジングルやBGMの制作、スタジオ・ミ ュージシャンとしての仕事、他アーチストのCD制作など、数多くの仕事をこなしており、今も現役だ。といってもハワイで音楽の仕事を続けていくのは、並大抵ではな
い。多くはホテルやラウンジの仕事で食いつなぎながら自分をすりへらしてしまうか、 さもなければほかに仕事を持ちながら音楽をつづけていくことになる。ウクレレの名手、オータ・サンは長い間にわたってホテル仕事を続けながらも自分を持ち続けた希有なミュージシャンの一人だし、後者の代表格といえばギャビー・パヒヌイだろう。
時代が少しずつハワイを向き始めていて、それも60年代の興味本位なゆがんだまなざしではなく、エコロジカルな視線でハワイの文化を見つめ始めるという追い風を受け
ているとはいえ、トマ&ナットのようにハワイのアイデンティティをことさらに表明 していない音楽の場合は、なかなかに大変に生き方を余儀なくされたこともあるのか
もしれない。ともあれ22歳の長男ジョン・ポール、16歳の長女ハイリー、結婚して22 年になるグエン、そして愛する音楽に囲まれ、リチャード・ナットはハワイでの暮ら
しを存分に楽しんでいる。
ここ数年にわたって、ぼくなりにハワイアンを熱心に聞き続けてくるうちに、ハワイ音楽に対する自分の耳が変わりつつあることに気づいた。最近になってCD化され
た古典ハワイアン・シンガーの名花レナ・マシャードや、昨年のホク・ハノハノ・ア ワードを受賞した新進グループのマウナルアなど、ハワイへの想いをかき立ててくれ
るアーチストとの出会いもうれしいし、たとえば戦前ジャズがハワイアン与えた影響や、同じく戦前ハワイアンがメインランドのポップス与えた影響など、ハワイ音楽の成り立ちや拡がりへと興味も拡がった。こうしてコンテンポラリー、トラディショナ
ルなど、数多くのハワイアンに触れる機会を持てば持つほど、また再びリチャード・ ナットの「Not Just Another
Pretty Face」が実に独自の作品であることに思い当た ることになる。ふと振り向いたときに、いつもそこにある。そんな作品なのだ。折に触れて手に取り、静かな気持ちになる。青春の甘酸っぱい気分を思い返す。いつの日にか近いうちに、また再びこのCDをトレイに納めて流れ出す音楽を聴きながら、穏やかな気持ちが僕のなかに高まることを感じることだろう。このCDを手にした方たちに、リチャードの音楽と、そしてハワイとの素敵な出会いが生まれることを、心から願うものだ。
「時としてアメリカ本土の音楽には、いらいらした気分が強くはらまれていること を感じるけれども、あなたの音楽にはそうしたストレスがない」と感想を送ったぼく
に、リチャードから寄せられたこんなコメントを紹介してこの稿を終わろう。「たとえハワイがアメリカを構成するひとつの州だとはいえ、それは全く別世界。トロピカルな環境、さまざまな人々、文化の違い、レイド・バックした環境、それらのすべて
が歌に音楽に影響を与えている。ハワイで作る歌は、のんびりしていて静かになる」。 すぐれた音楽家は、ぼくらに最も素敵なハワイを描き出してくれる。すぐれた音楽家の作品によって、僕らは最も素晴らしいハワイを想像することが出来る。リチャード・
ナットと、愛すべきハワイに感謝しながら、彼の音楽を胸に深く沈めたいと思う。
(大江田 信)
●
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|10|11
| 12
| 13
|
▲このページのTOP
▲Quarterly
Magazine Hi-Fi index
Page
|