|
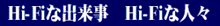
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|10
|11
| 12 | 13
| 14
|
●亜米利加レコード買い付け旅日記 14 大江田信
国分寺は新宿からJR中央線の下りで30分ほどにある郊外駅だ。今では駅ビルが出来て、しかも丸井やちょっとした洒落たコーヒー・ショップが進出するなどしてそれなりになってしまったけれど、僕が引っ越してきた1960年代の初頭では、ひっそりと息をひそめたような静かな住宅地にふさわしい小さな駅だった。改札口をでて、ほんの1分ほどのところにジャズ喫茶の「モダン」があった。入り口近くにテーブル席が5つ、奥にはカウンターという小体な店だった。今になってみれば、あのカウンターに座ってビールを飲んでみたかったものと思い返すものの、当時の僕はまだまだ坊ちゃん坊ちゃんした学生で、そんなことは思いもつかなかった。なにせ自宅からせっせと自転車をこいで、ジャズを聴きに通っていたのだった。
店は昼頃にエラ・フィッツジェラルドのライヴ・イン・ベルリンに収録の「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」と共に開店して、夜は11時ごろにオスカー・ピーターソン・トリオのアルバム「ブルー・トレイン」収録の「ヒム・トゥ・フリーダム」を流しながら閉店した。ぼくのなかでモダンはこの2曲と、そしてニーナ・シモンの「He
Was Too Good To Me」といっしょになって、記憶されている。
ニーナ・シモンは60年代のアメリカで、今ではアフリカン・アメリカンと呼ばれる黒人達の社会意識が向上していく過程において熱烈な支持を集め、そうした気運を体現するかのように激しい変貌を遂げたジャズ・シンガーだ。もともとはクラシック志望だった。英才教育に近いカタチでピアノを学び、しかし大学進学の夢がついえて、軽い気持ちでジャズを歌うようになる。始めはまじめでスクエアなジャズだった。旧来のジャズを好むファンからそれなりの熱い支持を受けはしたものの、彼女が本来持っていたものとジャズの世界とが相入れず、ニーナ・シモンは少しずつジャズからはみ出してしまう。そうするうちに、むしろ当時のロックやフォークを支持していた聴衆から、彼女の音楽への評価が高まった。コンサートは一種熱狂的な解放感つつまれるようになる。そうして彼女の急激な変化が始まった。政治的に急進的な発言もしている。政治意識が音楽にも、そのまま反映している。60年代の後半には、独自のジャンルとしか言いようの無いジャズとソウルとフォークとロックを一体化したような熱気に包まれた音楽を、一貫して発表していた。
「He Was Too Good To Me」は、彼女がまだジャズの世界にいた頃の歌唱と演奏で、ピアノの弾き語りにドラムとベースがバック・アップするという編成だ。RODGERS
RICHARDとHART LORENZによって書かれた作品で、つぶやくように歌うニーナ・シモンのボーカルが、まるでシンガー・ソングライターのそれのようだった。「彼は私には良すぎた人だった」とつぶやくフレーズの中に、男の優位性と女の気配りとして求められる日本的なあり方は少し違う男女の関係性を、まだ高校生だった僕もおそらく何となく感じ取っていた。たぶんそれはニーナ・シモンが歌っていたからだ。
モダンは決して流行っている店ではなかったから、いつでも座れた。コーヒー一杯で本を何時間読んでいても、いやな顔をさせることはなかった。武蔵美や東経大やらの学生の間に混ざって、中学から大学にかけて、ぼくはこの店で何年間かジャズを聴いて過ごした。ジャズをめぐる声高な議論が周囲にはあったし、様々な本も多く、随分そうした文章も読んだ。その影響で頭の片隅にジャズの理屈のようなものが、ぼくにもある。しかしそうした理屈とニーナ・シモンの歌声は、ぼくのなかでひとつにはならない。彼女の歌声が、どんな言葉よりも深く、強い。この曲のニーナ・シモンのボーカルは、つつましくせつなく痛ましい。心の内へすこしづつ踏み込んでいくような歌い振りが、好むと好まざるとに関わらず、歌とは結果として身を削ぐようにしながら歌われるものだと、おのずと語っていたように思う。
ジャズ喫茶「モダン」は、案の定、今はもう無い。
(大江田 信)
●
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|10
|11
| 12 | 13
| 14
|
▲このページのTOP
▲Quarterly
Magazine Hi-Fi index Page
|