|
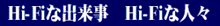
| 1 | 2
| 3 | 4
| 5 | 6
| 7 | 8
| 9 |10
|11 | 12
| 13 | 14
| 15
|
16 |
●亜米利加レコード買い付け旅日記 16 大江田信
K市のダウンダウンから20分ほど西側を東西に走るM通りは、センスのいい街並みとして、界隈では良く知られた一角だ。談笑する人々でいつも込み合っているカフェや、リズナブルな値段で美味しい料理を食べられる中華料理店、こざっぱりしたフランス料理店、ちょっとシックな洋服が並ぶレディース・ショップ、フェミニズム関連の本・雑誌などを扱う書店、新作を公開している映画館、アコースティック・ギターなどを扱う楽器店などが軒を連ねている。いつも人通りが多く、にぎわっている街並みだ。そうえいえばふと気づくと、アメリカの街ならば何処でも見かけるファースト・フードのチェーン店を見かけない。
「去年の冬に、M通りにマクドナルドが出来る話が持ち上がったんだ。M通りにはマクドナルドは似合わない。そんな気運が盛り上がって、マクドナルドに申し入れた。マクドナルド側も納得して、出店を取りやめることになったんだよ。誰もがそう思っているよ、この今のままの環境を大事にしようって。
そうそう、この店は、一日中、朝食が食べられるんだ。良い店だ」。ジムはガラス張りのカフェの方を向いて僕に示した。トーストかベーグルに、バターとジャム。またはチーズ。甘いマフィンかドーナッツのこともある。ベーコンかハム、もしくはソーセージを添えた卵焼き。そして暖かいコーヒー。とりたてて言うこともない普通の食事だけれど、アメリカ人にとって、朝食というのは、どこかしら特別なものなのだろう。そこには家庭の香りがする。
ジムはM通りに店を出しているレコード・ショップのオーナーだ。ちょうど僕と同年の生まれ。同時代の音楽経験を持っていることもあって、とても気楽に話をしている。K市を訪れ、彼の店を訊ねるときには、店を閉めた後に食事に出向くことが恒例だ。今回は、彼のオススメで、ひいきにしているインド料理店でカレーを食べることになった。総勢5人。ハイファイのスタッフと、ジム。そしてこの街で暮らしている日本人女性、
Cさんもメンバーに加わった。
インドのビールやお茶、それから思い思いのカレーをオーダーし終わると、雑談が始まる。松永クンが前々から、誰か音楽に詳しいアメリカ人の方に聞いてみたかった質問があった。それを聞いてみようということになる。「モンキーズの歌にLast
Train To Clarksville(邦題は「恋の終列車」。1966年11月全米1位の大ヒット)ってあるでしょ?Clarksvilleの駅まで付くのには、主人公はどれくらいの時間がかかるのだろう?」
ジムはこんな話を始めた。「あの歌の背景にあるのは、ベトナム戦争に召集される若者の心情だ。And I don't know
if I'm ever coming homeって、いう歌詞があるだろ?もしかするともう家に戻れないかも知れないというのは、ベトナム戦争に行くという意味だ」。ぼくらは、はっとして胸を突かれた思いがした。
「ポップ・ミュージックにベトナム戦争の影がどのように影響 しているのか、調べてみたことがある。そうした最初の歌は、Paul
Revere And The Raidersの『Kicks』(1966年春に発表され最高4位を記録したヒット曲)だろうと思う」。
僕も聞いてみたかった質問がある。アメリカで兵役が任意の意志に基づく志願制となったのは、ベトナム和平が締結された後の1973年のこと。それ以前は徴兵制が実施されていたはずだ。ジムは徴兵されたのだろうか。「高校を出る頃に、徴兵されるかどうか、抽選があった。名前の頭文字を元にリストが作られ、たとえば頭文字J
から一人、兵役に就く人間がピックアップされたんだ。運良く、ぼくは徴兵されなかった。ラッキーだった」。
たしかに今では兵役は、任意による志願制ではある。しかし義務兵役サービス(Selective Service System、通称SSS)に登録されたリストから、アメリカ政府は任意に徴兵をすることができる。将来起こりうる戦争への徴兵を公平に行うために、すべての18歳以上、26歳未満の男性は兵役登録をしなければならない。もちろんその全員が戦争に行くわけではなく、あくまでも兵役は志願制だが、政府がいざという時の連絡先をリストとして保持するために、この登録が行われる。登録を拒否したものは、31際まで学生ローンを受けられない、あるいは政府関連の仕事につけないなど、社会的な制約がつきまとう。女性には、SSSへの登録の義務はない。これがたった今2003年のアメリカにおける現実だ。
そういえばジョン・デンバーが書いて歌った後、Peter Paul And Mary がカバーして全米1位のヒットとなった「悲しみのジェット・プレーン」(1969年全米1位。原題は「Leaving
On A Jet Plane」)も、ベトナムに兵士として向かう男性が主人公の歌に違いないと僕は想像していた。P,P&Mが歌うときには、女性のマリーがリード・ボーカルをとるので、別れを前にした女性の悲恋の歌にも聞こえるが、これを男性の心情を代弁しているものとして聞き取ると、また違う風景を描き出す。主人公は「
I hate to go」と歌い、「I don't know when I come back again」とつぶやく。
「確かにあの歌もベトナム戦争を背景にした歌だ。徴兵される者に送られてくるのは、バス・ステーションから軍事基地までの切符か、または電車の切符なんだ。タクシーのチケットは、送ってこない。召集は突然にやってくる。翌朝には基地に向かわなければならないこともある。あの歌のシーンに、『タクシーがホーンを鳴らしながら待っている』という一節があるだろ。そのバス・ステーション、あるは駅まで行く
早朝の道すがらに、彼は女性の家に立ち寄った。作者はジョン・デンバーだね?ジョンが兵役に向かう男に与えた恋人との別れのシーンがあの歌だ」。
なるほどLast Train To Clarksvilleの主人公の場合も、時間が切迫している。彼は夜中の終電車に乗ってクラークスヴィルに向かおうとしている。明日の朝には、徴兵に応じなければならない。残された時間は、少ない。ほんの数時間しか二人で過ごせない。せめて朝食のコーヒーが香るキスをしたいと、必死の想いで彼女に電話をかけている。駅の中は騒がしくて、電話の向こうが聞き取れない。おそらくこの歌の全体の響きからすると、彼はたぶん彼女に会うことは出来ないのだろう、と僕は思う。
ポップ・ミュージックにベトナム戦争の影が落ちているということは、しかもそれがヒット・チャートの高位にまで支持されたということは、それは社会に宿っていた不安がふとした拍子に日常的な歌のひとつにこぼれ落ちたことを示している。だれもがその歌に隠された真実を、知っていたのだ。
食事を終えた僕らは、もと来た道をジムの店まで戻った。M通りに交差するアベニューを渡る手前、その角にはバグダッドという名のバーがある。もう50年近い歴史を持つ店だ。通りの面した側を大きなガラス張りにした店の中では、ピザを食べながらビールを楽しむカップルが見える。バーを左手に見ながら、店の奥に入っていくと、そこにボール・ルームがある。
「バグダッドだ。今のうちに行っておいた方がいいか もしれないぜ。」
「ああ、イラクの首都の名前だ。」
「そのうち、無くなっちまうぞ」とジムはつぶやく。「戦争が始まる。まったくブッシュは、どうしょうもない。ワシントンの今の政権は、オイル・コネクションで出来上がっている。ブッシュにしても、チェイニーにしても、石油利権でつながっているだけだ。自分たちの利益のことしか考えていない。そのうちにアメリカは世界の嫌われ者になる」。
もともとの血筋がユダヤ系であることを、ジムの名字が示しているものの、自らの宗教的な趣旨をことさら示すことはない。むしろ世界にはさまざまな音楽文化があり、それぞれの民族にはそれぞれの音楽があること、そうした音楽が共存し影響しあうことの楽しさを彼は知っているし、それは宗教観に於いても同様と見受ける。我が物顔に自身のみを誇示する宗教の偏狭さを好んでいない。そして
同時に21世紀の戦争の原因の一つが、宗教にあることを彼は知っている。ふとつぶやいた言葉が、印象的だ。「We're living
in the dangerous world」とジムは言う。それにしてもどうして宗教指導者はこの期に及んでさえ、戦争を止めろと言わないのだろう。
夜は9時を廻った頃だっただろうか。こんな時間に、街の目抜き通りをのんびりと歩きながら、それも通りのウインドウをのぞき込みながらする会話にしては、ちょっと不似合いかも知れない。行き過ぎる人々の数も、決して少なく無い。しかしこの街では、だれも我々の会話をとがめる人はいない。
アル・カイーダのテロの危険性が指摘され、テロ警戒の危険度レベルが一段階高い「テロ攻撃の高い危険がある」オレンジになると、ニューヨークの週末では、レストランもがらがらだったとテレビが報道している。すぐそのあとで、またブッシュの演説の光景に画面が変わる。戦争に向かう道筋とアメリカの威信を、彼は美しい言葉でレトリックにくるんでいる。大観衆を前にマイクの前で声高に語られる言葉はいかにもうさん臭く、こちらの胸の奥まで届いてこない。いつだって真実とは、ひっそりと小声で語られるもののはずだ。まるで歌のひとつのフレーズのように、それは静かな広がりを見せてきた。
2003年2月。ジムと僕らはこんな会話を交わしている。確かに危険に満ちた世界に、僕らは生きている。世界はあやういバランスの上に成り立っている。それでも僕らは再会を約束する。ジムと僕らは、いつものように握手をして、いつものように別れる。
(大江田 信)
●
|1
| 2 | 3
| 4 | 5
| 6 | 7
| 8 | 9
|10 |11
| 12 | 13
| 14 |
15 |
16 |
▲このページのTOP
▲Quarterly
Magazine Hi-Fi index Page
|